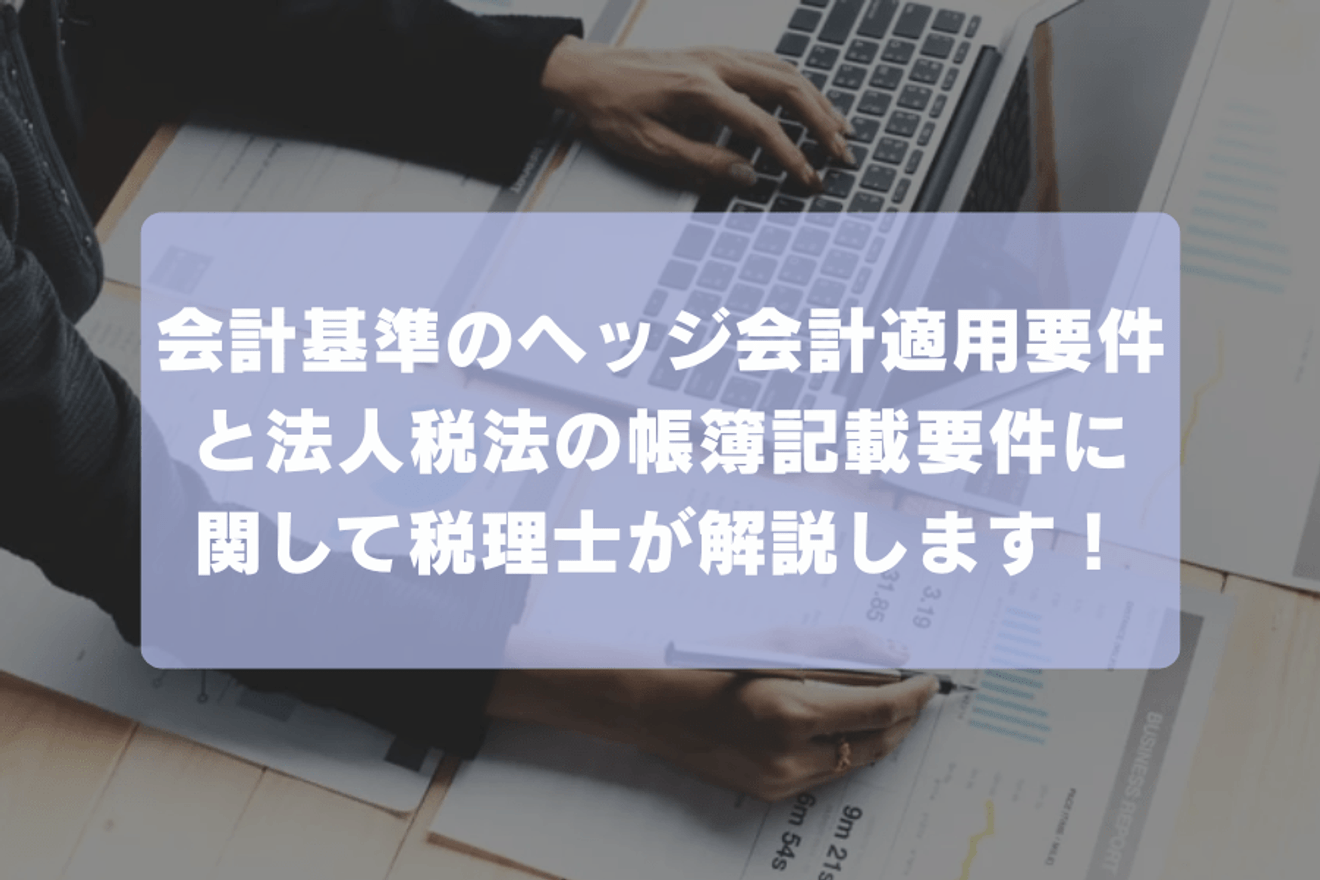
会計基準のヘッジ会計適用要件と法人税法の帳簿記載要件に関して税理士が解説します!

2025.11.11
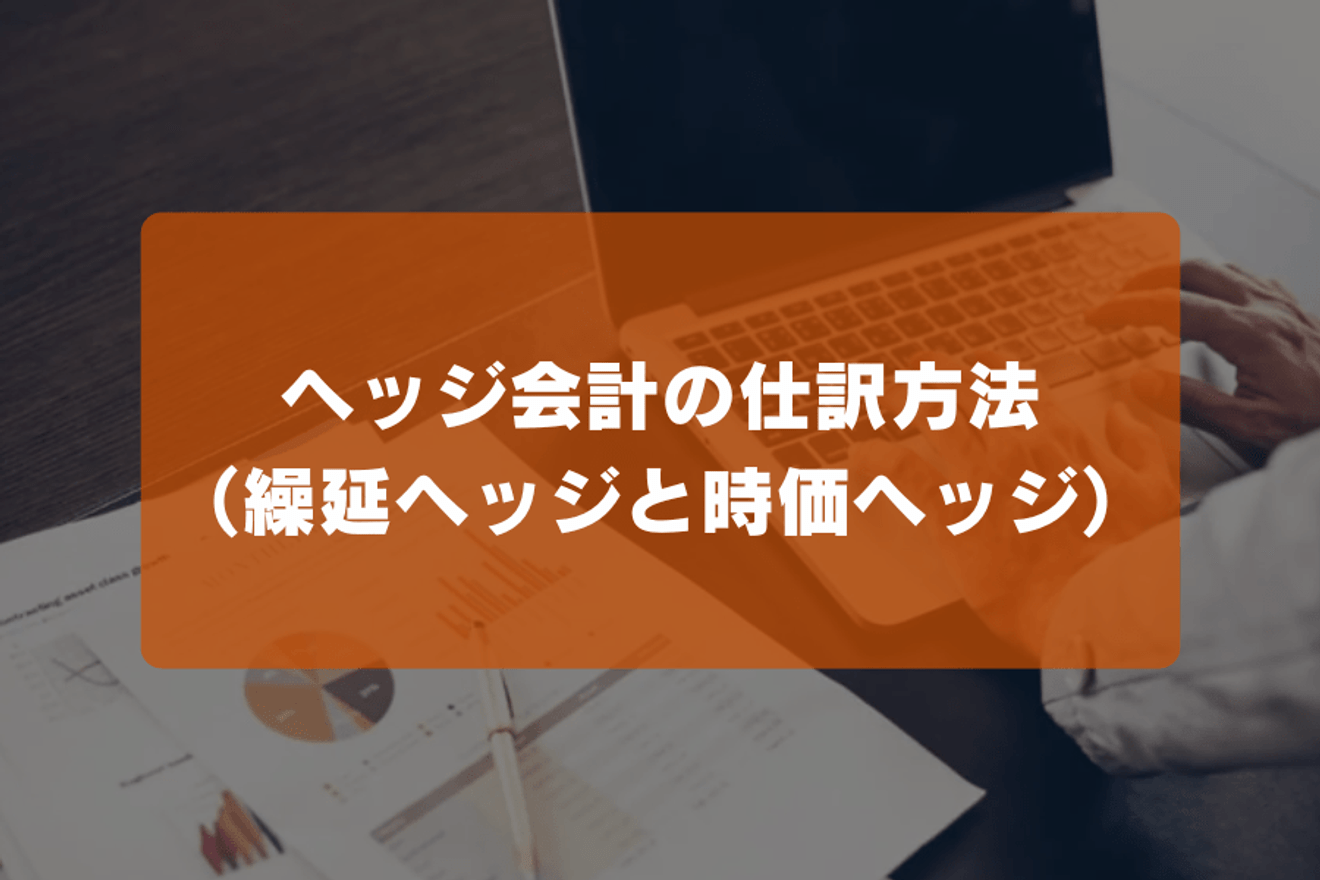
ヘッジ会計の仕訳方法(繰延ヘッジと時価ヘッジ)

2025.11.11
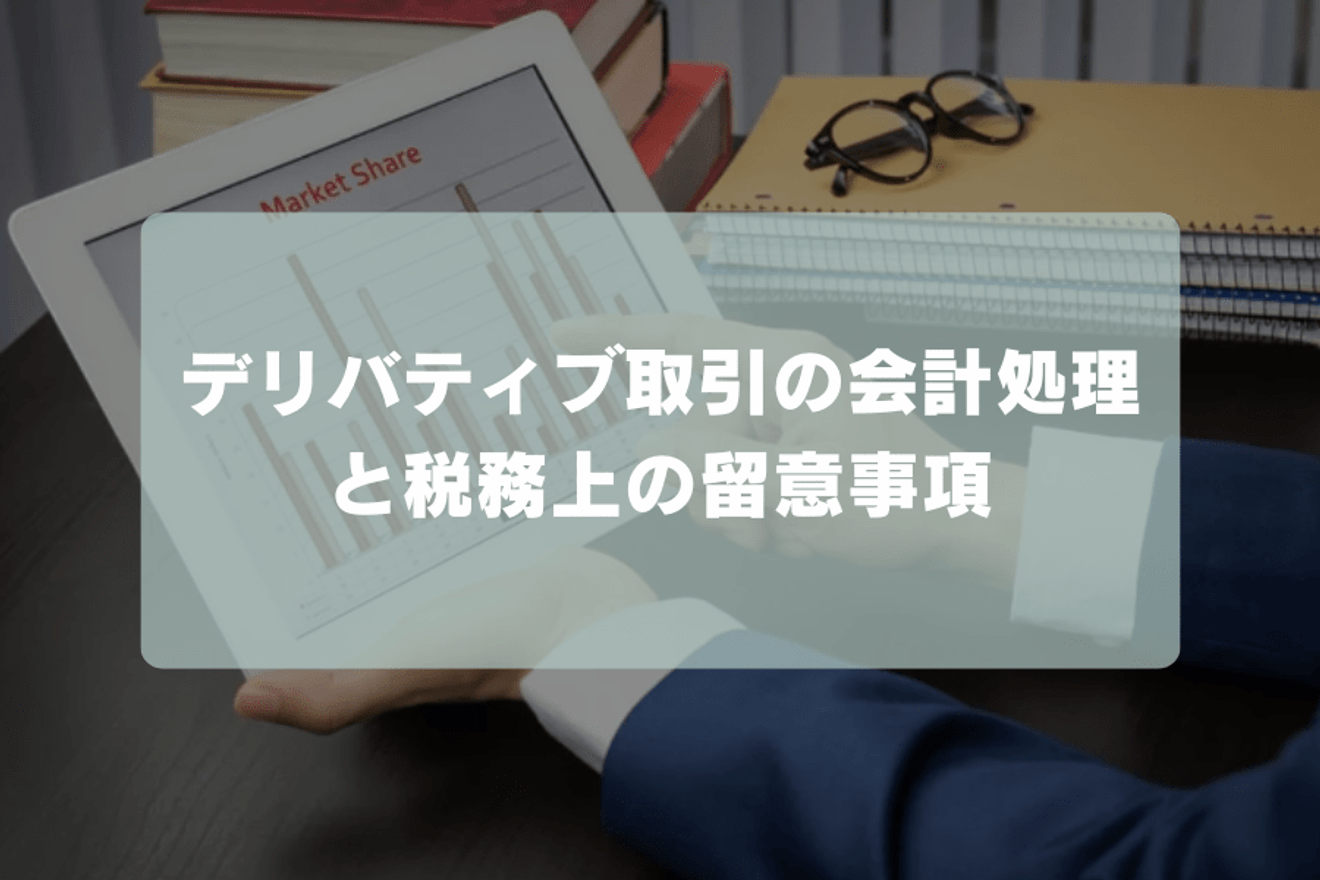
デリバティブ取引の会計処理と税務上の留意事項

2025.11.10
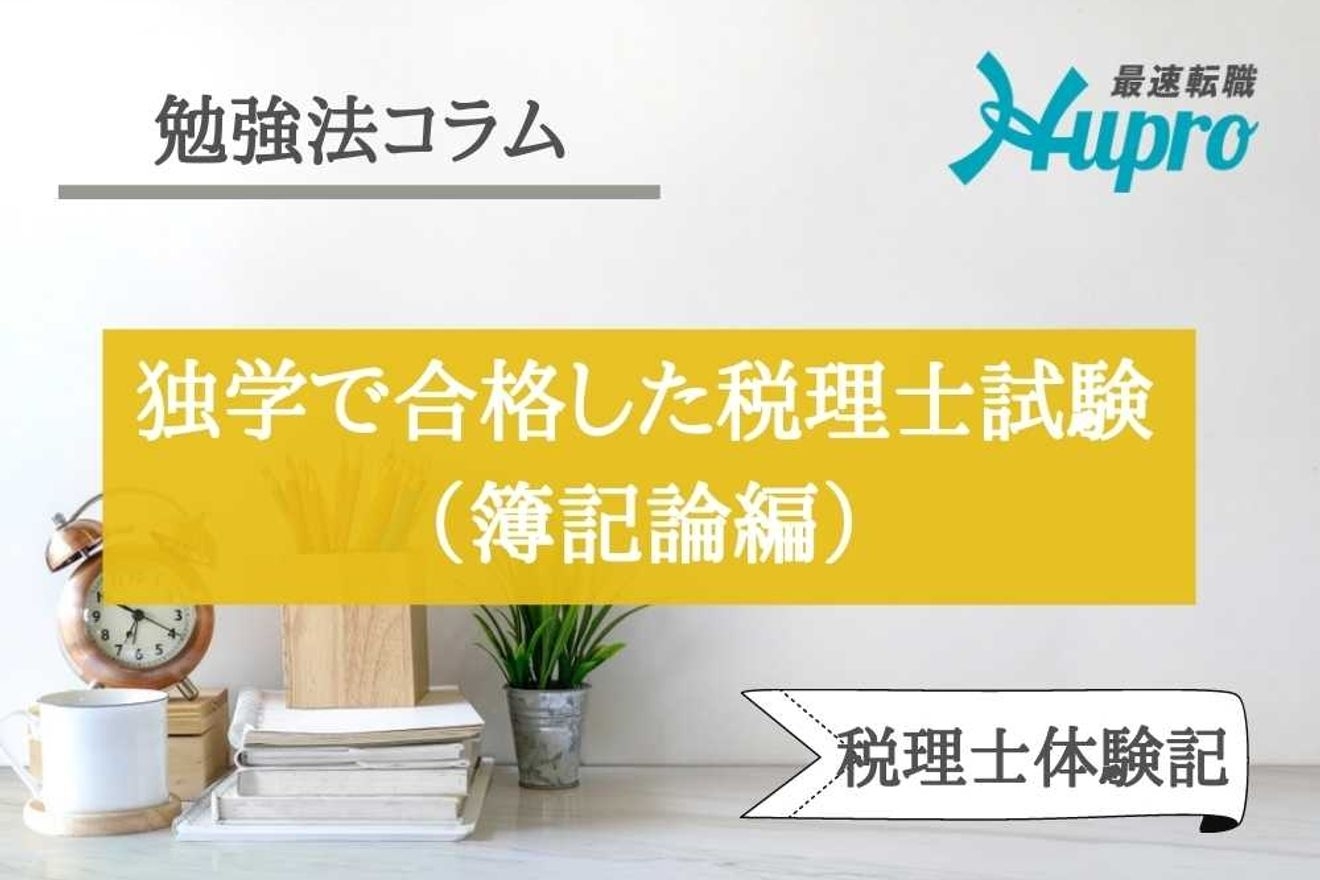
独学で合格した税理士試験簿記論の勉強法

2025.10.31

取得形態で異なる有形固定資産の取得原価の決定方法!税理士が解説!

2025.10.31
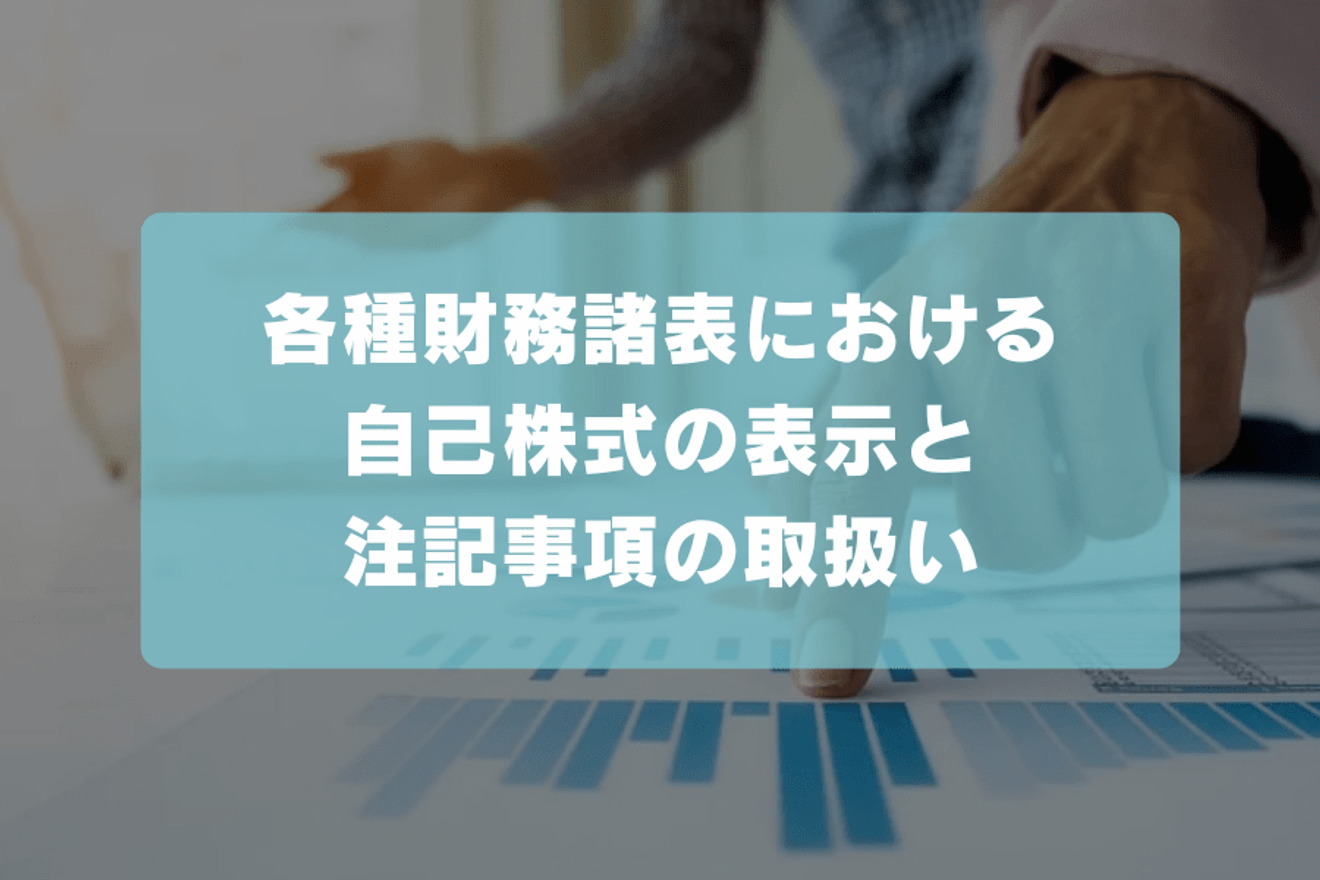
各種財務諸表における自己株式の表示と注記事項の取扱い

2025.10.31

敗因分析からの税理士試験消費税法のリベンジ合格法をご紹介

2020.11.14

税効果会計の資産負債法と繰延法の違いと資産負債法の採用理由

2020.10.30

過年度遡及会計基準導入による臨時償却の廃止と現行の会計処理方法

2020.08.14

特別償却(即時償却)と特別償却準備金の会計・税務処理の違い

2020.08.07

自社利用ソフトウェアの会計処理と法人税法の取扱いの相違点

2020.07.19

企業会計における開発費と研究開発費の違い

2020.07.07

賃貸等不動産の範囲と時価以外に必要な注記事項を押さえよう

2020.07.07

上場企業と非上場中小企業で違う?減損の兆候の把握とは

2020.06.09

企業会計の減損損失と法人税の評価損の計上場面の違い

2020.05.29
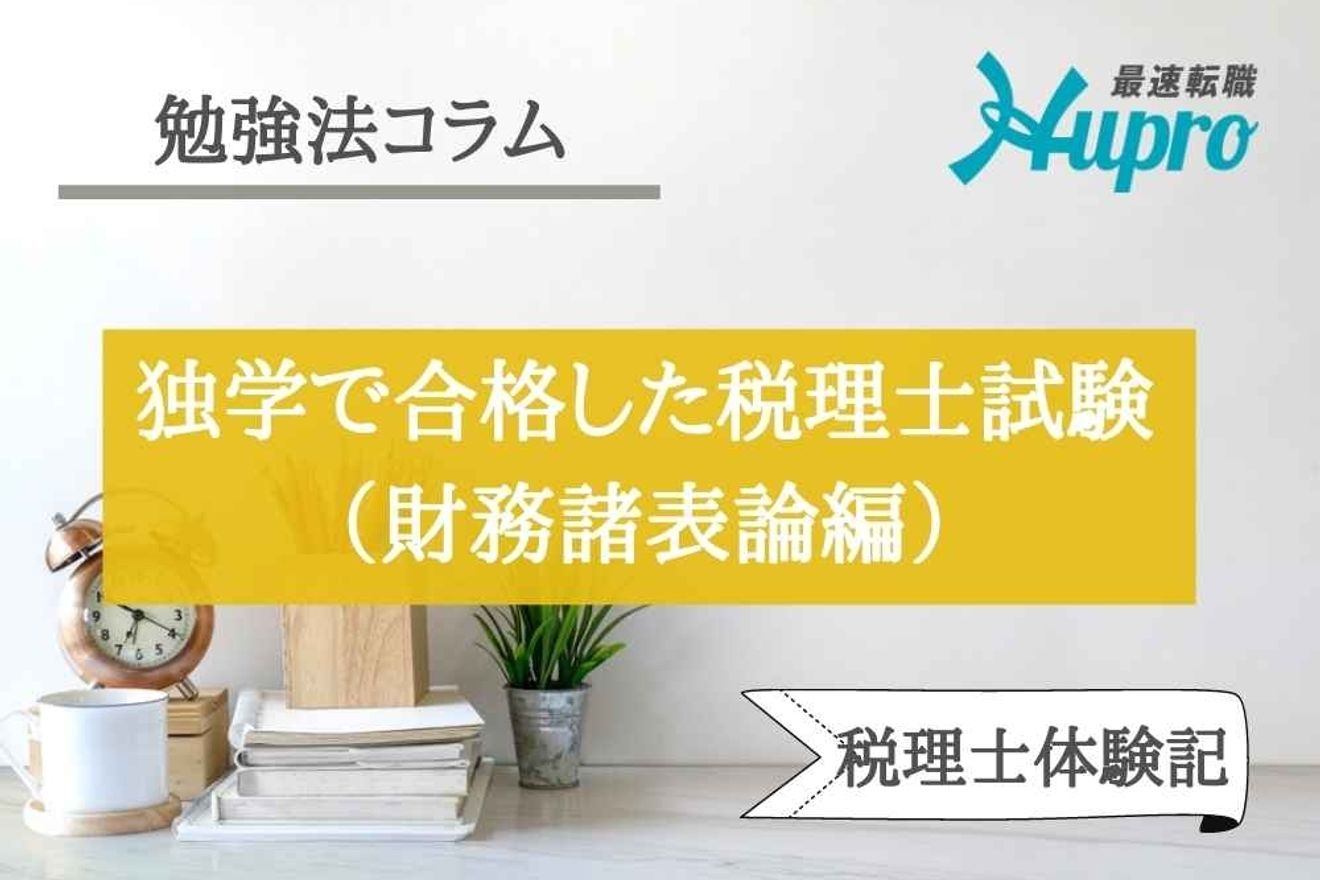
独学で一発合格した税理士試験財務諸表論の勉強法

2020.03.23
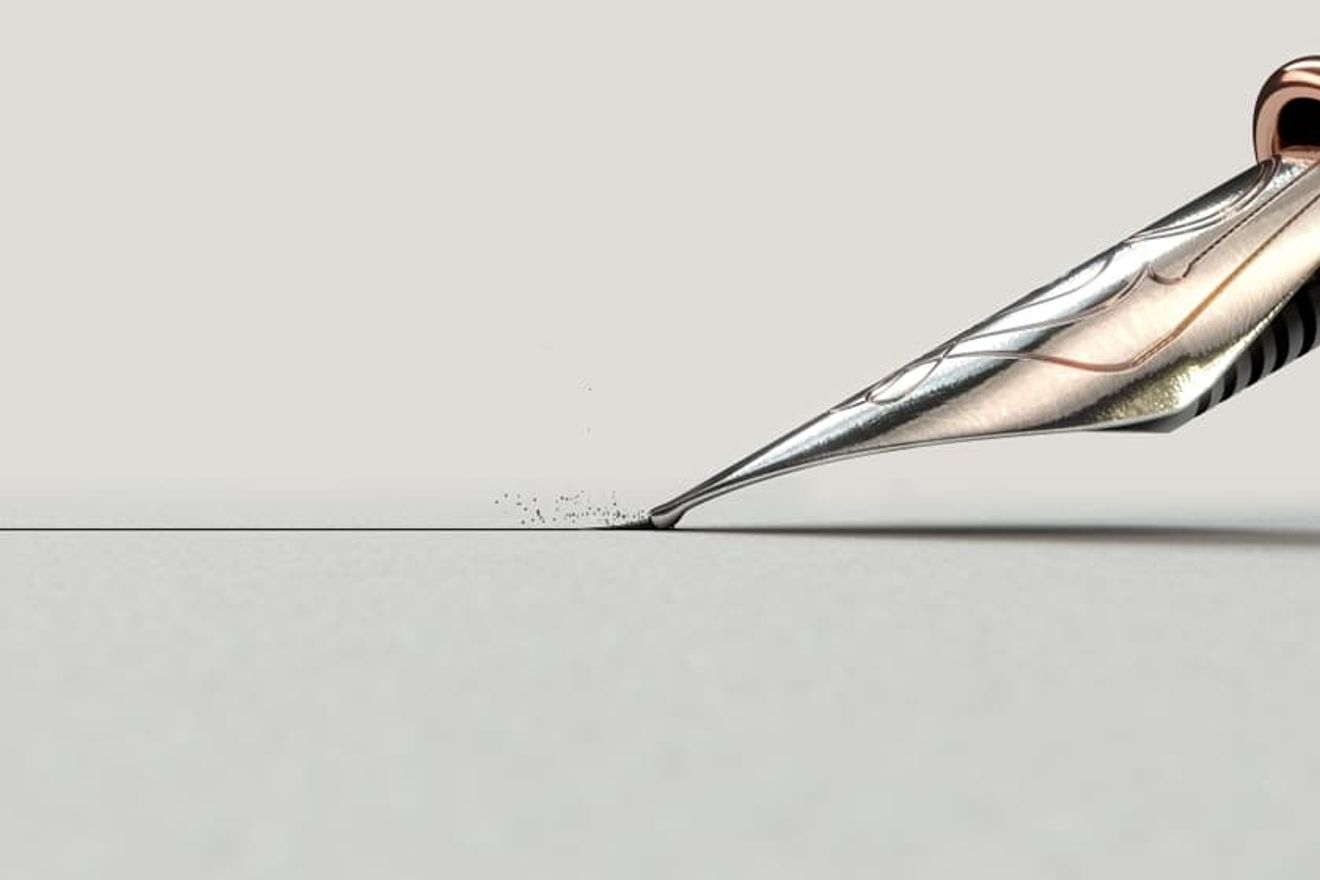
税理士試験は勉強道具にもこだわろう

2020.03.06
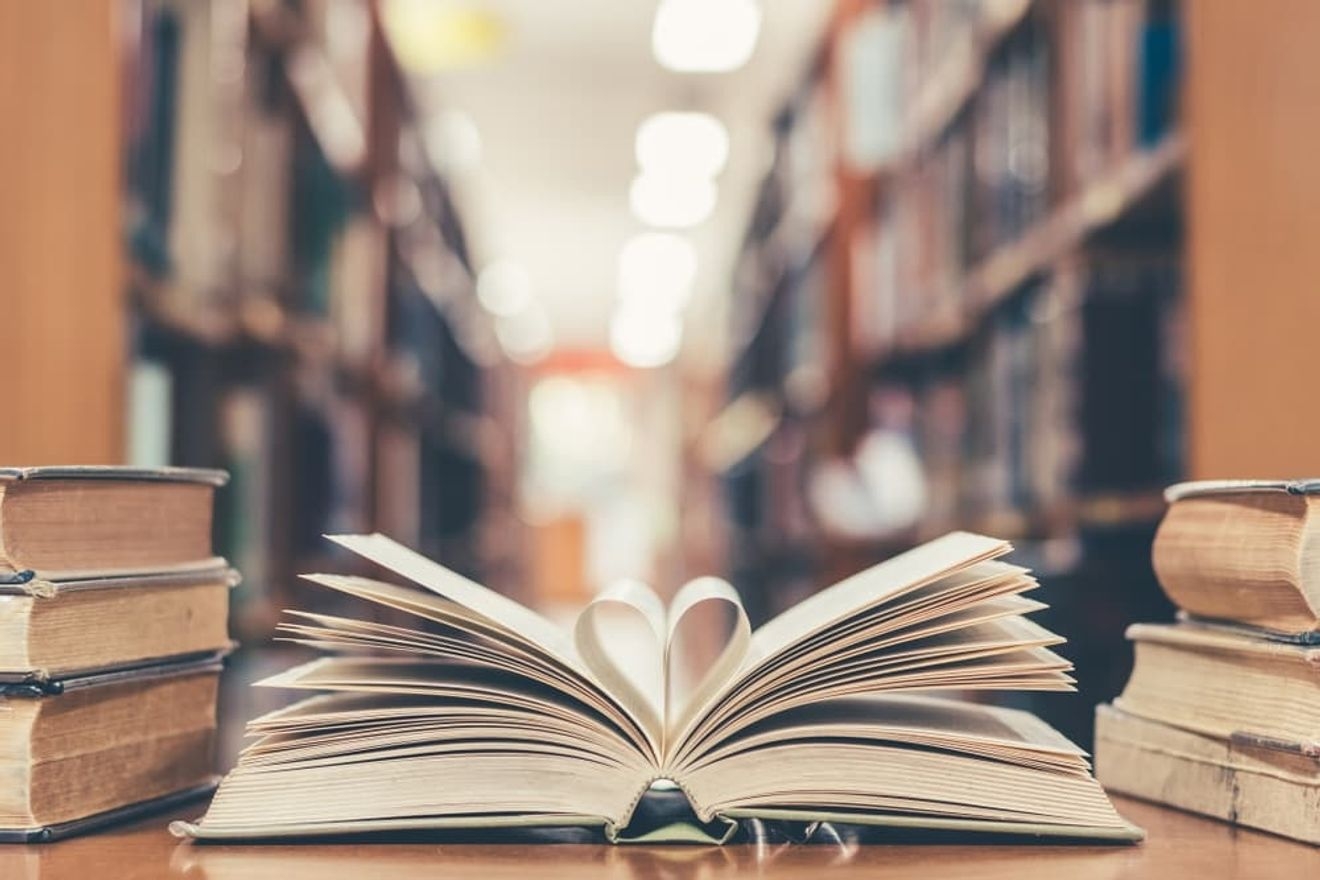
税理士試験受験生向け会計税務オススメ書籍

2019.12.12