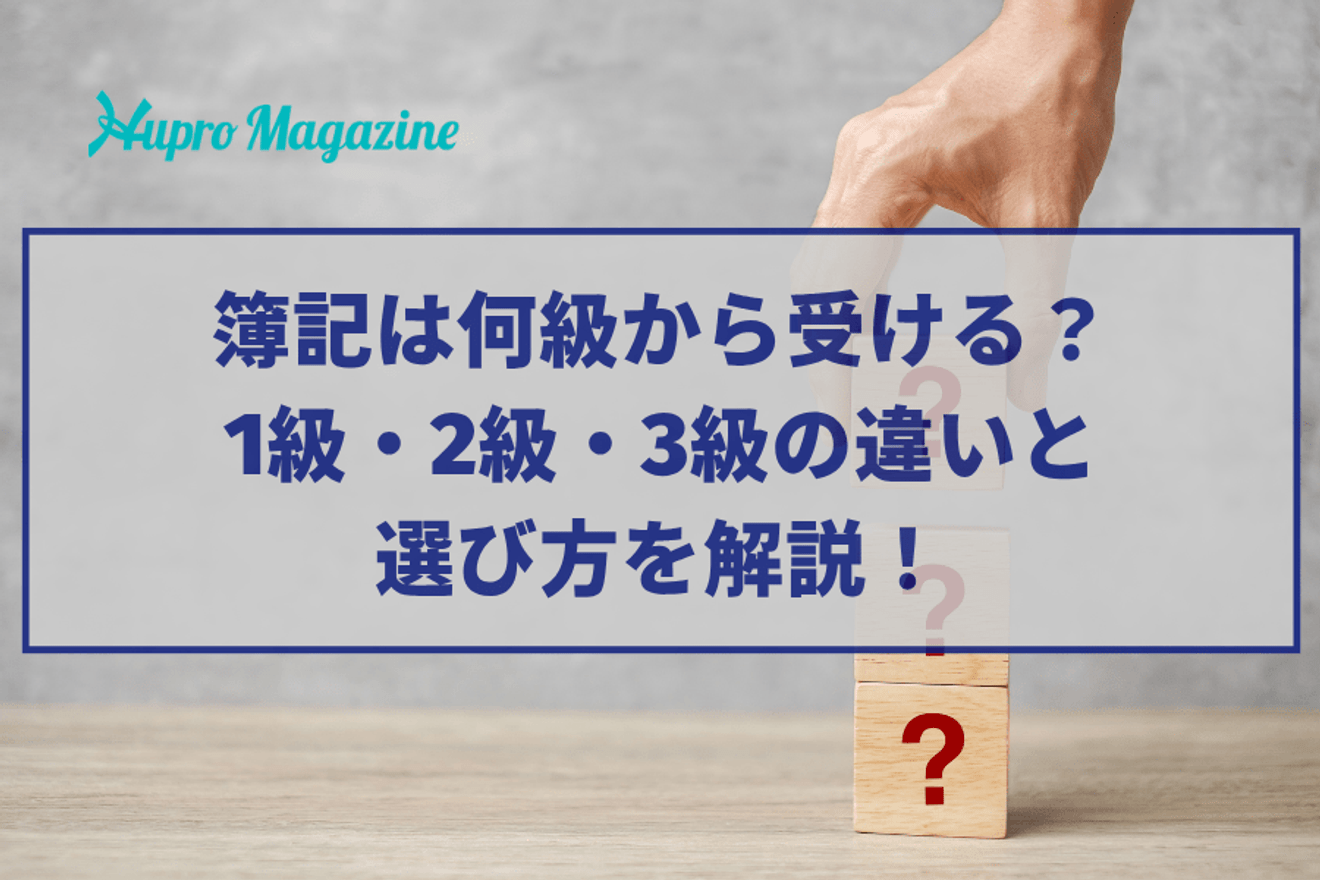
「簿記を勉強してみたいけど、何級から受ければいいの?」
そんな疑問を持つ人は少なくありません。簿記検定はそれぞれ難易度や内容が異なり、目的によって最適なスタートラインも変わります。ここでは、それぞれの級の違いや特徴、どの級から受験すべきかをわかりやすく解説します。
簿記とは、企業の経済活動を帳簿に記録し、計算・整理して、財務諸表を作成するためのスキルです。日々の取引を帳簿に記録し、最終的には損益(いくら儲かったか)や財産(今どれだけ資産があるか)を把握できるようにします。企業の経営成績や財政状態を把握するために、経理部門だけでなく、営業や企画など様々な部署で必要とされます。
簿記には「日商簿記」「全経簿記」「全商簿記」の3つの検定試験がありますが、この記事では特に社会人や転職希望者、経理職を目指す方におすすめな日商簿記について解説していきます。
結論から申し上げると、簿記の知識が全くない初心者の方は、3級から受験することを強くおすすめします。なぜ3級から始めるべきなのでしょうか。まず第一に、基礎知識をしっかりと固めることができるからです。簿記3級では、簿記の基本概念や専門用語を体系的に学習でき、仕訳の基本ルールが身につきます。これらの基礎知識は、上位級を受験する際の土台となる重要な要素です。
第二に、挫折リスクを大幅に減らすことができます。いきなり2級から始めると、専門用語の多さや複雑な概念に混乱してしまう可能性があります。段階的に学習を進めることで、モチベーションを維持しながら着実にスキルアップできるのです。
経理実務や学習経験がある人はすでに簿記の基礎を理解していることから、簿記2級からはじめることをおすすめします。簿記3級では、仕訳の基礎や簡単な帳簿作成など、経理の基本を学びます。しかし、実務経験がある人なら、日常の業務を通じてこれらの知識はすでに習得済みの場合が多く、3級の内容は「既知の情報」と感じることが少なくありません。
また、2級のテキストや講座は、3級の内容を前提にしているとはいえ、重要な基礎事項には丁寧な説明が加えられています。実務経験+2級の教材で、3級の範囲も自然に網羅できるのが実情です。
こうした理由から、経理の実務経験がある人は、すでに簿記3級レベルの知識を備えていることが多く、2級から学習を始めることで「効率的かつ実務に役立つ」資格取得が可能になります。
簿記1級
| 対象 | 初心者・学生・事務職希望者 |
| 学習内容 | 商業簿記の基礎(仕訳、帳簿、決算) |
| 難易度 | やさしい |
| 合格率 | 約40~50% |
| 学習時間の目安 | 約50~100時間 |
| 試験形式 | CBT(ネット試験)または紙筆試験 |
| 受験料 | 2,850円(税込) |
| 就職・転職の評価 | 履歴書に書ける入門資格 |
簿記2級
| 対象 | 経理実務者・転職希望者 |
| 学習内容 | 商業簿記+工業簿記(実務レベル) |
| 難易度 | やや難しい |
| 合格率 | 約15~30% |
| 学習時間の目安 | 約150~250時間 |
| 試験形式 | CBTまたは紙筆試験 |
| 受験料 | 4,720円(税込) |
| 就職・転職の評価 | 多くの求人で「必須」または「優遇」される(税込) |
簿記3級
| 経理実務者・転職希望者 | 経理責任者・会計士・税理士志望者 |
| 学習内容 | 商業簿記・会計学・工業簿記・原価計算(高度な理論) |
| 難易度 | 難しい(高度) |
| 合格率 | 約10%前後 |
| 学習時間の目安 | 約500〜800時間 |
| 試験形式 | 紙筆試験のみ(年2回) |
| 受験料 | 7,850円(税込) |
| 就職・転職の評価 | 管理職・専門職・国家資格受験資格に有利 |
簿記3級は、簿記のみを対象とした入門レベルの資格です。小規模企業の経理処理や基本的な仕訳、試算表・精算表の作成、そして貸借対照表・損益計算書の作成などが主な学習内容となります。
難易度については、合格率が約40-50%となっており、他の国家資格と比較すると比較的取得しやすい資格と言えます。必要な勉強時間は約100時間、勉強期間の目安は1〜3ヶ月程度です。独学でも十分に合格を狙える難易度となっています。
簿記3級を取得することで、家計簿感覚での帳簿管理ができるようになり、小規模事業の経理業務に携わることができます。また、財務諸表の基本的な読み方も身につくため、ビジネスパーソンとして必要な会計知識の基礎を習得できます。
特に、簿記を初めて学ぶ方、経理・会計の基礎知識を身につけたい方、まずは簿記がどんなものかを知りたい方には最適の資格です。
簿記2級になると、試験内容が大きく変わります。商業簿記に加えて工業簿記が追加され、中規模企業の経理処理や複雑な仕訳処理、工業簿記における原価計算、そして財務諸表分析などが求められるようになります。合格率を見ると、3級の40-50%から2級の20%前後へと半分以下に激減します。これは単純に問題が難しくなるだけでなく、学習すべき範囲が大幅に拡大することが主な原因です。
勉強時間は3級の約100時間から2級は約250-350時間と、2.5倍から3.5倍に増加します。これは単純に覚える量が増えるだけでなく、理解の深度が求められるためです。3級では「覚える」ことが中心でしたが、2級では「理解して応用する」能力が必要になります。
2級から1級への難易度の変化は、3級から2級以上に劇的です。合格率は20%前後から10%前後へとさらに半減し、必要な勉強時間は350時間から1,000時間以上と約3倍に跳ね上がります。これは他の難関資格と比較しても相当な水準で、公認会計士や税理士試験の登竜門と呼ばれるのも納得できる難易度です。
1級では4つの科目(商業簿記・会計学・工業簿記・原価計算)すべてで足切り点(各科目40点満点中10点)をクリアし、なおかつ総合で70点以上を取る必要があります。つまり、1つでも苦手科目があると合格は困難になります。
日商簿記は3級から履歴書に記載でき、「基礎知識がある証明」として評価されることもありますが、簿記2級となると、仕訳や帳簿記入だけでなく、財務諸表の読み取りや分析もできるため、実務レベルのスキルがあると判断されるのは簿記2級からとなります。多くの求人で「簿記2級以上歓迎」「応募資格:簿記2級取得者」とされていることからみても、就職や転職で役に立つのは簿記2級からです。
日商簿記を勉強することで、売上・仕入・人件費・利益など、会社のお金の動きを記録・整理・分析する力が身につきます。また、「費用対効果」「収益性」「損益分岐点」など、経営判断の基本概念を理解できるようになることから、企業の「お金の流れ」を実務レベルで学ぶことができるといえます。
上記でも述べた通り、簿記の知識は、あらゆる企業で必須のお金の管理スキルであることから、「仕訳ができる」「決算書が読める」など、実務に近いスキルがあることを企業にアピールできます。つまり、単なる「資格保有」ではなく、実務で即戦力となる“数字の理解力”が証明される資格であると言えます。特に2級以上は、実務レベルでの即戦力として評価され、就職・転職活動で他の応募者と差をつけられる大きな強みになります。
経理の仕事は、日々の仕訳・帳簿入力・決算書の作成など、簿記で学ぶ内容とほぼ一致しています。特に日商簿記2級では、商業簿記と工業簿記の両方を学び、企業の財務活動を幅広く理解できます。つまり、簿記資格があることで、経理の基礎知識があると客観的に示せるため、たとえ未経験であっても「育成前提」で採用されやすくなるのです。特に日商簿記2級以上は、実務に直結するスキルが学べるため、転職・キャリアチェンジに強く、安定した専門職への道をひらく第一歩になります。
簿記の上位資格である日商簿記1級は、税理士試験の受験資格の1つです(一部科目のみ)。税理士試験や公認会計士試験の出題範囲には、「簿記論」「財務会計論」などがあり、簿記の知識がそのまま通用します。つまり簿記資格で土台を固めておけば、上位資格の学習もスムーズに進めやすくなり、よりキャリアアップを目指せるといえます。
「簿記は何級から受けるべき?」という疑問には、初心者なら3級から、就職・転職を見据えるなら2級以上がベストな選択であるとお答えできるでしょう。段階的にステップアップすることで、着実に実務スキルとキャリアの可能性を広げていきましょう。