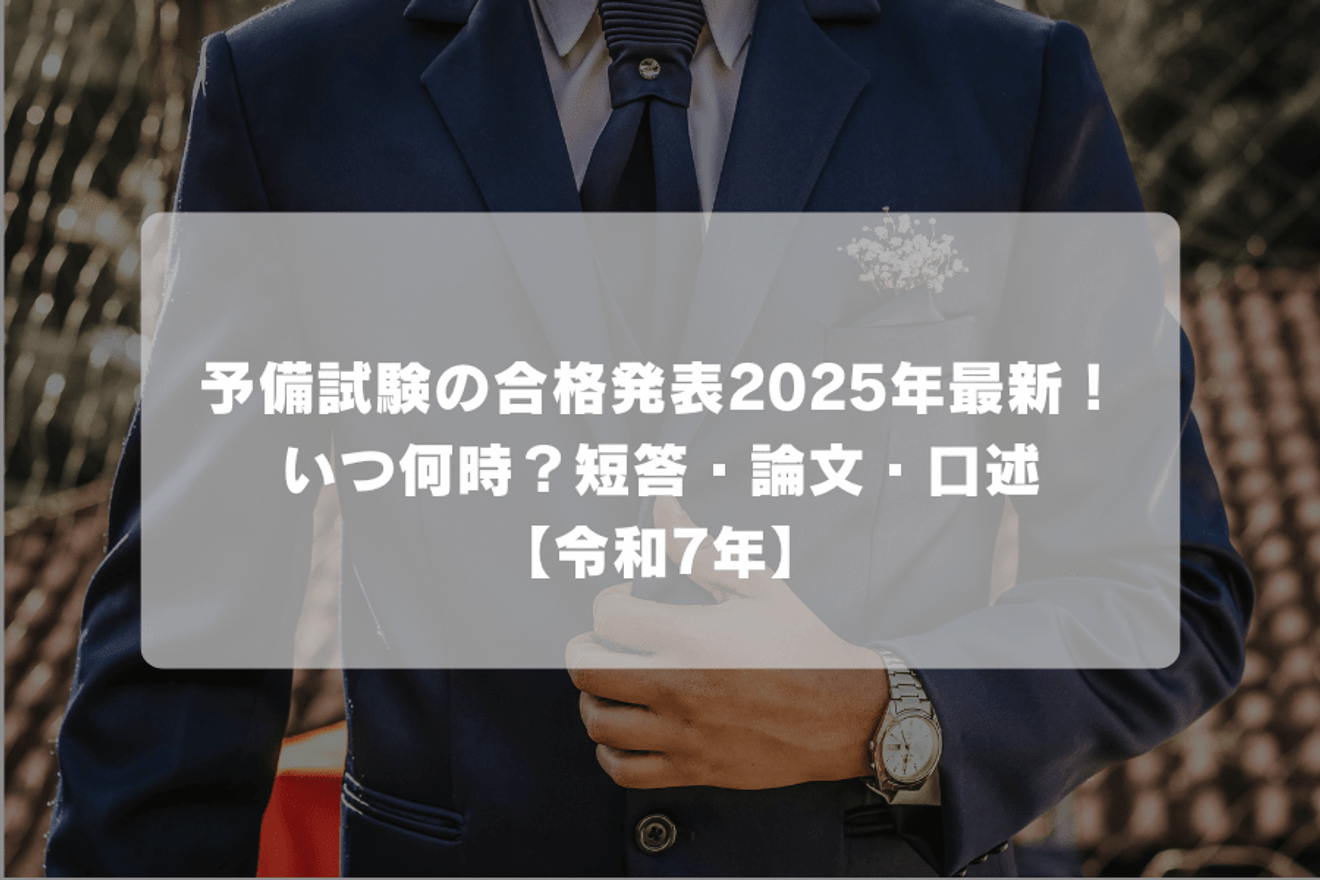
2025年(令和7年)の予備試験の合格発表日は、短答式試験が8月7日(木)、論文式試験が12月18日(木)、口述試験(最終合格発表)が2026年2月5日(木)です。
この記事では、法務省の発表に基づき、短答・論文・口述の各試験の合格発表日時や確認方法を詳しく解説します。合格後のキャリアプランや、万が一の場合の次のステップについても触れています。
2025年(令和7年)の予備試験の合格発表日は、短答式試験が8月7日(木)、論文式試験が12月18日(木)、口述試験(最終合格発表)が2026年2月5日(木)です。
以下では
の発表方法や時間など、それぞれ詳しく見ていきます。
2025年(令和7年)の予備試験短答式試験の合格発表日は、8月7日(木)午後5時頃です。発表方法は以下の2通り。
なお、通知に関しては不合格者は成績通知のみ、合格者は加えて論文式試験の受験票が届きます。通知は令和7年8月下旬に行われます。各科目の点数及び合計点数と順位が通知されます。
また、現地での掲示板などによる合格発表はされていないようです。
2025年(令和7年)の予備試験論文式試験の合格発表日は、2025年12月18日(木)午後4時頃です。発表方法は以下の2通り。
なお、通知に関しては不合格者は成績通知のみ、合格者は加えて口述式試験の受験票が届きます。通知は令和7年12月下旬に行われます。各科目のA~Fの6段階による評価及び合計点数と順位が通知されます。
また、現地での掲示板などによる合格発表はされていないようです。
2025年(令和7年)の予備試験口述式試験の合格発表日は、2026年2月5日(木)午後4時頃です。発表方法は以下の2通り。
なお、通知に関しては不合格者は成績通知のみ、合格者は加えて合格証書が届きます。通知は令和8年2月下旬に行われます。総合得点と順位が通知されます。また、現地での掲示板などによる合格発表はされていないようです。
※参考:予備試験試験日程2025年最新!出願日や申込日なども!【令和7年】
予備試験の合格発表に関して、受験生が気になる点をQ&A形式で解説します。
合格発表の日時を改めてまとめると以下の通りです。
合格発表の確認方法は主に法務省ホームページでの確認となります。
合格発表時に合格点や合格率も公表されます。法務省ホームページでの合格発表と同時に、合格最低点や受験者数、合格者数、合格率などの統計情報も公表されます。
これにより、自身の成績だけでなく、試験全体の傾向を把握することが可能です。これらのデータは、次年度以降の受験生にとっても重要な指標となります。
短答式試験と論文式試験については、不合格者にも成績通知書が郵送されます。この通知書には科目ごとの得点などが記載されているため、自身の弱点を分析し、次回の学習計画を立てる上で非常に重要な資料となります。
ただし、口述試験で不合格となった(最終不合格の)場合、個別の通知はありません。
法務省大臣官房人事課は令和7年(2025年)8月7日、予備試験短答式試験の合格発表をしました。
受験者数に関して、出願者は15,764人、欠席者3,332人、受験者は12,432人(うち途中欠席101人)で受験率は78.9%でした。採点対象者は12,331人でした。
合格点は159点/270点満点、合格者数は2,744人、合格者の平均点は175.8点でした。
予備試験の最終合格はゴールではなく、司法試験に向けた新たなスタートです。合格後に取るべき行動について解説します。
予備試験合格で得られるのは「司法試験の受験資格」です。最終目標である司法試験合格に向けて、すぐに対策を始めることが最も重要です。
予備試験の学習で得た知識を土台に、司法試験特有の出題形式や長文問題に対応できる応用力を養う必要があります。多くの合格者が、気を緩めることなく翌年の司法試験合格を目指して学習を継続します。
司法試験の勉強と並行して、法律事務所でのアルバイト(司法修習生予定者向け)や、企業の法務部などで実務経験を積むことも非常に有益です。
実務に触れることで、法律知識がどのように社会で活かされているかを体感でき、学習へのモチベーション向上に繋がります。また、合格後のキャリアを考える上でも貴重な経験となり、就職活動を有利に進めることができます。
なお、実務経験を積むための求人探しやキャリア相談には、士業・法務に強い転職エージェントヒュープロの活用がおすすめです。
ヒュープロなら、法律事務所や企業法務部の求人情報が豊富で、あなたの希望やスケジュールに合わせた案件紹介が受けられます。司法試験の勉強と並行しながら効率よく実務経験を積み、合格後のキャリアをより有利にスタートさせましょう。
▼登録は以下のバナーから可能
残念ながら不合格だったとしても、これまでの学習が無駄になることは決してありません。次に向けて冷静に計画を立てましょう。
独学や現在の学習方法に限界を感じている場合、予備校の講座を利用して弱点を克服するのも有効な手段です。プロの講師による的確な分析や、質の高い教材を活用することで、効率的に実力を伸ばすことが可能です。
特に論文式試験で点数が伸び悩んでいる場合は、答案添削指導のプランのある予備校カリキュラムも検討できるでしょう。
予備試験ルートでの合格が難しいと感じた場合、法科大学院(ロースクール)へ進学し、司法試験の受験資格を得るルートも有力な選択肢です。
法科大学院では体系的な法律教育を受けられ、同じ目標を持つ仲間と学ぶことで新たな刺激も得られます。近年は社会人向けのコースや未修者コースも充実しており、多様な経歴の人が学んでいます。
既に社会人の人や、今回の不合格で大学卒業・大学院修了のタイミングが来る人の多くは、来年再度予備試験合格を目指すとしても、現実問題として生活費を稼ぐためにも働く必要があるでしょう。
その際には、働きながら法律実務を学ぶことのできる、弁護士事務所や企業の法務部などは有力な候補。
実は弁護士事務所や企業の法務部は、必ずしも弁護士資格を有していなくとも求人が出ている場合があります。
但し、現実問題として無資格の人がいきなり弁護士事務所や企業の法務部などへの転職・就職をするのは難しいでしょう。
そこで、士業・法務に特化した転職支援サービスヒュープロの活用がおすすめです。ヒュープロでは、未資格者でも働きながら法律実務を学べる企業法務の求人情報を取り扱っています。
経験豊富なコンサルタントが、あなたの学習状況や希望条件に合わせて最適な案件を紹介してくれるため、司法試験予備試験の勉強と両立しながら実務経験を積むことが可能です。これにより、合格後のキャリアを有利にスタートさせることもできます。
▼登録は以下のバナーから可能
予備試験の結果がどうであれ、難関試験に挑戦し、膨大な法律知識を習得したあなたの経験は、社会で高く評価されるべき貴重な財産です。その価値を活かさない手はありません。合格した方は司法試験を見据えた実務経験を、そして今回は結果に繋がらなかった方もその知識を武器に、新たなキャリアを切り拓くことができます。
特に企業の法務部や法律事務所は、あなたの専門性を存分に発揮できるフィールドです。しかし、「学習経験を職務経歴書でどうアピールすればいいか」「実務未経験でも挑戦できる求人はあるのか」といった不安を感じる方も多いでしょう。
そんな時は、士業・管理部門に特化した転職エージェントヒュープロにぜひご相談ください。
「ヒュープロ」は法務分野の転職市場を熟知しており、あなたの予備試験での学習経験を正しく評価してくれる企業や事務所とのマッチングを得意としています。非公開求人も含め、あなたの知識を活かせる多様なキャリアの選択肢を提案できます。
これまでの努力を次のステージに繋げるために、まずは一歩踏み出してみませんか。専門のキャリアアドバイザーが、あなたの新たな挑戦を全力でサポートします。
▼登録は以下のバナーから可能