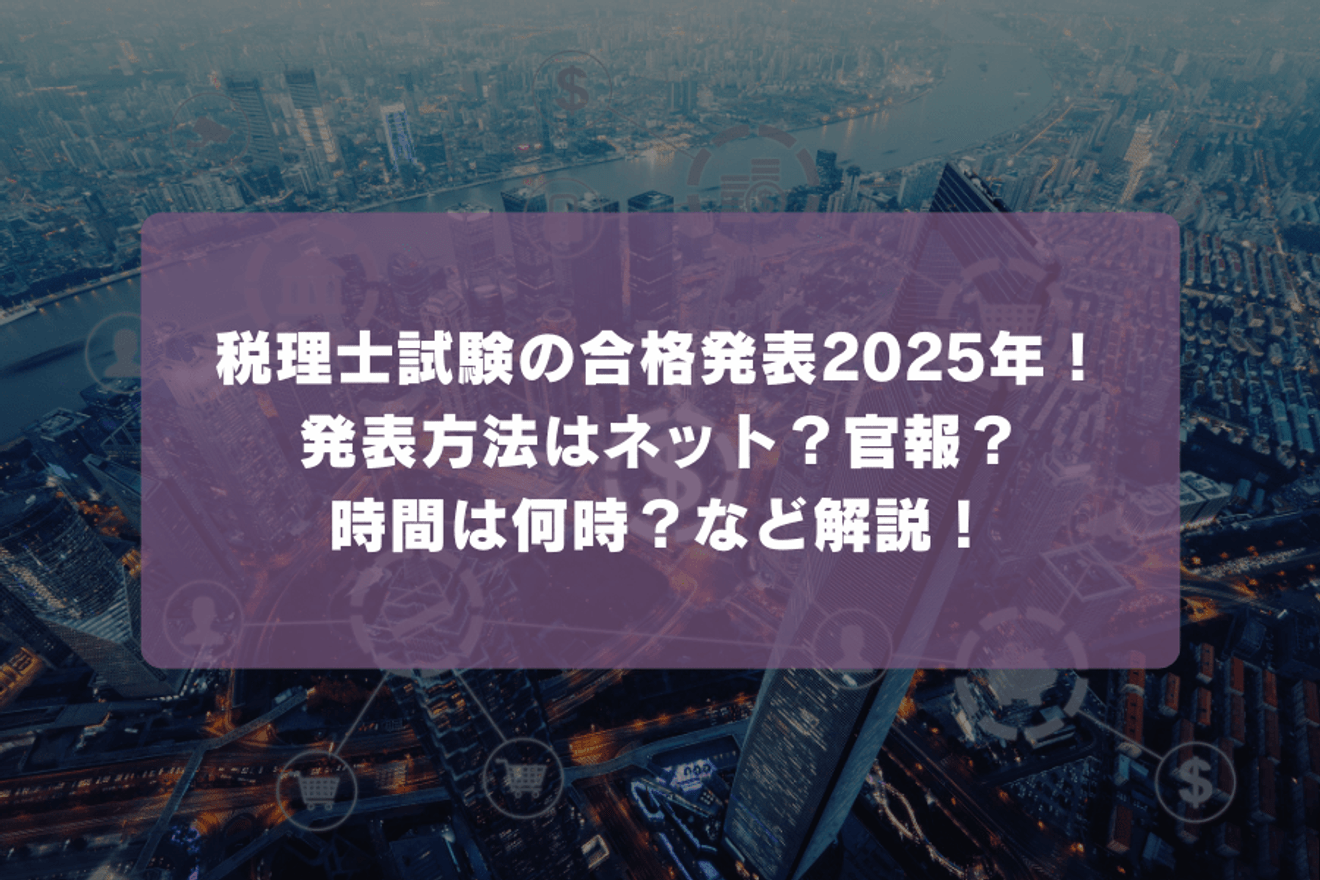
第75回税理士試験の合格発表日は令和7年11月28日(金)の予定です。発表の時間や発表法について気になりますよね。
この記事では税理士試験の合格発表日や発表時間や発表方法、合格・不合格の場合にすべきことなどを解説します。

2025年度(令和7年度)税理士試験の結果についてみていきます。主な論点は以下の通り。
令和7年度(第75回)税理士試験の受験者数は今回36,320人で、前回(令和6年度)の34,757人から1,563人増となりました。
一昨年は税理士試験の受験資格が緩和されたことにより、受験者数が5年ぶりに3万人を超えましたが、今年もその好影響が継続したのか昨年以上の受験者数となりました。
| 科目 | 受験者数 | 合格者数 | 7年度合格率 | (参考) 6年度合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 簿記論 | (104.3) 18,466 |
(66.9) 2,058 |
11.1 | 17.4 |
| 財務諸表論 | (114.4) 15,629 |
(453.1) 4,980 |
31.9 | 8.0 |
| 所得税法 | (93.7) 1,120 |
(97.3) 146 |
13.0 | 12.6 |
| 法人税法 | (100.6) 3,606 |
(83.0) 488 |
13.5 | 16.4 |
| 相続税法 | (95.9) 2,413 |
(70.7) 333 |
13.8 | 18.7 |
| 消費税法 | (98.0) 7,064 |
(96.2) 712 |
10.1 | 10.3 |
| 酒税法 | (111.7) 590 |
(112.5) 72 |
12.2 | 12.1 |
| 国税徴収法 | (100.1) 1,671 |
(106.5) 231 |
13.8 | 13.0 |
| 住民税 | (95.2) 439 |
(92.9) 78 |
17.8 | 18.2 |
| 事業税 | (124.5) 310 |
(111.8) 38 |
12.3 | 13.7 |
| 固定資産税 | (103.9) 928 |
(89.4) 144 |
15.5 | 18.0 |
| 合 計 (延人員) |
(105.2) 52,236 |
(138.8) 9,280 |
17.8 | 13.5 |
第75回税理士試験では合格者数が527人であり、昨年より51人減でした。また一部科目合格者は7,320人であり、昨年の5,184人から2,136人の大幅減でした。合格率については21.6%で、こちらも前回の16.6%より5.0ポイントの大きな上昇とました。
なお学歴別および年齢別の受験者数・合格者数・合格率については以下の通りです。
| 区分 / 学歴等区分 | 受験者数 (A) |
合格者数等 | 合格率 (B/A) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5科目 到達者数 |
一部科目 合格者数 |
合格者数合計 (B) |
||||
| 学歴別 | 大 学 卒 | 25,893 | 420 | 4,957 | 5,377 | 20.8 |
| 大学在学中 | 2,811 | 9 | 887 | 896 | 31.9 | |
| 短大・旧専卒 | 695 | 2 | 81 | 83 | 11.9 | |
| 専門学校卒 | 3,049 | 53 | 395 | 448 | 14.7 | |
| 高校・旧中卒 | 3,179 | 32 | 754 | 786 | 24.7 | |
| そ の 他 | 693 | 11 | 246 | 257 | 37.1 | |
| 年齢別 | 41歳以上 | 11,632 | 180 | 1,159 | 1,339 | 11.5 |
| 36〜40歳 | 4,674 | 96 | 904 | 1,000 | 21.4 | |
| 31〜35歳 | 5,100 | 82 | 1,184 | 1,266 | 24.8 | |
| 26〜30歳 | 6,420 | 101 | 1,537 | 1,638 | 25.5 | |
| 21〜25歳 | 6,752 | 66 | 1,921 | 1,987 | 29.4 | |
| 20歳以下 | 1,742 | 2 | 615 | 617 | 35.4 | |
| 合 計 | 36,320 | 527 | 7,320 | 7,847 | 21.6 | |
学歴別合格率では大学在学中が最高となっています。
年齢別合格率では20歳以下が最高となっていますが、受験者が1,000人台であるなど、合格率算出する際の分母(受験者数)が少ないため「20歳以下のほうが合格しやすい」と単純に言うべきではないでしょう。
2025年の税理士試験の合格発表日は令和7年11月28日(金)です。
以下では
2025年税理士試験の合格発表は令和7年11月28日(金)午前10時です。
明確に公式HP等で記載されているわけではありませんが、例年の傾向として基本的には当日の午前10時に公表されています。
2025年の税理士試験の合格者の発表は、以下のように行います。
なお、官報はネットでの閲覧も可能です。
また、申し込んだ科目を全て欠席した人への試験結果の通知はありません。
税理士試験の合格発表当日には、試験の合格点や合格率なども公表されます。
一部科目合格、一部科目不合格の場合、税理士試験等結果通知書が郵送されます。また、一部の科目に合格した人については、発表予定日に受験地・受験番号を国税庁ホームページに掲載されます。
受験した人で、合格科目のない人には、税理士試験結果通知書が郵送されます。
なお、申し込んだ科目を全て欠席した人への試験結果の通知はありません。
税理士試験に合格したらすべきことは主に以下の2点。
税理士試験に合格したらすべきことの一つに、実務経験を積むべく就職活動をすることが挙げられます。
税理士になるには試験合格に加えて「登録」が必要となります。この登録の要件として「2年以上の実務経験」が必要となります。
すなわち、試験には合格したが2年以上の実務経験がない人は、その時点では「税理士になる」ことはできません。
そのため、税理士になるには、2年以上の実務経験を積む必要があります。既に税理士事務所などで勤務している場合、引き続き勤務することで2年以上の実務経験を積むことで登録ができるようになります。
一方、現時点で実務経験が不足しておりかつ税理士事務所など実務経験を積むことのできる仕事をしていない場合、登録するには税理士事務所などへの転職活動が求められます。
その際に有効なのが、士業・管理部門に特化した転職エージェントヒュープロの活用です。ヒュープロでは一般的な求人媒体では見つけにくい税理士事務所や会計事務所の非公開求人も多く扱っており、合格者のキャリア形成に適した求人紹介を受けられます。
さらに、税理士としてのキャリアを見据えた相談も可能なため、効率的に実務経験を積める環境へと繋がりやすくなります。
まずは無料相談からでもヒュープロを活用してみるとよいでしょう。
税理士試験合格後、「登録」手続きを経ることで税理士になります(税理士を名乗って業務をすることができるようになります)。
登録にあたっては、2年以上の実務経験や必要書類の提出、さらに日本税理士会連合会による審査が求められます。審査を通過すると正式に税理士名簿へ登録され、晴れて税理士として独立開業や勤務税理士としての活動が可能になります。
仮に実務経験が不足している場合、上の見出しでも述べているように、まずはヒュープロなどを活用して税理士事務所などへ転職するとよいでしょう。
税理士試験に不合格になったらすべきことは主に以下の3点。
税理士試験に不合格になった場合、次の受験に向けて予備校の利用を検討するとよいでしょう。
税理士試験は科目数が多く、独学だけでの合格は非常に困難といわれています。(特に低い点数で)不合格になった場合、勉強方法そのものを見直す必要があるでしょう。
大手予備校では、合格者データに基づいたカリキュラムや効率的な学習スケジュールが整備されており、最新の出題傾向に対応した指導を受けることができます。特に仕事と両立しながら学習する人にとっては、カリキュラムや講師のサポートが大きな助けとなります。
税理士試験では、大学院で特定の分野を研究することで、一部の科目を免除できる制度があります。不合格になった場合でも、大学院進学を選ぶことで学問的な知識を深めつつ、受験科目を減らすことが可能です。
また、この大学院には平日夜間や土日などを中心に開講しているものも存在するため、忙しい社会人でも通学可能な場合があります。
中には税理士の科目免除とともにMBA(経営学修士)を取得できる大学院もあります。自分の状況に合わせて大学院進学も検討するとよいでしょう。
上述の通り税理士になるには試験合格に加えて2年以上の実務経験も必要となります。そのため、まだ実務経験を有していない社会人の場合、「税理士事務所などで実務経験を積みながら税理士試験合格を目指す」という手があります。
実務に触れることで学習内容が実際の業務にどのように活かされているのかを理解でき、試験勉強へのモチベーション維持にもつながります。また、補助業務を通じて身につけたスキルは、合格後に税理士として独立・開業を目指す際にも大きな強みとなるでしょう。
未経験歓迎の求人も多く存在するため、積極的に応募してキャリアと学習を両立させることがおすすめです。
なお、こうした未経験可の税理士事務所や企業法務部への転職活動を効率的に進めるには、士業・管理部門に特化した転職エージェントヒュープロの活用がおすすめです。ヒュープロでは、一般には公開されない非公開求人も多数取り扱っており、あなたの希望や状況に合った職場を専門コンサルタントが丁寧に紹介してくれます。
学習と実務経験を両立させ、次回試験合格や将来の税理士キャリア形成に向けた最適な環境を手に入れられるでしょう。
税理士試験に合格した後や、まだ合格していない段階でも、税理士資格や税務知識を活かせる職場での実務経験は、キャリア形成において非常に重要です。しかし、未経験可の税理士事務所などの求人は限られており、効率よく探すのは簡単ではありません。
そこでおすすめなのが、士業・管理部門に特化した転職エージェントヒュープロです。ヒュープロでは、一般には出回らない非公開求人も多く取り扱っており、あなたの希望条件や経験、学習状況に応じて最適な職場を専門のコンサルタントが紹介してくれます。
また、税理士資格取得後のキャリアプランに関する相談も可能で、効率的に実務経験を積みつつ、次回試験合格や独立開業に向けた準備を進められる環境が整っています。
税理士資格を活かした転職を成功させたい方は、まずは無料相談からヒュープロを活用してみることをおすすめします。
