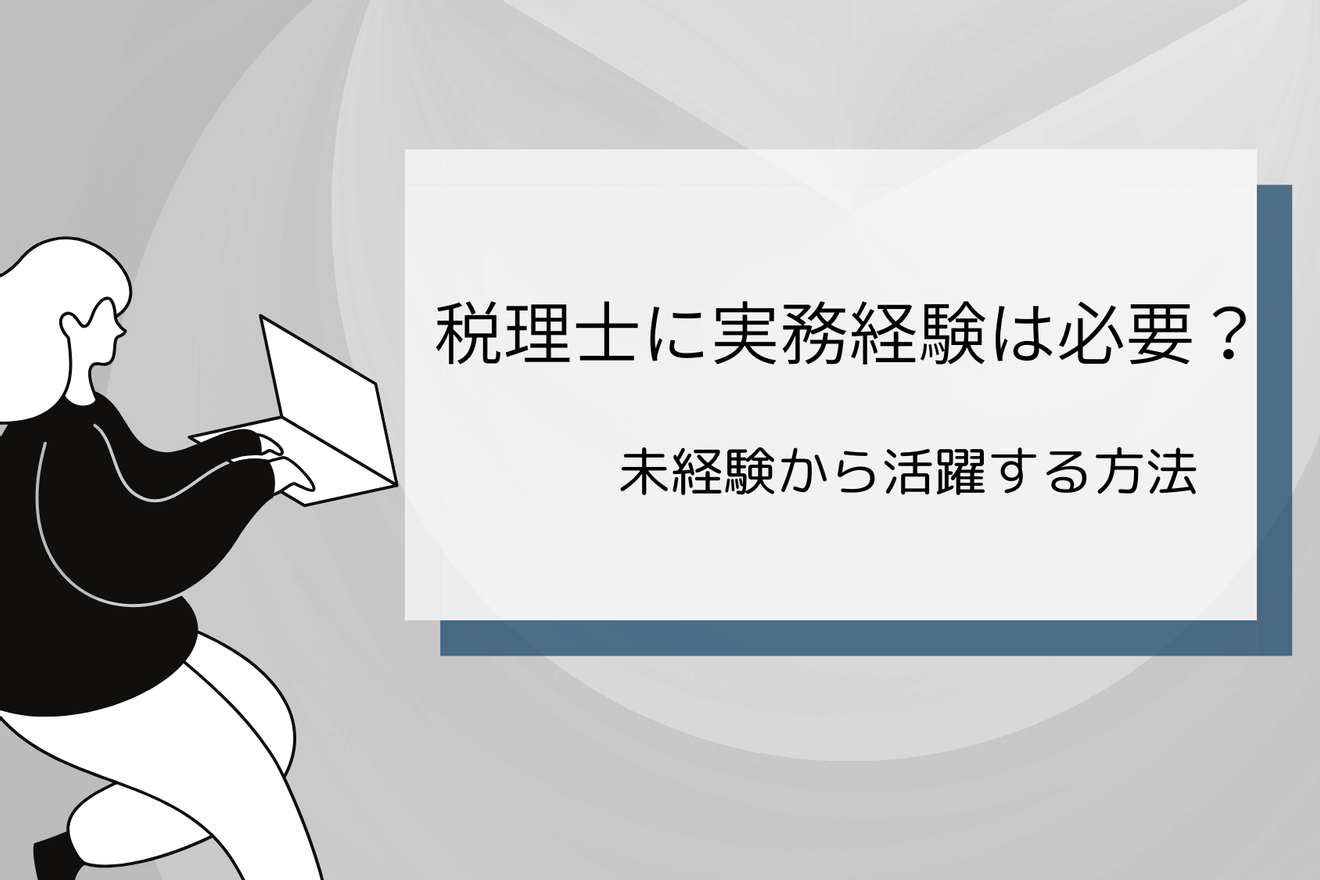
税理士として登録するためには、税理士試験の合否に関わらず、2年間の実務経験が必要です。税理士試験を突破しただけでは税理士として登録することはできません。それでは、税理士試験突破後、実務経験がない方はどのようにして実務経験を積んでいけば良いでしょうか?この記事では、実務経験なしから税理士として活躍するために大切なことについて説明をしていきます。
結論から申し上げますと、実務経験がないと税理士にはなれません。なぜなら税理士になるには、下記が必要であると税理士法第3条に定められているからです。
国税局での従事経験がある方については、実務経験免除での税理士登録が可能ですが、それ以外の場合は実務経験が必須なのです。
ではここからは、税理士登録をするために必要な2つの手順について、それぞれ詳しく見ていきましょう。なお、税理士資格の取得と実務経験を積む順序はどちらでも問題ありません。
まずは税理士資格を取得する方法です。税理士資格を取得するには、税理士試験の合格もしくは試験免除の条件をクリアする必要があります。
税理士として登録をするためにはまず、当然ながら「税理士資格」を取得する必要があります。税理士試験は毎年8月に実施されており、会計学に関する科目2科目と、税法に関する科目3科目の合計5科目に合格することで「税理士資格」の認定を受けることができます。
税理士試験は国家資格の中でも難易度が高く、2023年度の全科目合格者は8.4%でした。
先にご説明したような税理士試験を受けなくても、税理士としての登録ができることがあります。
①学位取得による科目免除
| 該当者 | 免除される科目 |
| 平成14年3月までに大学院に進学した者 | 商学の学位(修士または博士)を持つものは会計系の科目(簿記論・財務諸表論) 法学・経済学のうち財政学の学位(修士または博士)を持つ者は税法系の科目(選択必修及び選択科目) |
| 平成14年以降に大学院に進学した者で、会計系あるいは税法系の修士論文を執筆し学位を得た上で、それぞれの科目に1科目以上合格した者 | 会計学に属する科目等の学位を持つ者は残る会計系の科目
税法に属する科目等の学位を持つ者は残る税法系の科目 |
| 平成14年以降に大学院に進学した者で、会計系あるいは税法系の博士論文を執筆し学位を得た者 | 会計学に属する科目等の学位を持つ者は会計系の科目
税法に属する科目等の学位を持つ者は税法系の科目 |
②国税従事による科目免除
| 該当者 | 免除される科目 |
| 10年又は15年以上税務署に勤務した国税従事者 | 税法系の科目 |
| 23年又は28年以上税務署に勤務し、指定研修を修了した国税従事者 | 会計系の科目 |
③弁護士資格・公認会計士資格を有している場合
弁護士資格、会計士資格を有している場合、無条件で税理士として登録することができます。しかし、平成29年以降4月1日以降の公認会計士試験の合格者は、税法に関する研修を修了した公認会計士についてのみ、税理士資格を得ることができます。
税理士資格の取得と併せて、2年間の実務経験をすることで税理士に登録することができます。
通常は、税理士として登録するためには、誰でも税理士試験に合格したのち実務経験を積む必要があります。
それでは、まだ実務経験のない税理士試験合格者はどのように実務経験を積んでいけば良いでしょうか?この記事では、税理士として活躍するための実務経験の積み方について丁寧に解説していきます。
税理士法においては、実務経験とは「租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるもの」と規定されています。したがって、この規定に該当する実務経験でなければ、将来税理士として活躍することはできません。
それでは、より具体的にどのようなことを実務経験と呼ぶのでしょうか?規定によれば、実務経験に該当するか否かは、登録申請書及び在職証明書等が提出された後、税理士会の調査(面接等)の段階で個別に判断することになっています。
実務経験に該当する事務の内容としては、租税に関する事務所又は会計に関する事務で政令で定めるものと規定されています。「租税に関する事務」とは、税務官公署における事務のほか、その他の官公署及び会社等における税務に関する事務をいいます。
一方、会計に関する事務とは、貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて計理する会計に関する事務(特別な判断を要しない機械的事務を除く)と定められており(税理士法施行令第1条の3)、簿記の原則にしたがって、会計帳簿等を記録し、その会計記録に基づいて決算を行い、財務諸表等を作成する過程において簿記会計に関する知識を必要とする事務と規定されています。
財務諸表等を作成する過程において簿記会計に関する知識を必要とする事務とは、より具体的に言えば以下のような事務のことを言います。
と定義されています。
ここで、特別な判断を要しない機械的事務とは、簿記会計に関する知識がなくてもできる単純な作業のことをいい、電子計算機を使用して行う単純な入力作業のことを言います。これらの作業は実務経験には該当しないので注意が必要です。
会計事務所などの経理実務に携わっていても、簿記会計の知識がなくてもできるような単純な事務や、電卓を使用して行う単純な入出力の事務では、実務経験にはカウントされません。また、原則として対価の伴わない従事は実務として認められていません。
実務の期間は、試験合格又は試験免除決定の前でも後でもかまいません。
①実務経験期間が通算して2年以上とは、正規の雇用関係があり、原則として通常の勤務時間内(時間外勤務は含まない)における税務又は会計に関する事務に従事していた期間を暦にしたがって計算し、2年以上になる場合です。
②従事した事務に実務経験に該当する事務以外のものが含まれている場合には、実務経験に該当する事務に従事した時間を抽出して積み上げ計算を行います。
③一箇所での勤務で実務経験が充足しない場合には、複数箇所での勤務期間を合算して実務経験とすることが可能です。
勤務時間の積上げには、以下のような制限が設けられています。
2年以上の実務経験があることを証明するには、税理士名簿に登録申請する際に在職証明書を提出します。在職証明書は、日本税理士連合会により定められたをフォーマットを使用し、実務経験を積んだ事業所の代表者・又は上司の捺印が必要です。またトータルでは2年になるけれど、1年ずつ別々の事業所で経験を積んだ方はそれぞれの在職証明書を準備し、提出します。又、在職証明書に押印した印鑑を証明するために、印鑑登録証明書の提出も必要です。
一般事業者の場合は「職務概要説明書」も必要
「職務概要説明書」に関しては、特別なフォーマットがないため、以下の必要事項を漏れなく記入する必要があります。
こちらは日本税理士連合会により定められた様式ではないので、ご自身で漏れがないよう記入してください!
税理士資格や実務経験が無いと、会計業界への転職は難しいと思っている方も多いのではないでしょうか?ここではいくつかのパターンに分けて紹介します。
資格と経験のどちらもない場合は、そのいずれかを持っている方も多くいる中での転職活動になるので、それなりの対策をしておく必要があります。実務未経験の場合は、20代を中心とした若手に対するポテンシャル採用を行っている事務所があるため、そちらを選んで応募するのがオススメです。また、多くの会計業界の求人が日商簿記2級を必須もしくは歓迎資格としています。ですので税理士資格はハードルが高いという方も、日商簿記2級は取得しておくとよいでしょう。
〈関連記事〉
税理士資格を持っていて、税理士登録のために会計業界に転職したいという方は多くいらっしゃいますが。このような方は業界の転職市場での価値が非常に高いです。しかし、資格と同じかそれ以上に実務経験の有無が転職市場価値を左右する業界なので、年齢によっては転職活動に苦労するケースもあります。
税理士資格を持っていなくても、実務経験がある場合はかなり市場価値が高いです。採用する側は即戦力として入社してもらうことができるので、場合によっては有資格者よりも重宝されることもあります。
〈関連記事〉
会計事務所では、実務経験のない科目合格者や税理士受験生も税理士補助として多く活躍しています。
主な業務は、クライアントの記帳代行がメインですが、税務コンサルタントとしてのアドバイザリー業務に携わることができる事務所もあります。
実務未経験の場合でも、税理士補助として科目合格者や受験生を求めている事務所はたくさんありますので、転職も難なくできるでしょう。
また、事務所によっては資格取得応援を行っており、フレックスタイム制の導入や、試験前休暇等を設けてくれるところもあるので、要チェックです!
では、実務経験がない方が会計事務所で働いた場合の給与水準について解説します。
結論から申し上げますと、未経験で会計事務所に入る場合の年収は約300万円程度~だと思っていただければよいでしょう。
先ほども述べたように、実務経験がない場合でも会計事務所では税理士補助として雇ってもらえることが多々あります。
また、特に科目合格者であれば科目合格手当というものを受けられることがあるので、もう少し上げることもできるでしょう。
〈関連記事〉
未経験から会計事務所に就職するためには税理士試験を合格しているかどうかにかかわらず、重視すべきポイントがいくつかあります。
まずはなぜ税理士業界で働きたいと考えているのか、自分自身でも理解しておく必要があります。人それぞれのきっかけや志があって応募するので、志望動機に正解はありません。しかし履歴書への記載はもちろん面接時にも聞かれることが多いポイントなので、なんとなくで作成するのではなく、「なぜそう思ったか?」を自問し続けることで明確な志望動機を見つけましょう。また、それを面接時にもアウトプットできるよう準備しておきましょう。
次になぜその事務所に応募したのかという理由も落とし込みましょう。同じポジションの募集は沢山ある中でなぜその企業を選んだのかは、書類選考でも面接でもほぼ必ず選考基準に入っています。志望動機の完成度が低かったり他の企業でも通用するような内容だと、志望度が低いもしくはもし入社してもすぐ辞めてしまうかもしれないという懸念に繋がってしまいますので注意が必要です。企業情報や求人を仔細に確認し、相手に熱意が伝わるような内容を作りましょう。
就職・転職活動にあたって、自分で応募する求人を探したり面接の日程調整をするのは骨が折れるものです。そこで活用すべきなのが人材エージェントです。希望の条件やご自身の経歴などを伝えることで効率的に求人を提供され、日程調整もエージェントが実施してくれます。内定を複数社もらった際に断りをいれてくれるなど、心理的負担のある対応もする必要がありません。そういったサービスを無料で受けられるエージェントが多いのも特徴です。
求人を見る
税理士事務所で未経験を歓迎している求人の一覧です。未経験に必要な一定期間の教育体制が整った企業の求人があります。
求人を見る
若手でこれから税理士を目指している方向けの求人の一覧です。所内で若手が活躍している事務所の求人も豊富もあります。
<関連記事の紹介>
2年間という時間をかけて、税理士事務所や会計事務所の先輩である従業員の働きぶりをみながら、クライアントとの距離の近づけ方を確認することができます。税理士登録上の規定を満たすために実務を経験するだけでは意味がありません。
将来、税理士として登録をしたときのことを考えながら、実務に取り組まなければなりません。実務経験を積むことによって、税理士事務所を開業後、スムーズに仕事をスタートすることができるようになるというわけです。
会計事務所や税理士事務所では、様々なバックグラウンドを持ち、年齢を重ねた人が働いています。そのような環境のなかで税理士として生きていくことは大変です。そのような環境のなかで、本当に自分が税理士として働くことに意義を感じることができるか、それを試す場としても実務経験期間は存在しています**<。
単に経験を積むためだけに税理士事務所や会計事務所に所属するのではなく、自ら目的意識を持って実務経験を積んでいくことが、将来税理士として活躍するための近道です。