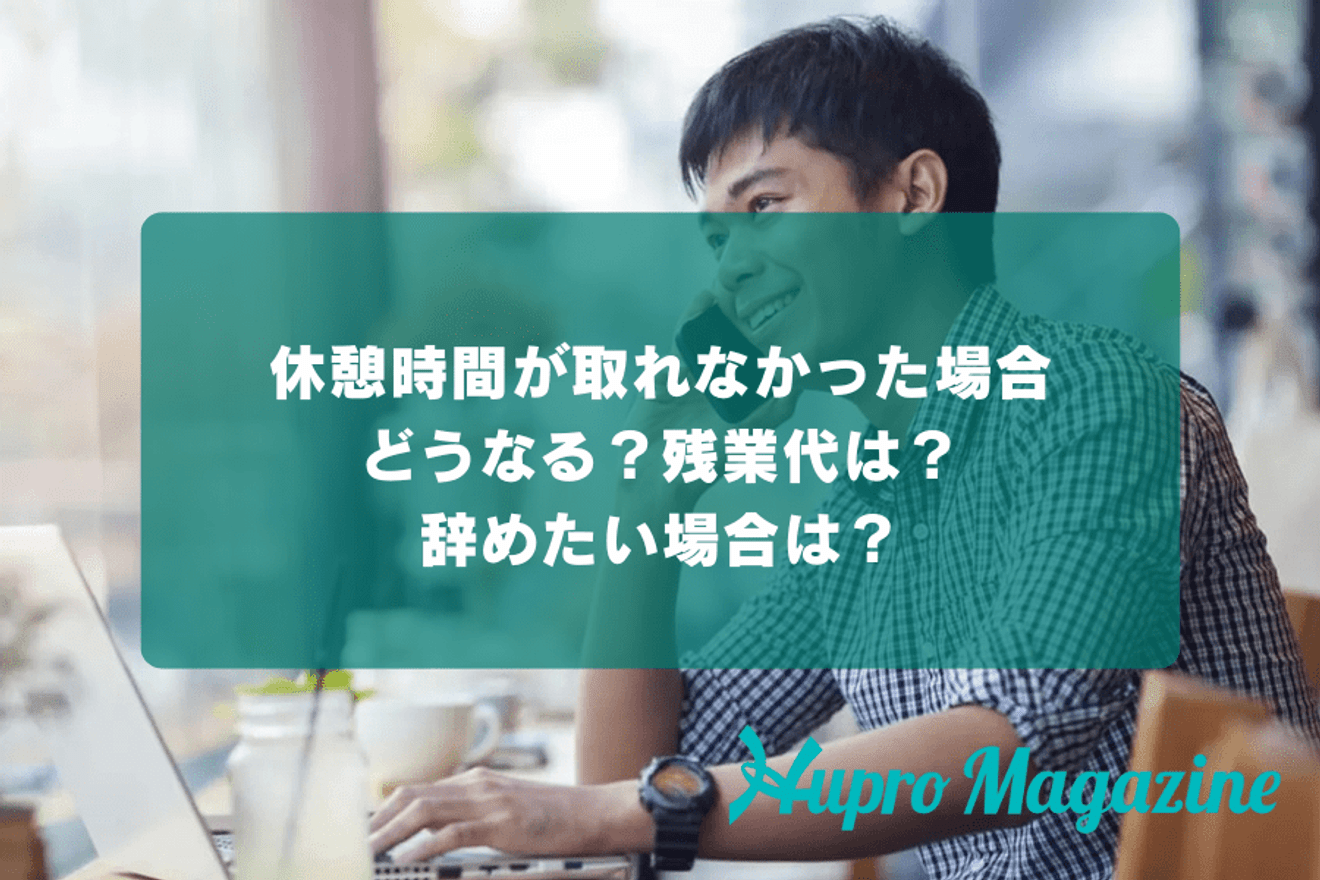
「仕事が忙しくてお昼休みが取れない」「休憩中も仕事したのに手当がない」など、休憩時間について疑問や不満を抱えている人は多いでしょう。
今回は、法定の休憩時間と休憩が取れないときの手当について解説するとともに、休憩時間が取れないため辞めたい人向けの解決策4つを紹介します。
休憩時間に関する違反・違法となるケースとしては主に以下の3点が挙げられます。
一方、休憩を取らせずとも違反・違法でないケースもあります。以下でそれぞれ詳しく見ていきます。
休憩時間に関する違反・違法となるケースとして、必要な休憩時間を付与できなかった場合が挙げられます。
必要な休憩時間は以下の通り。
なお、~時間を「超える」場合なので、例えば6時間ちょうどの勤務で休憩なしの場合、残業がなければ必ずしも違法にはなりません。
当然、どんな理由があろうとも、定められている休憩時間を従業員に付与しないのは違反です。
「休憩を取らせようとした時間に忙しくなってしまった」、「急にシフトに穴が開いて、休憩を回せなくなってしまった」など、やむを得ないように感じられる事情があるかもしれませんが、いかなる理由でも休憩を取得させなければなりません。
労働基準法第119条第1項によって、休憩の付与義務を違反した場合は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
休憩時間に関する違反・違法となるケースとして、休憩時間を買い上げ処理した場合が挙げられます。
①のケースと併せて、「この日は人が足りないから休憩時間分の賃金を上乗せして、休憩なしで働いてもらおう」と、休憩時間を買い上げ処理したケースについても違反となります。支払う賃金に関係なく、休憩を取得させなければなりません。
休憩時間に関する違反・違法となるケースとして、勤務時間外で休憩時間を取得させた場合も挙げられます。
始業前・終業後に休憩を取得させるのも違反です。逆に勤務時間内であれば、始業後30分での休憩も、10分×6回で取得することも可能です。
休憩時間を取得させなくても違反にならない唯一のケースとして、労働者が自ら休憩を返上する場合があります。
休憩時間分はやく帰りたいなど、本人からの申し出があった場合のみ違反とならないため、事業主から推奨することはできません。
前提として、法定通りの休憩を取らせるように指示する必要があり、あくまでも例外のケースであることを理解しておきましょう。
忙しくて休憩が取れなければ、他の時間帯で休憩時間を取る、もしくは分割して取得することが原則です。
しかし、実際には代わりの休憩が取れずに1日が終わることもあります。
この場合、休憩時間に行った労働に対しては賃金を受け取ることができます。ただし、会社が賃金を支払った場合も法定の休憩時間を付与していないので、労働基準法に違反していることに変わりありません。
以下では
という論点に関して、それぞれ詳しく見ていきます。
所定労働時間(労働契約や就業規則で定める労働時間)が7時間、休憩が1時間の正社員が休憩なしで仕事をした場合、正社員には1時間分の残業代を受け取る権利があります。
また、時給制のアルバイトが1時間の休憩時間中も仕事をしていれば、1時間分のバイト代を受けることができます。
就業形態にかかわらず休憩時間でも仕事をした分については、賃金が発生するのです。
休憩中の労働時間を含めて1日の労働時間が法定労働時間を超えた残業については、割増賃金がプラスされます。
法定労働時間は「1日8時間、1週40時間」で、これを超える労働時間に対する割増は25%です。定時で仕事が終わっても、休憩時間を削ったことによって実際の労働時間が法定労働時間を超えれば割増した残業代を受け取ることができます。
休憩時間は、労働者の仕事における負担や疲労を取るための時間です。
事業主は労働者に対してなんとなくで休憩を与えて良いわけではなく、労働基準法第34条にて以下のように取得させなければなりません。
言い換えると、休憩時間の決め方は下記の通りとなります。
労働契約を結ぶとき会社から労働条件について説明を受けますが、会社は労働条件として給与や労働時間のほか、休憩時間についても明示する義務を負っているのです。
フルタイムで勤務する場合、休憩時間が1時間ある会社や45分しかないところもあります。その中でも1時間にする会社が多いのは、45分休憩だと残業がある日は都度15分追加しなければならないからです。
もちろん、最低45分の休憩が義務付けられている労働時間で1時間の休憩を取得しても全く問題ありません。
お昼休みに電話や来客の対応があるので外出できない、などの不満を感じている人は多いのではないでしょうか。
実は、休憩の取り方についても労働基準法の定めがあり、「休憩時間の3原則」とよばれます。
それぞれの原則について解説します。
一斉付与の原則は、会社は従業員全員に同時に休憩時間を付与しなければならないというものです。パート・アルバイトや派遣労働者も同様です。
お昼休みを交代制にするためには、会社は労働者の過半数で組織する労働組合などと「対象となる労働者の範囲」と「休憩の与え方」について労使協定を結ばなければなりません。
労使協定なしでお昼休みを交代制にすれば労働基準法違反になります。
ただし、一斉に休暇を取ることが難しい「運輸交通業」「商業」「保健衛生業」「接客娯楽業」など特定業種については、一斉付与の原則が適用されません。
途中付与の原則は、休憩時間は労働時間の途中に付与しなければならないというものです。
例えば「8時間勤務した後、1時間の休憩して退社」「出社後すぐに1時間休憩してその後に連続8時間勤務」などは、「途中付与の原則」に違反しています。
自由利用の原則は、会社は休憩時間を従業員に自由に利用させなければならないというものです。
外食や買い物などのほか、会社の秩序や業務に支障がなければ政治活動や宗教活動をすることも認められています。(会社施設内で政治活動などを行う場合は、会社の許可が必要な場合があります)
休憩時間を自由に利用できない下記ケースは、本来、休憩時間ではなく労働時間とすべきものです。
休憩時間と労働時間のどちらと見なすのかという判断が裁判で争われることもありますが、厳密にいえば、実際に仕事をしている時間以外でも、会社の「指揮命令下」に置かれている時間は労働時間となります。
休憩時間が取れないため辞めたいと考える人には、以下の4つの対処法がおすすめです。
以下でそれぞれについて詳しく見ていきます。
休憩が取れない場合、まずは直属上司に申し出しましょう。事態を把握してなかった場合、問題点に気づいた上司が対応してくれるかもしれません。
上司が対応してくれなければ、総務や人事など会社の担当部署に相談する方法もあります。
会社に申し出しても、「もともとそういう会社だから」などと相手にされないケースがあるかもしれません。また、申し出をしたら社内での待遇や役職に影響を与えるのではないか、など不安な部分も多いでしょう。
そのような場合は、労働基準監督署に相談する方法があります。
労働基準監督署で有効なアドバイスが受けられたり、労働基準監督署が会社に直接、指導・勧告してくれるケースもあります。
また、裁判によって休憩中の労働に対する賃金を請求するのも選択肢の1つです。時間もお金もかかるので、どうしてもの場合の最終手段と考えるのがいいでしょう。
労働基準監督署に相談したり裁判する場合、休憩時間も仕事をしていたことを証明する証拠が重要です。「勤務時間や勤務内容をメモする」「パソコンの稼働時間やメールなどの記録を集める」「証言してくれる人を探す」などの方法が考えられます。
休憩時間の問題は労働基準法が関わる問題なので、法律の専門家である弁護士を頼るのもよいでしょう。
一般的には、弁護士事務所や法律事務所で相談することができます。
まずは無料で相談でき、対応を依頼する際に費用が発生するという形態が多いので、比較的ハードルが低いでしょう。
そもそも社内の労働環境がよくない、働き方が合わない、などと感じるのであれば、転職を検討するのも選択肢の一つです。
上記の手段のような所属する企業の違法状態の解決にはならないものの、ご自身のキャリアをどうするかというのも重要な視点です。
社会全体で、違法な休憩の取らせ方を日常的にしている企業はごく僅かです。ですので、他の企業に転職することで自身の労働環境の改善はしやすいといえます。
税理士事務所や会計事務所といった士業領域や、企業の経理職な度への転職を検討している場合は、士業・管理部門特化の転職エージェントである「ヒュープロ」にて無料でご支援させていただきますので、ぜひご活用ください!
▼登録は以下のバナーから可能