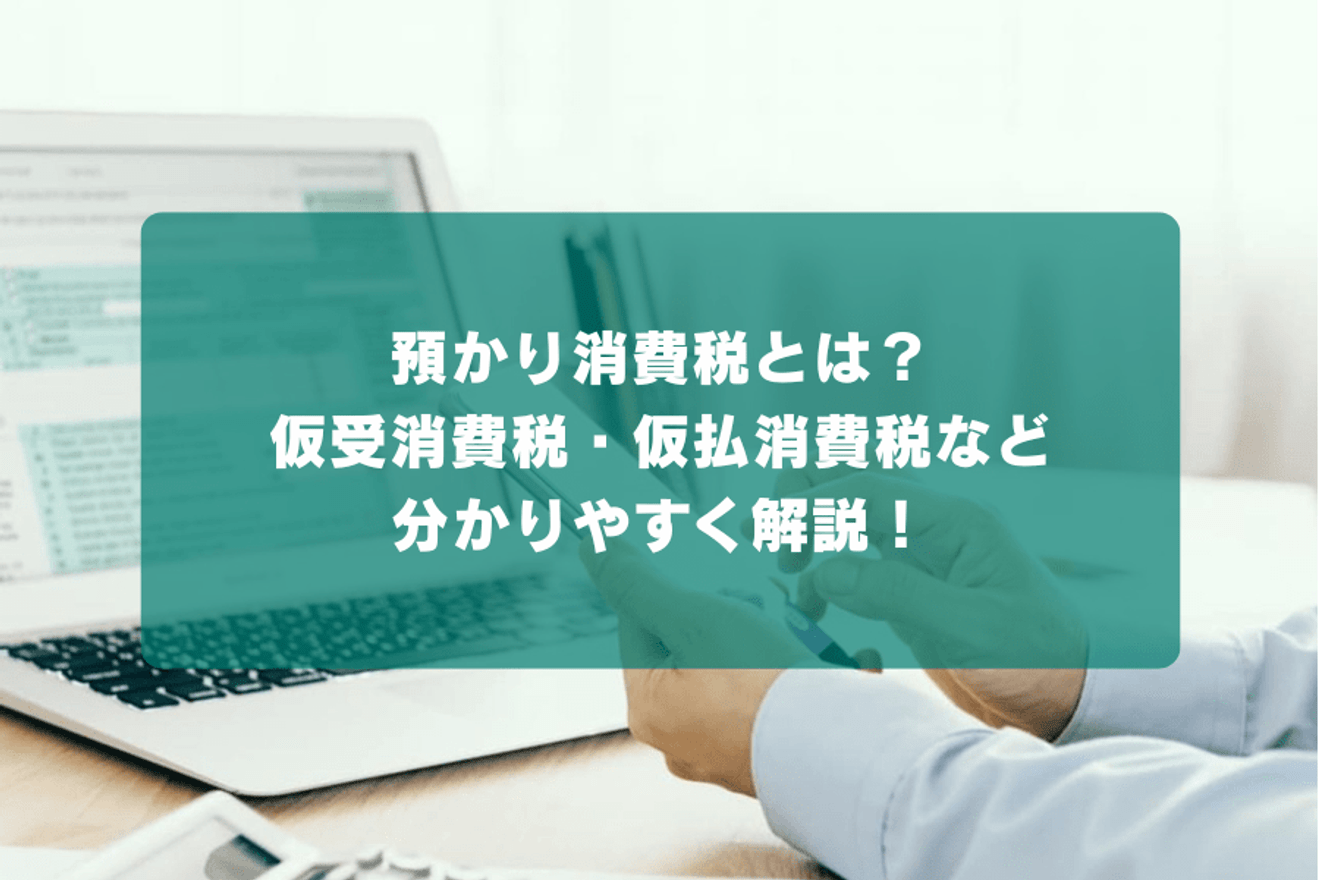
2019年10月より消費増税でついに消費税が10%になりました。経理や財務を担当している人でも、初心者は消費税の処理が意外と複雑で迷ってしまうことは多くないですか?
そんな不安を感じているのであれば、ここで一度しっかりと意味を理解し正確に処理できるようにしていきましょう。

預かり消費税とは仮受消費税のことで、一般的な税務用語では仮受消費税のほうが正しいです。
お客様に対して商品やサービスを販売した際に消費税額を計上するための勘定科目のことで、流動負債として扱われる項目となります。
決算を行う際には原料や経費などこちら側が支払った仮払消費税と相殺して未払い消費税として計上されるものです。
少し難しく説明しましたが、簡単に言うと、ものやサービスを売ったときにお客様から「預かる消費税」(仮受消費税)のことです。
自分たちが買ったときに支払う消費税は買った先に預かってもらうことから「支払う消費税」(仮払消費税)となり相殺することができるのです。
一般的な消費者的な考えでは、ものを買ったときに消費税として支払ったものは、支払った時点で納税していると考えられます。
では販売した側(つまり私達)は販売した際に受け取った消費税はそのまま納税しないといけないのでしょうか。わかりやすくするためさまざまな制度は一旦おいておき、シンプルに説明します。
つまり販売時に受け取った消費税から支払った消費税を引いて納付するということになるのです。
消費税は税金の負担者と納税者が異なる間接税となります。
さらに、消費税の計算が煩雑となりやすい小売店や卸売業、サービス業、製造業などでは簡易課税制度と呼ばれるものも存在しており、簡易課税制度では、仮払消費税を所蔵する区分によって一律に計算することを許されている制度です。
このように間接税ならではの難しい側面もありますが、基本的なしくみとしては前述の通り、預かっている消費税と支払うべき消費税の差分を払う(または還付される)という仕組みなのです。
消費税をもう少し詳しく見ていきましょう。
消費税はとても基本的な税金であるがゆえに、かなり広範囲に課税される税金となりますが、生産時点や流通時点で複数回税金がかからないように、税金が累積しない仕組みがとなっているのです。
これが上述の消費税の仕組みで一次請け二次請けと進むたびに相殺されて行く仕組みなのですが、そもそも消費税を含む税金が課税されるものと、課税されないものに分かれるのはご存知でしょうか。
非課税となるものの例としては、土地や住宅に関わるもの、証券・利子・保険料・外国為替など、切手や商品券、行政手数料、社会医療保険や介護保険等のサービス、出産や死亡関連の費用、障害者や学校等の一部の費用などが挙げられます。それ以外が基本的には課税取引となるのです。
消費税を計算しているとどうしても1円未満の端数が発生してしまうことがありますよね。その場合はどのように計算すべきなのでしょうか。
パターンは2つあります。1つ目としては、「税抜の金額から税込にした場合」と「税込の金額から税抜の金額にした場合」です。
この場合は企業の判断で、切り上げるか切り捨てるかを選択することができます。また、「支払った消費税の計算」と「消費税を納付する際の計算」の場合は切り捨てとなります。
2019年10月1日から消費税はついに10%に増税されました。前後で消費税が変わってしまい処理に困るということはないですか?その場合考えられることを説明しておきましょう。万が一困ったら参考にしてみてください。
例えば、課税商品のやり取りをしていて、こちらの受付日と先方の発注日がズレてしまい、お客様には10%で預り金として計上し、業者からは8%で支払いをしてしまったというケースです。
この場合、まずは実際の受け取った金額と支払った金額を先方に確認しましょう。誤りであり、業者も不一致が発生している可能性もあるからです。
もし業者が返金を求めてくる場合は返金すべきですし、不要ということであれば、仮受消費税として国庫に納めるべきとなります。
いかがだったでしょうか。一見複雑そうに見える消費税ですが、一度理解してしまえば難しくはないですよね。意味をしっかりと理解した上で、借り方、貸し方にしっかりと分けて正確に処理できるようになりましょう。