
公認会計士は独学で合格できる資格なのでしょうか?これから目指すことを考えている人の多くが最初に悩む点です。
そこで、今回は公認会計士の短答式試験及び論文式試験の特徴や難易度、独学での合格の可能性とその理由について解説します。
公認会計士の仕事に興味はあるけど、どうすればよいかよく分からない方は多いと思います。これから公認会計士試験に挑戦するかどうか検討している方、専門学校に通うべきか独学で挑戦するか迷っている方はぜひ参考にしてみてください。
結論から申し上げますと、独学で公認会計士試験に合格することは可能です。
公認会計士試験には受験資格が定められていないため、独学でチャレンジすることは当然可能です。
ただし、かなり困難な道であるということを理解しておく必要があります。
まずはじめに公認会計士試験の概要と難易度を把握してから、独学による合格の可能性を見ていきましょう。
公認会計士試験は、短答式試験と論文式試験の2種類に分かれており、どちらにも合格する必要があります。
短答式試験は、年に2回(5月と12月)に行われるマークシート方式の試験であり、科目は、財務会計論、管理会計論、監査論、企業法の4科目です。短答式試験に合格後2年間は試験免除となります。合格基準は、70%を基準として公認会計士・監査審査会が認めた得点比率で決まります。
論文式試験は、年に1回(8月)に行われる記述式の試験であり、科目は必須の会計学、監査論、企業法、租税法の4科目と、選択科目で経済学、経営学、民法、統計学の中から1科目選んで受験します。短答式試験同様に、合格した科目については2年間免除の対象となります。合格基準は、60%を基準に公認会計士・監査審査会が認めた得点比率で決まります。
〈参考記事〉
試験の難易度を表すものとして代表的なのは、合格率です。
直近3年間の最新の受験者情報から、欠席者をのぞいた合格率は、短答試験は15%、論文試験は40%程の合格率となっていることがわかります。つまり、最終的な合格率は10%前後であり、非常に難易度の高い試験であると言えます。
〈参考記事〉
合格者のなかでも独学で合格した人の割合は、10%を切ると言われています。つまり、受験者全体の中では1%未満ということとなり、独学での合格がいかに少ないかがわかります。
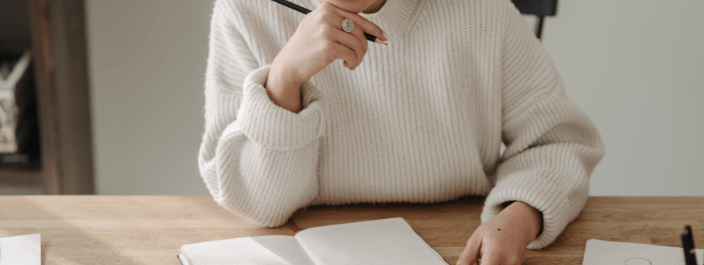
上述の通り、公認会計士試験では科目数の多い2段階の試験に合格する必要がある一方、その合格率は低く、その中でも独学の合格者の割合は10%以下と言われているため、独学での合格は難しいといわれることが多いです。
また、独学での合格が難しいといわれている理由として、以下の4つも挙げられます。
同じ会計系の資格である税理士試験は科目ごとの合格制度であり、一度科目に合格すれば生涯有効のため、1科目ずつ勉強して長期間での勉強が可能です。
一方公認会計士試験は、短答式試験は合格後による免除も2年間の有効期限があり、さらにすべての科目に一発合格する必要があります。論文式試験についても科目合格による次回試験での免除制度はあるものの、こちらも2年間と期限が定められています。
そのため、公認会計士試験は短期決戦と言われることが多く、短い期間で短答式・論文式試験の合格を目指す必要があるため、独学でコツコツ合格を目指すことは難しいと言われています。
公認会計士試験は短答式・論文式の2段階の試験に合格する必要があり、科目数も多く、勉強範囲が広いです。
そのため、合格までに必要な勉強時間は2,500~3,500時間だと一般的に言われています。
試験範囲が膨大なため、出題傾向に応じた効率的な勉強が必要となりますが、独学では出題傾向が分かりづらく対策も難しいため、3,500時間以上かかる場合もあるでしょう。
〈参考記事〉

短答式試験はマークシート方式なので、基礎知識と問題の読解力を基に消去法で解答することも可能です。そのため、市販のテキストや問題集でもある程度対策することもできるでしょう。
一方、論文式試験については、記述式のため問題を読み解いた上で、自分の言葉で解答しなければいけません。そのため、何が正解で何が減点対象になるのかなどの解答のコツも知る必要があります。
独学の場合には知識のインプットが中心となることが多いため、こうした解答のコツを含めた論文式試験に対して対策することが難しいといえます。
上述の通り、公認会計士試験の合格に必要な勉強時間は約3,000時間であると言われています。
そのため、長期間モチベーションを維持しながら学習する必要がありますが、独学の場合、予備校と違い近くに同じ目標を目指す仲間がいないため、モチベーションを保ちにくいことがあります。
また、どこから勉強を始めるかなどの勉強スケジュールや日々の学習進捗についても、独学の場合は全て自分で計画を立てて管理する必要があります。
〈参考記事〉
ここまで、独学で公認会計士試験の合格を目指すことについて、その難しさについて解説してきました。
短期決戦で合格しなければいけないのに対して膨大な勉強量が求められたり、また独学のためモチベーションや学習進捗の管理が難しい点などがデメリットとして挙げられるでしょう。
ただ、これらの難しさ・デメリットがある一方、それでも独学で合格を目指す方もいらっしゃいます。
ここからは、公認会計士試験を独学で目指すメリットをご紹介していきます。
公認会計士試験の予備校や専門学校、通信講座にかかる学費や受講料はかなり高額です。
一般的に通信講座や予備校に通うとなれば、70~150万円ほどかかるといえるでしょう。
独学で受験する一番大きなメリットは上記のような費用をかけずに済むということでしょう。最近は、使いやすい参考書や実際に予備校で使われているようなテキストもフリマサイトや中古などで安価で手に入れることができます。うまく活用すれば、費用をかけずとも勉強することができます。
二つ目は、時間の融通が利きやすいということです。
特に働きながら勉強をする場合、予備校のように決められた授業時間で学習するということが難しい方もいるでしょう。独学であれば、自分の都合の良い時間に合わせて勉強スケジュールを組み、自分のペースで勉強を進めることができます。
ここからは、独学で合格を目指す場合に重要となるポイントをご紹介します。
公認会計士の論文式試験では選択科目があり、「経営学」「経済学」「民法」「統計学」から1科目を選んで受験します。
得意とする分野がある場合にはその科目を選択することで学習時間の短縮につながるでしょう。
また得意科目がない場合、一般的には経営学を選択する人が多い傾向があります。他の科目に比べて専門性が低く、学習時間も短く済むと考えられているからです。また統計学についても暗記量が少ないため、選択する人が多いです。
かけられる学習時間が少ない場合には、選択科目を得意分野で選んだり、経営学・統計学から選択すると良いでしょう。
公認会計士試験は約3,000時間の勉強が必要と言われるほど、膨大な知識が求められます。その一方で、科目合格制ではないために短期決戦で合格する必要があります。
そのため、働きながら合格を目指す場合と勉強に専念する場合によって、スケジュールの立て方は変わります。
働きながら合格を目指す場合、勉強時間の確保がとにかく重要となります。社会人の場合、1日3時間の勉強でも3年以上はかかる計算です。
仕事と両立しながら勉強時間を確保する必要があるため、通勤時間などのすきま時間の活用はもちろん、出勤前の時間や、退勤後の時間なども勉強時間に充てることが求められるでしょう。
また、限られた時間で効率よく勉強を進めることも重要であるため、苦手なポイントの重点的な復習など、工夫して勉強を進めましょう。
上述の通り、公認会計士試験の合格のためには勉強時間の確保が重要となるため、その点大学生のように勉強に専念できる場合には合格を目指しやすいでしょう。
日々の勉強はもちろん、春休みや夏休みなどの長期休暇を利用して、毎日コンスタントに勉強することが重要です。
受験日から逆算して1日の中で必ず勉強する時間を決めて、ルーティン化しましょう。また、受験日から逆算した上で、どの科目のどの範囲をいつまでにやるのかを決めておけると、かなりスムーズに勉強できるでしょう。
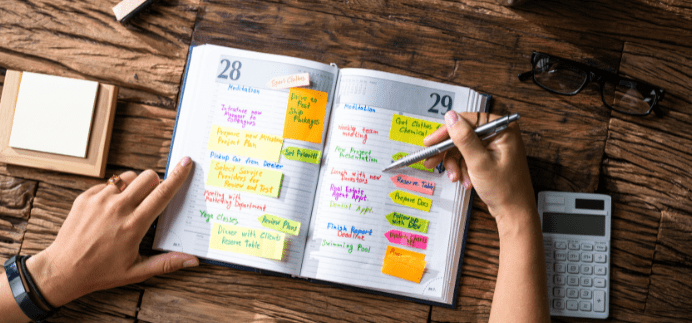
独学で公認会計士試験を突破するために、最新の試験動向をきちんと事前に調べることも重要です。
独学での受験では、なかなか試験の最新情報や傾向、法改正の情報などを掴むことができません。一方で試験では最新の法改正の内容も把握していないと間違えてしまう問題もあります。またその年の傾向などもあるため、このような予備校に通っていれば得られるような情報をしっかりとキャッチアップするためにも、積極的にコミュニティへの参加をしたり、XやInstagramなどのSNSで情報収集をしていく力も必要です。
独学で勉強している場合、どのテキスト・問題集を選ぶかは非常に重要です。
予備校では、独自に作られた最新の教材で勉強を進めることができます。しかし、独学の場合は自分で教材の収集を行わなければならず、一般に販売されている参考書の使用がメインとなるため、使う教材に限りがあります。
また、公認会計士試験に絡む法律は頻繁に法改正が行われるため、テキストや問題集についても最新のものを購入する必要があります。
以下の記事では、独学での合格へ向けて見ておくのにおすすめなテキストをいくつか紹介しているので是非ご確認ください。
〈参考記事〉
知識がない状態でアウトプットの練習をしても、学習効率は低いです。そこで、まずはテキストを使い、内容ひとつひとつの論理関係や考え方の根拠を深く理解するまで読み込むことを心がけましょう。
ただ、公認会計士試験は相対評価で合否が決まる試験であり、模試などのアウトプットの機会を通じて自分のレベルを知ることも重要です。
また、公認会計士試験は問題量に対して試験時間が短いこともあるため、時間間隔を身に付けるという意味でも模試を受験するのは良いでしょう。
また、多くの問題の中でもどの問題を解き、どの問題を捨てるかを判断しなければなりません。その感覚を養うためにも、各専門学校が提供する答案練習(通称:答練)を解いて最適な実践演習を積みながら、採点を通じて自分の答案の良否を判断しましょう。
当然、独立だけが公認会計士の唯一の目指し方ではありません。
代表的な他の2つの方法を見てみましょう。
大手の簿記や会計の専門学校や予備校の公認会計士コースを受講する受験生は多いです。
基本的に1年以上のコースが組まれており、独学と違って勉強のスケジュールや習得度の進捗管理も学校が行ってくれるので、心身ともに負担が少なくなります。ただその対価として100万円程度の学費を払うことになりますので、その認識は必要です。
しかし、実際試験合格者のほとんどは大手予備校や専門学校を経ているといわれているので、十分に費用対効果があると言えるでしょう。
〈参考記事〉
通信講座は時間割が決まっているわけではないので、自分の好きなタイミングで勉強を進められるのが人気です。
その反面、受験に向けたスケジュール管理については自分で行う必要がありますが、オンラインのため通学もしなくて良く、働きながら合格を目指す社会人には有効な手段といえます。
いずれの方法でも、簿記や会計の知識がなくても一からすべて教えてくれるので、授業内容を理解して確認テストを受けづければ、確実に合格に近づきます。勉強内容以外に考えないといけないことが少なく、試験に集中できる一方で、授業料や模試費用、教材費などでコストがかさむことは間違いありません。
独学で合格する人はかなり少ないものの、そもそもチャレンジする人が少ないのも事実です。独学での合格に必要なスキルや環境を知ったうえで、自分の特徴を分析して、公認会計士試験合格への最適な方法を選びましょう。独学で目指す場合、モチベーションや勉強ペースを維持しつつ、根気強くつづけることが重要になります。おすすめの教科書や勉強方法を参考に、自分に合う勉強方法を見つけてください!
〈参考記事〉