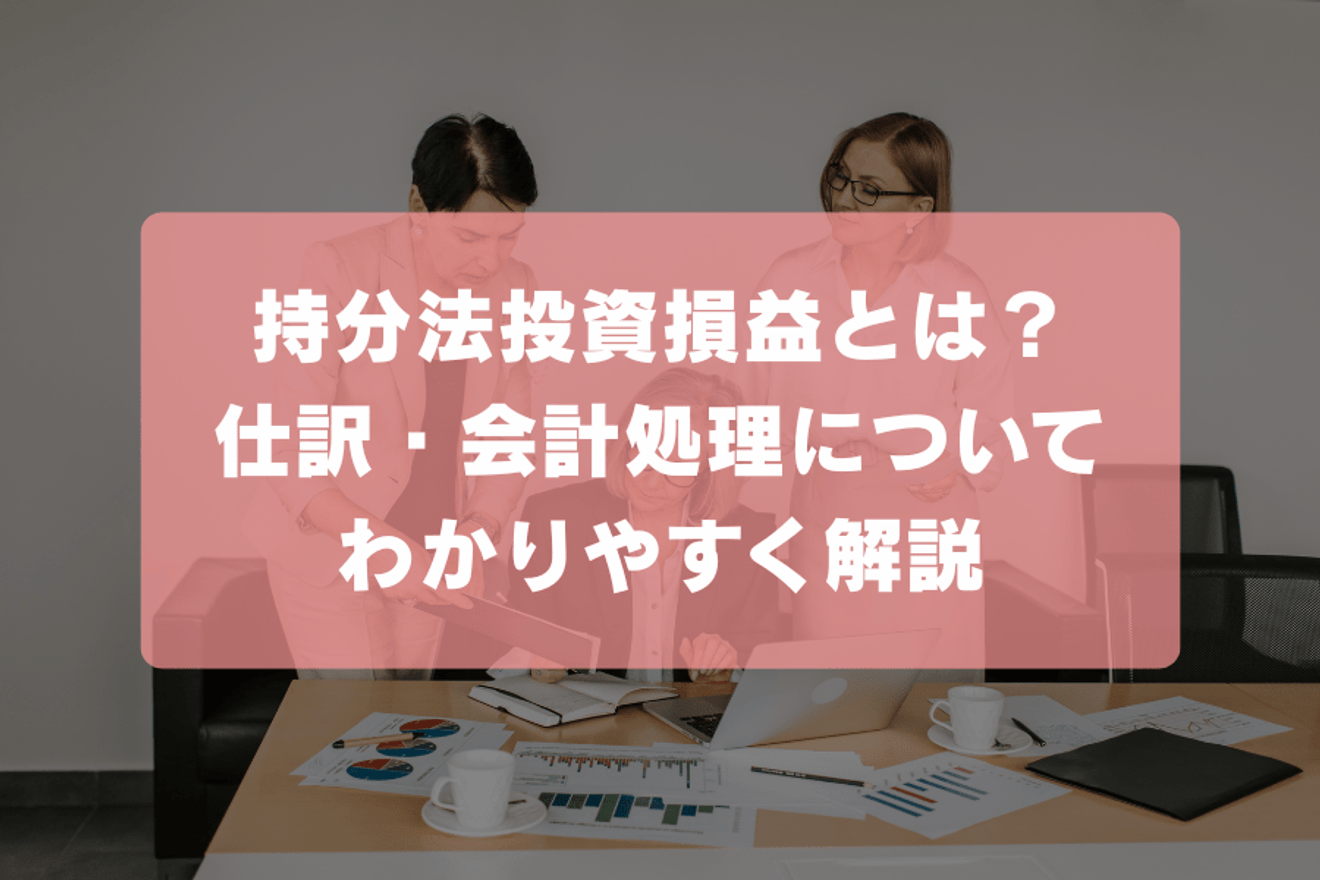
一昔前は製造業の会社は製造業に集中し、小売業は小売業に集中する等、単一業種である会社がほとんどでした。しかし、消費者ニーズの多様化によって、企業も多様化・多角化が行われるようになりました。その結果、子会社の設立や、他業種や海外企業と関連会社を設立する等、企業の構図はどんどん変わってきています。
このように企業が様々な会社を保有することになり、連結決算や持分法という会計処理が多くなってきました。ここでは持分法投資損益について現役公認会計士が解説していきます。

持分法投資損益(もちぶんほうとうしそんえき)とは、持分法を適用した際に計上される損益を言います。これは、持分法適用会社(関連会社)が計上した利益のうち、投資会社が保有している持分割合分について損益を計上するものです。
一方で、関連会社ではなく子会社の場合は連結決算と言って、基本的に子会社が獲得した損益をそのまま取り込むことになるため、子会社が計上した外部売上や計上した外部への支出がそのまま連結財務諸表として合算されることになります。
持分法では、そのような損益を一つ一つ計上するわけではなく、税引後損益のうち持分割合を一括で計上することになります。こういったことから、通常の連結決算を「全部連結」、持分法による連結方法を「一行連結」と呼ぶことがあります。
なお、持分法投資損益を計上する理由は、関連会社が獲得した利益はいつか配当や株式の売却損益によって実現されると考えられますが、事前にその損益を取り込むことでタイムリーに損益を決算書に反映させる効果があるためです。
先ほどの話のように、持分法は関連会社に対して適用されます。では、関連会社とはどのような会社なのでしょうか。
特別な事項がない限りは、投資会社の発行済株式総数の20%以上を保有している場合は関連会社として持分法の適用対象となります。ただし、15%保有していたとしても、役員の派遣や技術的に密接に関係している会社である場合には、関連会社として持分法の適用を行わなければならない可能性があります。この点については、一定のガイドラインが会計基準にかかれているものの、実際は担当する公認会計士と相談の上で最終判断となることが多いです。
一方で、20%以上投資先の株式を保有していたとしても、その投資が一時的な場合や、持分法を適用することによって投資家がミスリードをしてしまう可能性が高いものについても関連会社としてカウントせずに持分法を適用しない場合もあります。
持分法投資損益は、投資企業の税引後損益に対して自社の持分割合を乗じることで計算されますが、損益計算書上どこに計上されるでしょうか。
あくまで、投資に係る損益になるので、他の金融損益と同じように営業外損益として計上されます。なお、関連会社の税引後利益が100万円で、持分比率が30%であった時の決算時の仕訳は以下の通りです。

100万円に30%をかけただけなので、計算は容易だったと思います。
通常の会計処理では、持分法適用会社の損益に持分割合を乗ずることで済みました。しかし、持分法適用会社が債務超過であった場合は特殊な判断が必要です。
まず、株式取得以外に契約が存在せず、例えば関連会社が倒産したとしてもその責任を負わない場合、関連会社が債務超過の場合は損益の計上はありません。これは、投資額以上の損失を被ることがないのに、損失をそれ以上取り込んでしまうと投資家が誤解するからです。
一方で、債務保証やそれ以外の契約などにより、関連会社の債務を支払う義務が発生する可能性が高い場合は、債務超過であったとしてもその損失発生の可能性の範囲内で損失を取り込む必要があります。その際の貸方の科目は投資有価証券ではなく、貸付金となり、直接減額をしていきます。
単純に税引後損益に持分割合を乗ずる以外にも持分法投資損益を計上することがあります。それは、連結決算の際に行われる特殊な仕訳を持分法でも行った場合です。ここでは代表的なものについて紹介します。
まず、関連会社と製品を売買し、未だ在庫として計上されている場合、その損益は実現していないということで、その未実現利益を消去する必要があります。その未実現利益分投資有価証券を減らし、持分法投資損失を計上する必要があります。
また、関連会社との取引があり、売掛金が期末に残った場合です。その際、個別財務諸表では貸倒引当金が計上され、費用計上されているはずですが、連結上はその貸倒引当金もなかったことにするため、該当する部分の持分法投資損益を計上することとなります。
この他にも連結決算であれば消去されていた損益が存在する場合は、同様に持分法投資損益を計上する必要があります。