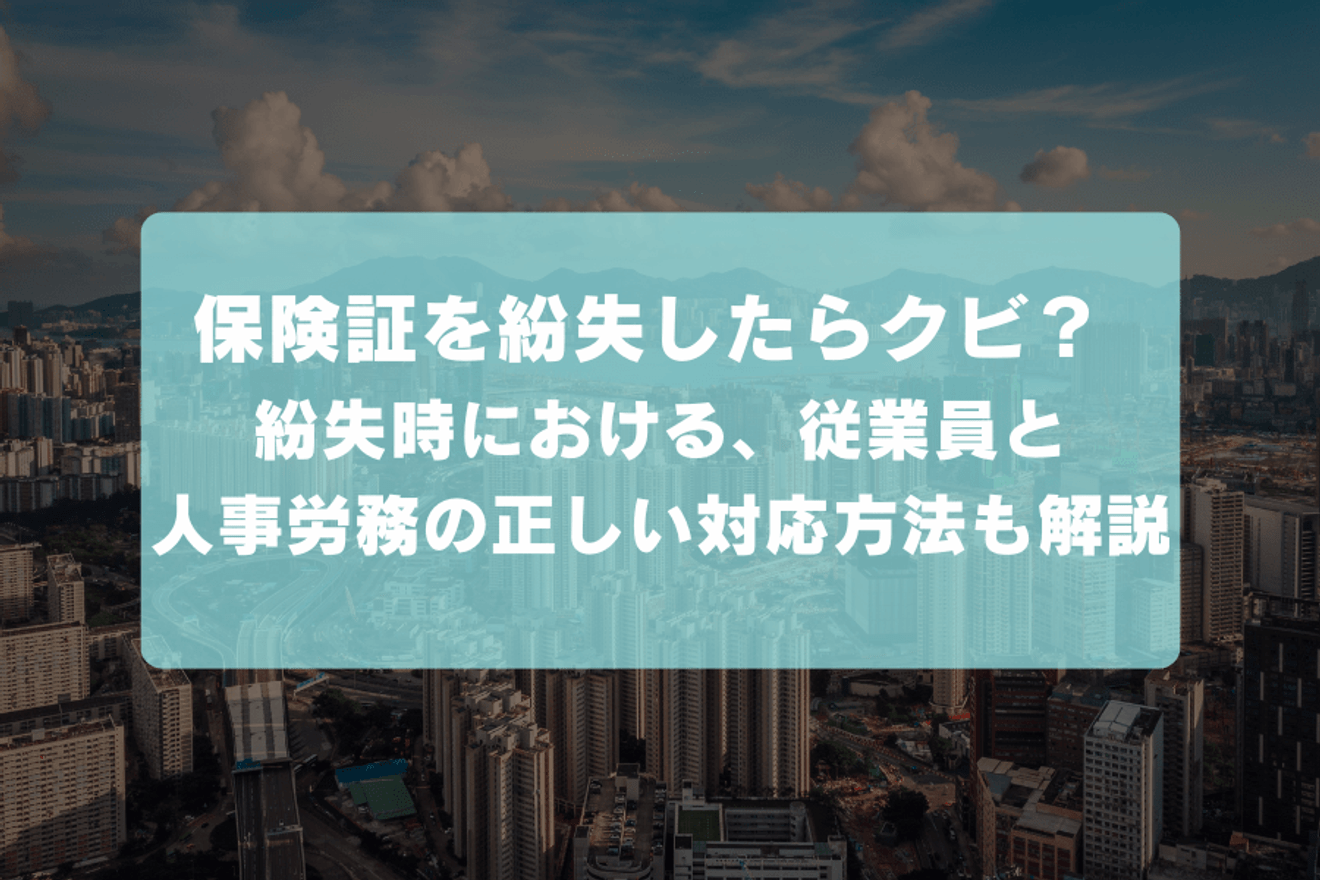
保険証をなくしたらクビになる?と不安に思う方もいるかもしれません。ですが、保険証の紛失は原則として解雇には当たりません。
とはいえ、対応を誤るとトラブルにつながる可能性があります。
本記事では、紛失時に従業員が取るべき行動、会社側(人事・労務)の対応ポイント、制度変更に伴う注意点について解説します。
「保険証を失くしただけでクビになるのでは?」と不安に思う方もいるかもしれませんが、基本的にはその心配は不要です。
労働契約法第15条では、懲戒処分を行うには「就業規則に定めがあること」が必要とされています。つまり、保険証の紛失が処分対象になるかどうかは、会社ごとのルール(就業規則)によって判断されます。
多くの企業では、懲戒事由として「会社の財産や情報に重大な損害を与えた場合」や「故意・重過失による損害」などが挙げられています。
保険証を「うっかり紛失」しただけであれば、懲戒や解雇にはあたらず、注意指導や始末書の提出で済むケースがほとんどです。
ただし、以下のようなケースでは、懲戒処分や最悪の場合は解雇につながる可能性があります。
このように、問題となるのは「紛失そのもの」ではなく、「その後の対応」や「信頼関係への影響」です。
たとえば、保険証を失くしたことを隠して医療機関で不正に使用されてしまったり、会社に虚偽の報告をした場合は、重大なルール違反とみなされる可能性があります。
また、同じような紛失が何度も繰り返されると、「情報管理能力に欠ける」と判断され、処分の対象となることもあります。
このように、紛失後の対応次第では処分の対象となる可能性もあるため、保険証の取り扱いには十分な注意が必要です。
では実際に、保険証を紛失した場合にどのようなリスクがあるのか、従業員と会社それぞれの視点から見ていきましょう。
保険証には、氏名・生年月日・住所・保険者番号などの個人情報が記載されています。
これらの情報は、消費者金融での借り入れやクレジットカードの不正作成などに悪用される可能性もあります。
保険証単体では本人確認書類として使えませんが、他の情報と組み合わせることで悪用されるリスクが高まることになります。
保険証がない状態で医療機関を受診すると、健康保険が適用されず、医療費を一時的に全額自己負担する必要があります。後日、保険者に「療養費払い」の申請をすれば基本7割分が返金されますが、申請には時間と手間がかかるため、急病時などには大きな負担となります。
保険証は会社を通じて交付されるため、もし、従業員の紛失が外部に知られると、個人情報管理が不十分であると評価されるリスクがあります。特に、社内で紛失が頻発している場合は、社内の教育や管理体制そのものが問われることになり、取引先や顧客からの信頼低下につながる可能性もあります。
まずは、紛失に気づいた時点で、すぐに動くことが大切です。
速やかに会社の担当部署(人事・労務など)へ報告しましょう。報告内容には、「紛失日時」「紛失場所」「紛失経緯」などを含めると、会社側も適切な対応を取りやすくなります。
紛失時には、会社を通じた手続きが必要なため、紛失を隠すと手続きが遅れたり、かえって問題が大きくなる可能性があります。
悪用防止のため、最寄りの警察署で遺失届を提出しましょう。
紛失した事実を公的に記録しておくことで、万が一第三者に悪用された場合でも、故意ではなく、適切な対応を取っていたことを示す材料になります。
なお、盗難の可能性がある場合は、被害届の提出も検討しましょう。
万が一、第三者によるなりすましで、無断でローン契約を結ばれたり、クレジットカードを作成されたりする事態に備え、信用情報機関に保険証の紛失を届け出ると安心です。
具体的には、信用情報機関(CICやJICC)が提供する「本人申告制度」を利用します。
この制度により、保険証の紛失情報が記録され、金融機関などが新規契約を結ぶ際にその情報を確認できるようになるため、被害を防ぐことが可能です。
保険証の紛失報告を受けた際、会社側が適切に対応することで、従業員の不安やトラブルを未然に防ぐことができます。特に制度変更期である今は、従来とは異なる対応が求められるため、以下のポイントを押さえておきましょう。
従業員から紛失の報告を受けたら、まずは健康保険組合や協会けんぽに連絡し、保険証の代替となる「資格確認書」の発行手続きを進めます。
これは、従来の保険証が発行されなくなる制度変更に伴う対応です。
資格確認書は、医療機関で保険診療を受けるための証明書として機能します。
※制度変更の詳細は、次のセクションで解説します。
紛失の経緯(日時・場所・状況)を記録し、必要に応じて社内共有しましょう。
また個人情報の観点からも、記録は関係部署のみがアクセスできるよう管理し、再発防止策として社内研修や注意喚起を行うことも有効です。
2025年12月をもって、カード型の健康保険証は廃止される予定です。
今後は、マイナンバーカードを健康保険証として使用する「マイナ保険証」による受診に移行します。
すでに多くの医療機関ではマイナ保険証に対応しており、受診時にはカードを読み取ることで保険資格が確認される仕組みです。
この制度変更により、紛失時の対応も変わってきています。
2024年12月2日以降、従来の保険証の新規発行は停止するとともに、再発行もされなくなりました。
紛失した場合は、代わりに「資格確認書」が発行される仕組みに変わっています。
資格確認書は、健康保険の加入者であることを証明する書類です。マイナ保険証を未登録・紛失・未取得などで利用できない人向けに交付されます。
医療機関で提示すれば保険診療を受けることができます。
なお、マイナ保険証を登録済みであっても、以下のようなケースでは資格確認書が交付されることがあります。
こうしたケースに備え、従業員からの問い合わせにも対応できるよう、人事・労務担当者は制度の背景や発行条件などあらかじめ把握しておくことが重要です。
資格確認書にも、氏名や保険者番号などの個人情報が記載されているため、紛失した場合は保険証と同様の対応が必要です。
従業員側は会社への報告、警察への遺失届提出、必要に応じて信用情報機関への申告など、前述の対応フローを参考にしながら、速やかに再発行のための手続きを進めましょう。
繰り返しになりますが、保険証の紛失は、原則として解雇(クビ)にはつながりません。
しかし、対応を誤ったり、隠したりすると、信頼を損ない、最終的には懲戒処分につながる可能性もあります。まずは正直に会社へ報告し、冷静に対応することが何より重要です。
制度変更についても触れましたが、現在、マイナ保険証へと移行中であり、紛失時は「保険証の再発行」ではなく「資格確認書」で対応する流れに変わっています。
会社側も、従業員が安心して医療を受けられるよう、制度変更に合わせたサポート体制の整備が求められます。
最後に、紛失を防ぐための対策を紹介します。
保険証の取り扱いは、個人情報管理の一環でもあります。従業員側も企業側も適切な対応を心がけましょう。