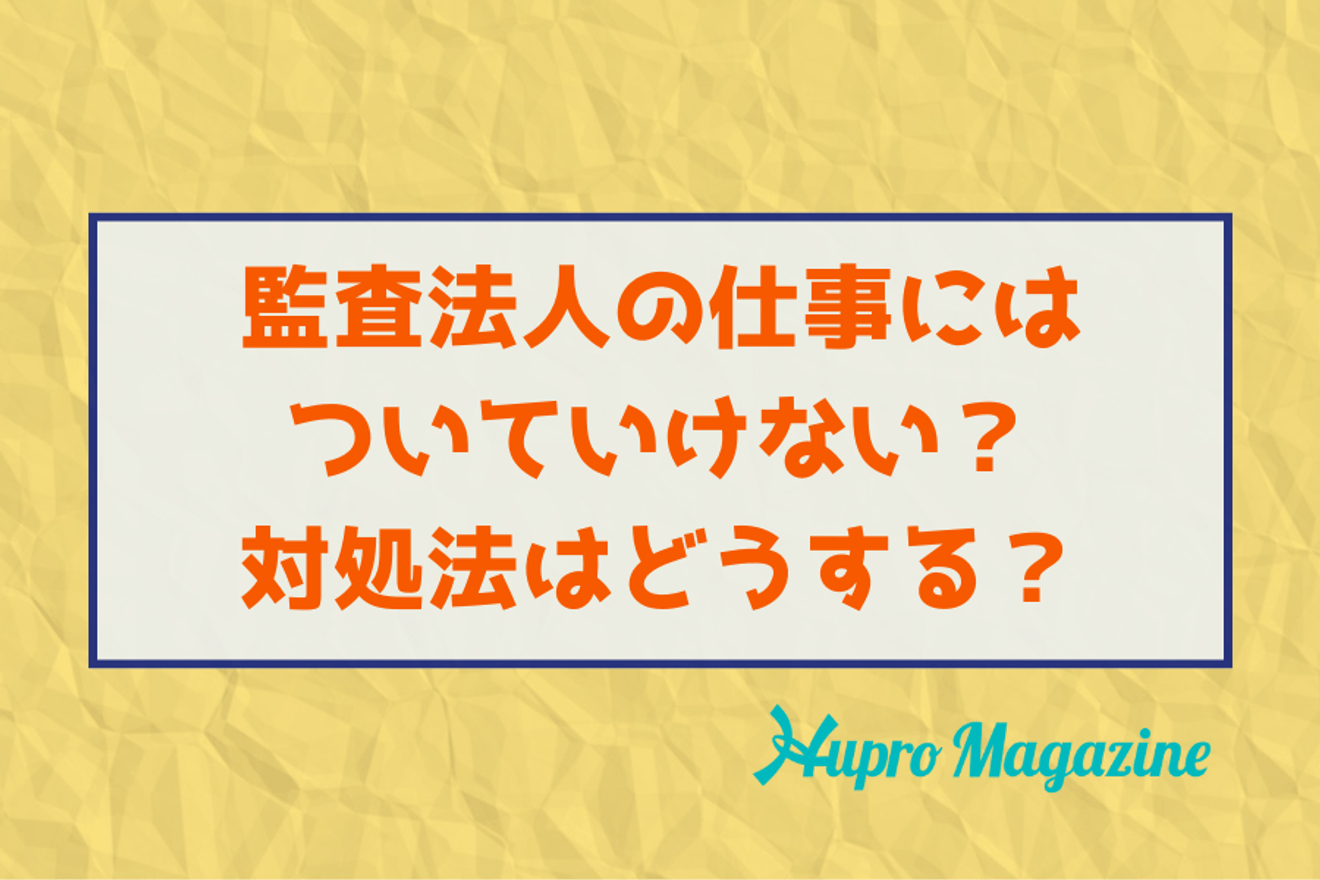
監査法人の仕事は専門性や難易度が高いため、たとえ公認会計士の資格を持っていたとしても、「ついていけない」と感じる方も一定数いらっしゃるようです。もし「ついていけない」と感じたらどうすればよいのでしょうか?「ついていけない」と感じる理由から、その対処法や取れる選択肢にフォーカスをあてて解説します。
監査法人の仕事についていけないパターンとして、主に以下のようなケースがあります。
それぞれ具体的に解説していきます。
監査法人の主な仕事は、クライアントである企業の監査を行う「外部監査」およびその補助です。監査は企業の財務数値の正確性を保証する役割があり、社会的な重要性も非常に高いですが、それだけにミスができないだけでなく会計に関する高い知識と実務スキルが必要となります。
公認会計士の資格を持っている方は、資格試験を突破するために多くの知識を習得していますが、それが必ずしも「実務をこなせる」ことに繋がるわけではありません。監査業務では問題の核心を探すだけでなく、クライアントに分かりやすく正しい会計処理を説明する能力も求められるのです。
このように多様かつ高いスキルが無いと対応できない業務レベルの高さに、「ついていけない」と感じることもあるようです。
監査法人は、一般的には業務量が多く、残業時間も長いとされています。特に日本企業の多くが3月決算としているため、その後の4,5月に監査の依頼が集中します。それにより、繁忙期には月の残業時間が60時間を超えたり、休日出勤が必要になるケースも増えます。
そのためワークライフバランスを高いレベルで保つことが難しく、ハードな働き方についていけなくなる方がいらっしゃいます。
監査という仕事の特性上、監査法人の担当者は財務情報のミスをクライアントに指摘する必要があります。場合によってはクライアントが隠そうとした不正を暴き、公表前に未然に防がなければならないというケースも発生し得ます。
もちろん、監査で財務情報を正しくすることはその企業の健全性や信頼性の担保に大きく貢献しますが、クライアント企業の当事者からは煙たがられることもあると聞きます。
社会的役割の高い仕事をしながらも、このようにクライアントとの関係に苦労することも「ついていけない」と感じる一因となっているようです。
公認会計士は難易度の高い資格試験に合格し、狭き門を突破した希少な人材というイメージがあるのではないでしょうか。しかし監査法人は、公認会計士資格を持っていることが当たり前のような環境です。
特にBig4監査法人などの大手では出世競争があることもあり、優秀な同僚と自分を比べて、「ついていけない」と感じてしまうこともあるようです。
このように、監査法人で「ついていけない」と感じるには様々な理由があるようですが、実際に監査法人での仕事に「ついていけない」と感じてしまった場合に取ることのできる選択肢をご紹介します。
まずは、「ついていけない」と感じた要因を乗り越える方法を検討してみましょう。
例えば業務レベルや同僚の優秀さへの懸念があるのであれば、研修や勉強によって自身のスキルを向上させることで解消できるかもしれません。
もしくは、自身の業務量を減らすことが難しくても、業務改善ツールやAIの利用などによって効率化できるかもしれませんので、導入の提案を検討してみるのも1つの手です。
また、監査業務は1つの案件に対して基本的にチームで取り組むため、チームで協力することで1人当たりの業務負担を軽減することも可能です。
多忙な環境や周囲に優秀な人材が集まっている環境では、「どうして自分だけが…」と挫折してしまいやすいです。しかし、実際に「ついていけない」と感じた要因が、自分の力でどうにか改善できるものなのか、周囲の力を借りれば改善できるものなのか、それとももうどうしようもないものなのかを冷静に分析することで、その後にどのような選択肢を選んだとしても後悔が残りにくいでしょう。
①を検討した上でも「ついていけない」と感じた場合は、他の監査法人への転職を考えてみましょう。同じ監査法人でも働き方や業務内容をよく見ると千差万別であり、転職によって「ついていける」職場で働ける可能性もあります。
例えば、人間関係についていけないと感じている場合は、環境そのものを変えることで働きやすさが180度変わる可能性もありますし、業務レベルの高さについていけないと感じている方は、より研修制度が充実している環境に移ることで、順を追って着実に成長できる可能性もあります。
「監査業務そのものをやりたくない」という訳でないのであれば、他の監査法人への転職はオススメの選択肢です。
②を選択肢の一つとしてご紹介した手前ですが、どうしても「監査法人の特性」は共通する部分も多く、場合によって他の職種を検討した方が良いケースもあります。例えば、程度の差はあるものの、繁忙期に残業時間が長くなるのはほとんどの監査法人に当てはまる特徴です。また、そもそも監査という業務自体についていけない場合は、公認会計士の知識の別の活かし方を模索するのが最適解といえるでしょう。
実際に、監査法人での経験や公認会計士としての知識は非常に幅広い環境で活かすことができます。ではどのように活かせるのか、次の章で見ていきましょう。
監査法人で働いていると、転職したくても「監査法人での経験は監査法人でしか活かせないのではないか」と、自身のキャリアに不安を感じている方も多いのではないでしょうか?
結論、監査法人での経験は転職において大いに活かすことが可能です。監査法人で主に関わることになる監査業務は、上場企業や大企業などの監査が義務づけられている企業にとっては欠かせない業務である一方で、専門性の高さからその業務に対応できる人は限られています。
そのため監査に携われる人材の市場価値は非常に高く、他の監査法人はもちろん、様々な職場で必要とされます。
特に近年は、公認会計士の人手不足が深刻なため、公認会計士資格を持っているだけで引く手あまたです。
転職の際には、監査業務に取り組む上でチームワークを発揮したエピソードや、監査法人での経験を通して身に着いたスキル、学んだことを整理してしっかりと話すことができれば、転職で困ることはまずないでしょう。
監査法人での経験を活かせるキャリアの選択肢については、次の章で詳しくご紹介します。
監査法人から他の職種へ移る際のキャリアパスとして代表的なものを見ていきましょう。
公認会計士が事業会社に転職する場合、大手企業であれば経理部門、ベンチャー企業であればCFOなどのポジションでニーズが高いです。この場合、「組織内会計士」や「企業内会計士」として、自社の会計業務に従事することになります。
事業会社と監査法人での最も大きな業務内容の違いは、企業の財務状況を外部からチェックするのか内部からチェックするのかの違いです。一言で言えば、これまで監査法人でクライアントとして関わっていた一般企業に、今度は内部の人間として関わるということです。
監査法人から事業会社に転職することで改善されやすいポイントは、ワークライフバランスです。特に大手企業では福利厚生が充実しており、多様な働き方が用意されていますので、「業務量の多さについていけない」ということにはなりづらいでしょう。
またベンチャー企業では公認会計士が複数在籍しているケースは多くないため、「優秀な同僚についていけない」というようなことも少なく、CFOなどのポジションに就くことができれば、かなりの裁量権を持って自由な仕事の進め方ができるでしょう。
税理士事務所や会計事務所は、一般的に税理士が開業している事務所のことを指しますが、公認会計士は税理士試験が免除されるため、一定の条件を満たせば税理士としても働くことができます。
税理士事務所や会計事務所で働く場合は、クライアントの税務申告の代理や税務相談などといった業務が中心になるため、監査とは違ってクライアントから感謝を伝えられる機会が多いとされています。
そのため、「クライアントとの関係性」に悩むことが少なくなる可能性が高いといえます。
企業の経営に関して総合的な分析やアドバイスを行うコンサルティングファームでも、公認会計士資格や監査経験を活かすことができます。特に、財務に特化したFAS系コンサルティングファームでは、公認会計士の資格取得や監査業務を通して培った会計の知識を遺憾なく発揮できるため、監査法人からの次のキャリアとしてはオススメです。
企業の経営戦略を考える上で財務のプロフェッショナルとしてアドバイスを行うため、税理士事務・会計事務所と同様に、クライアントから感謝を伝えられることも大いにあります。FAS系コンサルティングファームは、特にM&Aやデューデリジェンス(M&Aや投資の際に行う分析業務)など、財務に特化した支援サービスを提供しており、監査知識に加えた専門知識が求められるため、監査法人での業務レベルとは違った難しさがありますが、平均年収が高いため、年収アップを狙いたい方にはオススメです。
企業経営にとって必要不可欠な会計に関してのプロフェッショナルである公認会計士は、企業の経営支援を行うコンサルティングファームでも重宝されるでしょう。
その他にも金融機関やM&Aアドバイザリーなど、会計知識を活かせる選択肢は幅広くあります。公認会計士資格の取得や監査法人への勤務は大変な分、その知識や経験は様々な場所で活かすことができます。また、独立開業は経営不振に陥るリスクはあるものの、自由度が高く不必要な社内コミュニケーションもなくなるため、目指す方も多いキャリアパスです。
《関連記事》
監査法人の規模にもよりますが、比較的収入が安定している監査法人を辞めるとなると、年収が一気に下がってしまうのではないかと不安に感じられる方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そこで、実際の求人例を参考にしながら、監査法人以外の職種の年収相場を見ていきましょう。
| ポジション | CFO候補 |
| 仕事内容 | ◆財務経理業務全般(経営会議資料の作成等) ◆管理部門のマネジメント ◆資金調達/資金繰り管理 ◆監査法人対応等 |
| 応募資格 | <必須業務経験> 監査法人や金融機関との折衝経験 |
| 給与 | 年収800〜1,200万円 |
| 福利厚生 | 通勤手当、家族手当、住宅手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、退職金制度 <各手当・制度補足> 通勤手当:社内規定あり 家族手当:配偶者10,000円/子供5000円(22歳以下) 住宅手当:単身15,000円/同居25,000円 社会保険:確定拠出年金あり(基本給に対し、4.6%拠出) 退職金制度:再雇用あり、確定拠出金あり <定年> 65歳 <育休取得実績> 有(育休後復帰率100%) <教育制度・資格補助補足> ◆資格取得支援制度(合格祝い金支給) ◆資格手当:宅地建物取引士20,000円 ◆資格取得支援制度 ∟宅建社内模擬テスト(年3回程度実施)/合格祝い金の支給 ◆出産・育児支援制度(一部従業員利用可) ◆その他制度:確定拠出年金制度、育休・産休制度、提携保養施設、入居促進手当、家族手当 <その他補足> ◆給与改定:あり ◆賞与:あり(業績による) ◆確定拠出年金あり ◆健康診断人間ドック切替補助 ◆インフルエンザ接種補助 ◆保養施設利用 ◆年間有給休暇 ◆育児短時間勤務制度 ◆出産・介護休業制度 ◆育児休業(取得実績あり) ※育休復帰率100%、有給取得率93%(2023年11月~2024年10月)とワークライフバランスを保ちながら働くことができます。 |
前述の通り、経理として働く場合は大手企業が多く、ベンチャー企業の場合はCFO(最高財務責任者)というハイクラスポジションが用意されている場合が多いため、給与水準や福利厚生の充実度は高い傾向にあります。企業によって幅はありますが、年収相場としては中堅~大手監査法人と同程度といったところでしょう。
| ポジション | 税務会計スタッフ |
| 仕事内容 | 【実施して頂く業務の例】 ■クラウド会計の初期導入業務 ■会計アドバイザリー業務 ■財務コンサルティング業務 ■DXコンサルティング業務 ■M&A、組織再編、事業再生、IPOサポート ■事業承継・資産税 ■法人税務・個人税務 |
| 応募資格 | <学歴> ◎大学卒以上 <資格> 【必須資格】 ◎税理士資格または公認会計士資格 【必須業務経験】 以下のいずれかの条件を満たす方 ◎税務経験3年以上 |
| 給与 | 年収800〜1,000万円 |
| 福利厚生 | 昇給年1回 賞与年2回 社会保険完備 交通費全額支給 資格手当 所内外研修制度 税理士会登録費・会費事務所全額負担 参考書籍購入制度 |
税理士事務・会計事務所の年収は、CFOやコンサルティングファームと比較するとやや低めといった印象がありますが、監査法人と比較して働きやすい環境が確保されていることが多いため、働きやすさに対する給与としては十分に高い給与水準と言えます。
| ポジション | 事業再生アドバイザリー |
| 仕事内容 | 【業務内容】 財務及び事業に関する深い知見をもって、クライアント並びにその投融資先に対して主に以下のアドバイザリーサービスに携わっていただきます。 ■事業の継続・売却・清算等戦略オプションの検討及び実行支援 ■私的整理(事業再生ADR・地域経済活性化支援機構・中小企業再生支援協議会・任意整理)及び法的整理(民事再生・会社更生)支援 ■資本・事業・業務・組織等について抜本的な見直しを含む中期経営計画の策定及び実行支援 ■再生ファンド・PEファンド・不動産ファンド等投資家による投資検討・バリューアップ・Exit支援 ■地域金融機関の取引先を主とした地域間・地域内の企業連携・資本提携並びに経営の次世代承継支援 |
| 応募資格 | 【学歴】 4年制大学卒以上 【必須要件】 下記のいずれかに該当する方 ◎金融機関(法人向け業務)または事業会社における原則3年以上の実務経験 ◎公認会計士または米国公認会計士等の外国会計士の資格保有者で、Big4監査法人(国内外問わず)における原則3年以上の実務経験 ◎コンサルティングファームにおける事業戦略立案・トップライン向上・コスト最適化プロジェクトの実務経験 ◎金融機関の本部・アドバイザリーファーム等における事業再生アドバイザリー業務の実務経験 ※本部審査関連機能における経験・広い行内外ネットワークを有する方を特に歓迎 ◎セルサイドM&Aのフィナンシャル・アドバイザリーのプロジェクトマネージャー経験 ※再生型M&Aの経験者や銀行のM&A担当部署経験者は特に歓迎 【歓迎要件】 ○ビジネス遂行可能な英語力 |
| 給与 | 年収600〜2,000万円 |
| 福利厚生 | ■交通費支給 ■健康保険 ■厚生年金保険 ■雇用保険 ■労災保険 ■厚生年金基金 ■KPMGグローバル研修 ■KPMG Japanグループ研修 ■KPMG FAS独自研修 ■その他コンサルティングスキル基礎研修等多数 ■カフェテリアプラン制度 ■財形貯蓄制度 ■公認会計士企業年金基金 |
コンサルティングファームは基本的に成果主義であることが多いため、短期での昇格や昇給がしやすく、それに応じて高年収を狙いやすいですが、裏を返すと実力次第では年収が低くなる可能性もあり、年収の幅が広いことが特徴です。
他の求人も見たい方はこちらからご覧ください。
上記でご紹介したような職種に転職するにあたって、失敗しないための注意点を見ておきましょう。
当然ですが監査法人から転職したいと思った理由が、応募する職種や企業に当てはまらないかは確認しましょう。
「年収が今よりもいいから」とか「知り合いが働いているから」などで、軽い気持ちで入社してしまうと、根本的な課題を解決することができずに再度転職をしなければならなくなってしまうので、注意しましょう。
監査法人での経験は市場的には高い価値がありながらも、当人がアピールするのは中々難しいという声をよく聞きます。せっかくそのような経験を積んでるにもかかわらず、転職活動に苦戦してしまうのは非常に勿体ないといえるでしょう。
スムーズに転職に成功するためには、転職エージェントを利用するのがオススメです。士業・管理部門特化の転職エージェントであるヒュープロは、監査法人からの転職を多くご支援させていただいた実績がございますので、是非ご相談からお待ちしております。
本編の最後に、当社ヒュープロでご支援させていただいた監査法人からの実際の転職事例をご紹介します。
新卒から中小監査法人に勤められていたOさんは、繁忙期の業務量の多さから転職を検討されていましたが、残業が100時間に迫る月が発生したことで「ついていけない」と感じ、転職活動を本格化されました。
先述したように、「監査法人の特性」として一定の残業が発生することは避けられませんが、転職によって残業の程度を減らすことは可能です。Oさんは引き続きクライアントの監査を担当する監査法人で働きたいという意向もあったため、残業を少なくできるような仕組みを取り入れている監査法人を中心にご提案しました。
その結果、3法人からの内定を獲得し、そのうちの1つである準大手監査法人への入社を決められました。3年ほど経験しかなかったため不安を抱きながら転職活動を始められたとのことですが、価値ある経験をどのようにアピールするかという部分をキャリアアドバイザーからお伝えしたこともあり、後半は自信を持って活動を進められたと仰っておりました。
公認会計士の資格を活かして監査法人やコンサルティングファームで勤務されていたDさんですが、突発的な残業が発生しやすいクライアントワークと子育ての両立に「ついていけない」と感じるようになり、他職種への転職を考えるようになりました。
DさんはもともとBig4監査法人で働かれていたので、年収を維持するためにも上場企業での就業を希望されていました。上場企業は福利厚生や働き方の選択肢が充実していることが多い一方で、求職者からの人気も高いため、なるべく幅広い求人に応募していただくよう、お伝えしました。
その結果、40社以上の上場企業に応募していただき、その中の一つへの入社を決められました。850万円ほどの年収だった前職からのキャリアチェンジに不安もあったとのことですが、ほぼ同程度の年収をもらえる企業への転職に成功されました。
今回は監査法人の仕事に「ついていけない」と感じる理由について解説しました。「ついていけない」理由は人それぞれですが、自分で改善することが難しければ、職場を変えるしかないでしょう。他の監査法人なら解消しうるのか、そもそも職種を変えるべきなのか、よく見極めて転職していくのがよいでしょう。