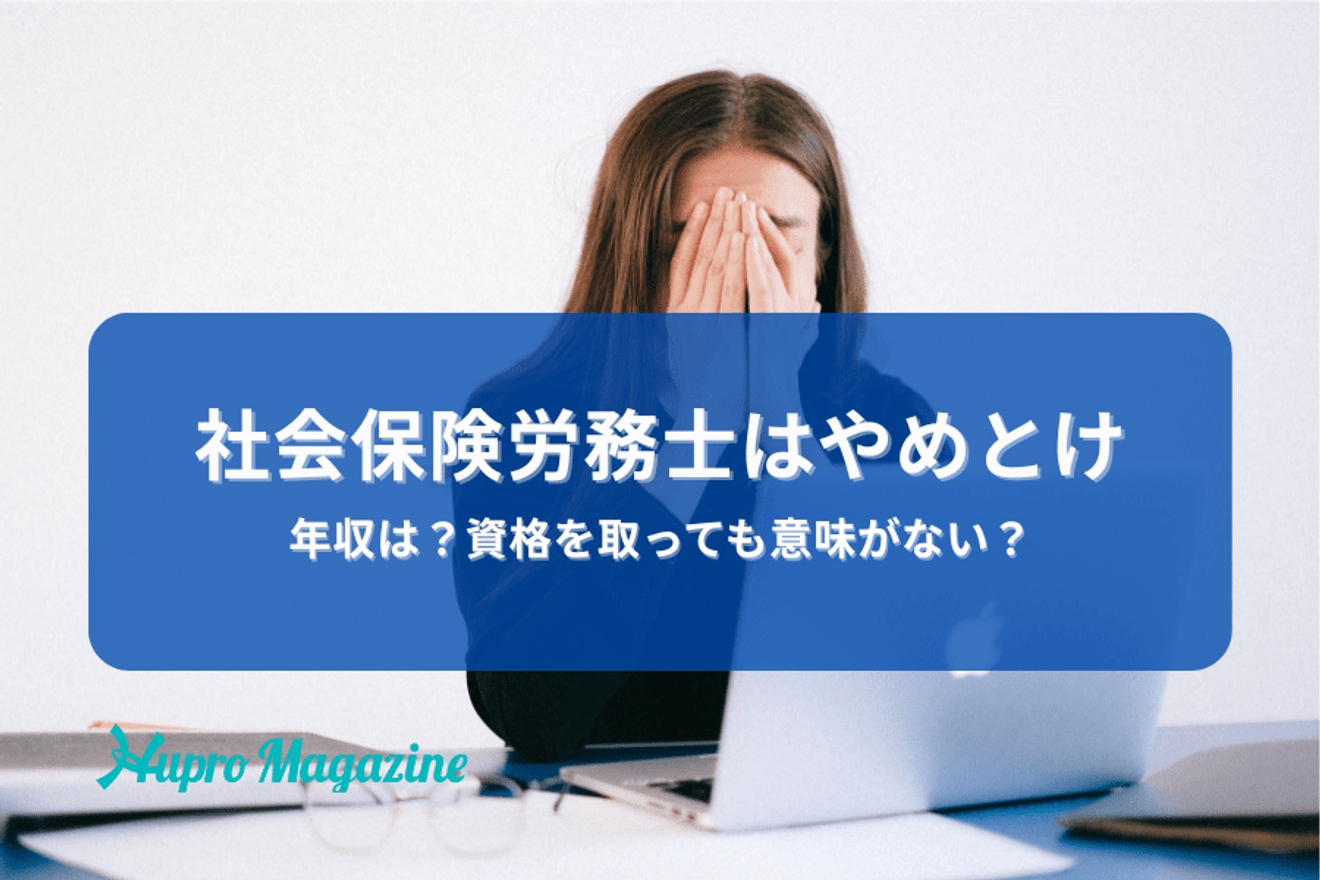
社会保険労務士は企業の労務管理や社会保険手続きに関する専門職ですが、資格取得に対して「やめとけ」との声を耳にすることもあります。本記事では、なぜ社労士が「やめとけ」と言われるのかや不安要素の真相について詳しく解説した上で、資格取得のメリットや向いている人についてもご紹介します。
労務や社会保険の専門家である社会保険労務士(以下、社労士)を目指すにあたって、「やめとけ」という意見が出てくる代表的な理由を5つご紹介します。
社労士資格を取得するためには社労士試験に合格しなければなりませんが、その試験は難関とされます。合格率は例年6%前後を推移しており、2024年の試験でも6.9%と非常に低い数字でした。
また試験内容も、法律、労働法、社会保険に関する幅広い知識が問われます。特に労働法規や年金制度に関する理解が深く求められ、法律を扱うため、条文の暗記や応用力も重要です。
このように幅広い知識を身に付けなくてはならないため、1,000時間ほどの勉強が必要とされ、資格取得までに数年かかる場合もあります。このように試験合格までの道のりが厳しく挫折する方も少なくないことから、「やめとけ」と言われることがあります。
また、試験は年1回しか行われないため、不合格の場合、再挑戦には1年待たなければならず、長期戦になることが精神的に負担となる場合もあります。独学で挑む方も多いですが、予備校に通うなどのサポートを利用することが一般的です。
《関連記事》
社労士の仕事内容は労務や社会保険関連の書類手続きが主な業務になります。特に給与計算や給与明細の作成、勤怠管理などの地道な作業が多いため、このような地道な作業が苦手な方からすると「つまらない」と感じてしまうようです。
せっかく難関な社労士試験に合格しても、実際の業務がつまらないと感じてしまうのであれば、「やめとけ」と言われてしまうことも想像つきやすいでしょう。
社労士は国家資格の一つで社労士は企業や個人にとって非常に重要な存在であり、前述のように非常に難関な資格であるのに対して、その知名度は低いといえます。実際に、弁護士や会計士や税理士といった他の士業の方が接する機会が多く、業務内容や役割についても知られていることが多いでしょう。
社会で重要な役割を果たしているにも関わらず周囲からの理解が薄いと、やりがいや達成感が得にくいと感じる人も少なくありません。
知名度の低さゆえに、キャリアパスの選択肢や展望が不透明に感じられることが、「やめとけ」と言われる一因となっているのです。
近年、DX化の推進やAIの発達などにより、企業の労務管理や給与計算、社会保険手続きなどの業務が自動化されつつあります。そのため、社労士の仕事が無くなってしまうのではないかと、将来性に不安を抱く声が上がっています。
労働法規やコンプライアンス、企業の人事労務に関するアドバイス業務は今後も必要とされるため、業務の内容や専門性を深めれば今後もニーズの高い職種ではあるものの、キャリアへの不安が拭えず、「やめとけ」と言われてしまうようです。
社労士の将来性については、以下の記事でも詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
厚生労働省「令和4年賃金構造基本統計調査」によると社労士の平均年収は約496万円です。これは給与所得者の平均よりは高い数字であるものの、他の士業と比べると低めであるといえます。
このため、年収を重視する方にとっては社労士の仕事に魅力を感じにくいかもしれません。また、先述したように資格取得の難易度が高いことを踏まえて平均年収を鑑みた時に、「やめとけ」と言いたくなるのでしょう。
ただ、上記の数字はあくまで平均年収であり、キャリアアップすることで、1,000万円以上の高年収を実現することも可能です。社労士の年収については、以下の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
このように社労士は「やめとけ」と言われることが大きいものの、取得すれば様々なメリットがあるのも事実です。社労士試験の受験者数や合格者数が年々増加しているのも、そんなメリットが大きいと感じる方が多くいらっしゃるからでしょう。
ここでは、そんな社労士になるメリットを4つご紹介します。
知名度が低いとはいえ、社会的に重要な位置付けとされていることは他の士業と同じであり、社労士事務所や企業の労務職などで高いニーズがあります。もちろん資格を持っているからといって、必ず就職や転職に成功するわけではありませんが、キャリアの選択肢を広げたり、無資格者に比べての優位性を発揮することができるでしょう。
社労士資格を所持している人にしかできない仕事である独占業務が存在するのも、社労士を取得するメリットといえます。独占業務は労務を代行する際などに必要とされる仕事なので、その分ニーズも高いといえます。
具体的な独占業務の内容については、以下の記事をご覧ください。
ご紹介したように、独立に際してのリスクはあるものの、うまく軌道に乗せれば、雇われて働くよりも高年収を実現することも可能です。また年収の魅力だけでなく、経営者としてのキャリアを歩めるというのも魅力といえるでしょう。
社労士取得を目指すにあたって、労務や労働関係のさまざまな知識を身につけることができるのもメリットの一つです。その知識を仕事に還元することができるのはもちろんですが、もし全く関連の無い仕事をしているとしても、自身の働く環境の適法性を測ることができます。
そのため、違法性のある部分を指摘したり改善することによって、当人はもちろん働く全ての従業員の権利を守ることにも繋がるのです。
ご紹介したように社労士は試験難易度が高いため、向き不向きを踏まえて、目指すかどうかを検討するのがよいでしょう。ここでは社労士を取得するのに向いている人の特徴は以下の通りです。
1つずつ見ていきましょう。
社労士は比較的高年齢からのスタートが可能な職業のため、独立をして長期的に働きたいという方には向いていると言えます。他の士業(弁護士や公認会計士)と比較するとまだ資格の取得がしやすく、かつ一定数の需要があるため、上手く顧客をつけることができれば独立もしやすい職業となってます。ただし、独立はせず企業で長く勤めたいという方は、資格の取得を急ぐことをオススメします。
後程詳しく触れますが、社労士の業務には社会保険や労務関連の相談業務(コンサルティング)が含まれます。そのため、コミュニケーション能力は社労士にとって必須とも言うべきスキルの1つで、誰かとコミュニケーションを取ることが好きな方や、他人の課題を解決することにやりがいを感じられる方にとっては向いている職業と言えます。
冒頭の「やめとけ」の理由でも触れたように、社労士の主な業務内容は給与計算や帳簿作成などの地道な作業が多くなります。そのため、細かい数字を扱う作業や日々の地道な作業を苦に感じないという方にとっては天職と言えるかもしれません。
社労士にとって正義感や法律順守の精神は重要なポイントです。社労士は労働者の働く環境を守る職業ですので、社会に対しての貢献度合いの高い仕事です。そのため、社会的貢献性が高い仕事や労働環境などの課題を解決に向き合いたいという、正義感の強い方は社労士に向いていると言えます。
この中に当てはまる特徴がある方は、是非社労士を目指してみてください。
ここまでの内容で社労士を目指すメリットや「やめとけ」と言われる理由について説明しましたが、社労士への志望度合いに変化はあったでしょうか?もし、実際に社労士を目指そうと思われている場合、予め押さえておいて欲しい点をいくつかまとめましたので、1つずつ確認していきましょう。
先ほどもご説明したように、社労士は、資格を活かして社労士事務所などを独立開業することで収入アップが望めます。しかし、独立開業は高年収を目指せる可能性がある反面、全く稼げないリスクも伴います。開業には一定の初期投資が必要な上に、顧客を確保するための営業活動やマーケティングも自分で行う必要があり、初めの数年間は収入が安定しないケースが多く、経済的な不安を抱えることもあります。
社労士になる方は年収アップを目指して独立を望む方が多い一方で、このような資金や労力を投資しながら確実にリターンが返ってこないというリスクも一定数あるのだ、ということを予め理解しておくことが重要です。
「やめとけ」と言われる理由の中でも出てきたように、社労士の将来性についてはしっかりと理解した上で目指す必要があります。社労士の将来性についてですが、結論からお伝えすると、AIによって完全に代替されることは難しいと言えます。
社労士の業務の中には1号業務・2号業務・3号業務の3種類があり、1号業務と2号業務は申請書や帳簿作成が主な業務内容になります。そのため、これらはAIの発展と共に代替される可能性がありますが、3号業務は主に社会保険関連の相談業務(コンサルティング)であるため、専門的な知識と経験を必要とするコンサルティング業務はAIに代替されにくいと言えます。
また、1号業務・2号業務の中でも社労士のみが行える独占業務に関しては、技術的な問題ではなく、法律や制度の観点からAIに代替されない可能性も考えられます。
前述で社労士のニーズが高いとお伝えしましたが、社労士のキャリパスについてもどのような働き方ができるのかを押さえておきましょう。具体的には、社労士資格は以下のような職場で活かすことができます。
これらの職場について、詳しくは以下の記事に解説しておりますので、併せてご覧ください。
実は、社労士資格保有者向けの求人数はあまり多くないというデメリットがあります。特に小規模な企業では、社労士を労務専任で雇用する余裕がなく、社労士事務所など外部に業務を委託する場合がほとんどです。これにより、社労士の求人が少ないというのが現実です。
ただ、士業・管理部門特化で転職エージェントをしている当社ヒュープロでは、社労士資格保持者向けの求人を豊富に掲載しています。求人数やキャリアの選択肢に対し、決して不安に感じる必要は無いので、もし社労士資格を活かして転職をしたいというお考えがある場合は、是非一度ヒュープロへご相談ください。
専任のキャリアアドバイザーが、あなたのご希望に合った求人をお探しします。
言わずと知れたYahoo!知恵袋にも、「社労士はやめとけ」という意見に関する質問が挙がっています。いくつか具体例を見てみましょう。
20代前半の男性より、「社労士取得を目指しながら働いているものの、社労士事務所で働く方から『社労士は食えないからやめたほうがいいよ』と言われ、社労士の存在意義について悩んでいる」といった内容の投稿がされていました。
この投稿に対し、「実際、食っていけないからやめた方がいい」という回答が複数寄せられている一方で、「自分の思ったように生きるべき、目指したいなら目指してみてほしい」といった社労士の方の回答が、ベストアンサーとなっていました。
こちらは閲覧数が15,000件以上となっており、社会的な関心の高さが伺えます。
大学生が、「就職活動でのアピールポイントとして社労士の取得を検討しているが、ネガティブな情報を目にしたこともあるため、目指すべきか迷っている」という投稿をしています。
「就職活動で確実に有利になるので目指すべき」という意見がある一方で、「独立開業するつもりが無いのに取得するのはおすすめしない」とか「就活のアピールポイントにするには労力がかかり過ぎてしまう」などといった否定的な意見が多い印象です。
就職活動で活かすには難易度が高い、というイメージが大きいことが見受けられます。
40代で子育てをしながら総務として働く女性から、「一念発起して社労士の勉強をしようと考えているが、5か月後の試験を目指すべきか、来年まで勉強すべきか、そもそも受験しないべきか、意見が欲しい」といった内容の質問がありました。
この質問にはポジティブな回答が多く、「ぜひ目指すべき。ただ数ヶ月の勉強では難しいと思うので数年かかることを留意した方が良い」といった意見が寄せられていました。
このように、それぞれの質問に対して様々な意見が寄せられていることが、お分かりいただけるでしょう。
今回は、「社労士はやめとけ」と言われる理由について解説しました。社労士を取得するにあたっては、必ずしもメリットだけではないものの、決して「やめとけ」言われるほどのデメリットがあるわけではありません。
社労士の市場価値は知名度よりも断然高いといえますので、取得した上で就職や転職を目指すのはオススメといえます。
希望の就職先に入るための準備はしっかりしたいという方は、是非転職エージェントをご活用ください。当社ヒュープロは士業・管理部門に特化した転職エージェントであるため、社労士の就職や転職に関して、弊社ならではのサポートが可能です。ぜひご相談から、お待ちしております。