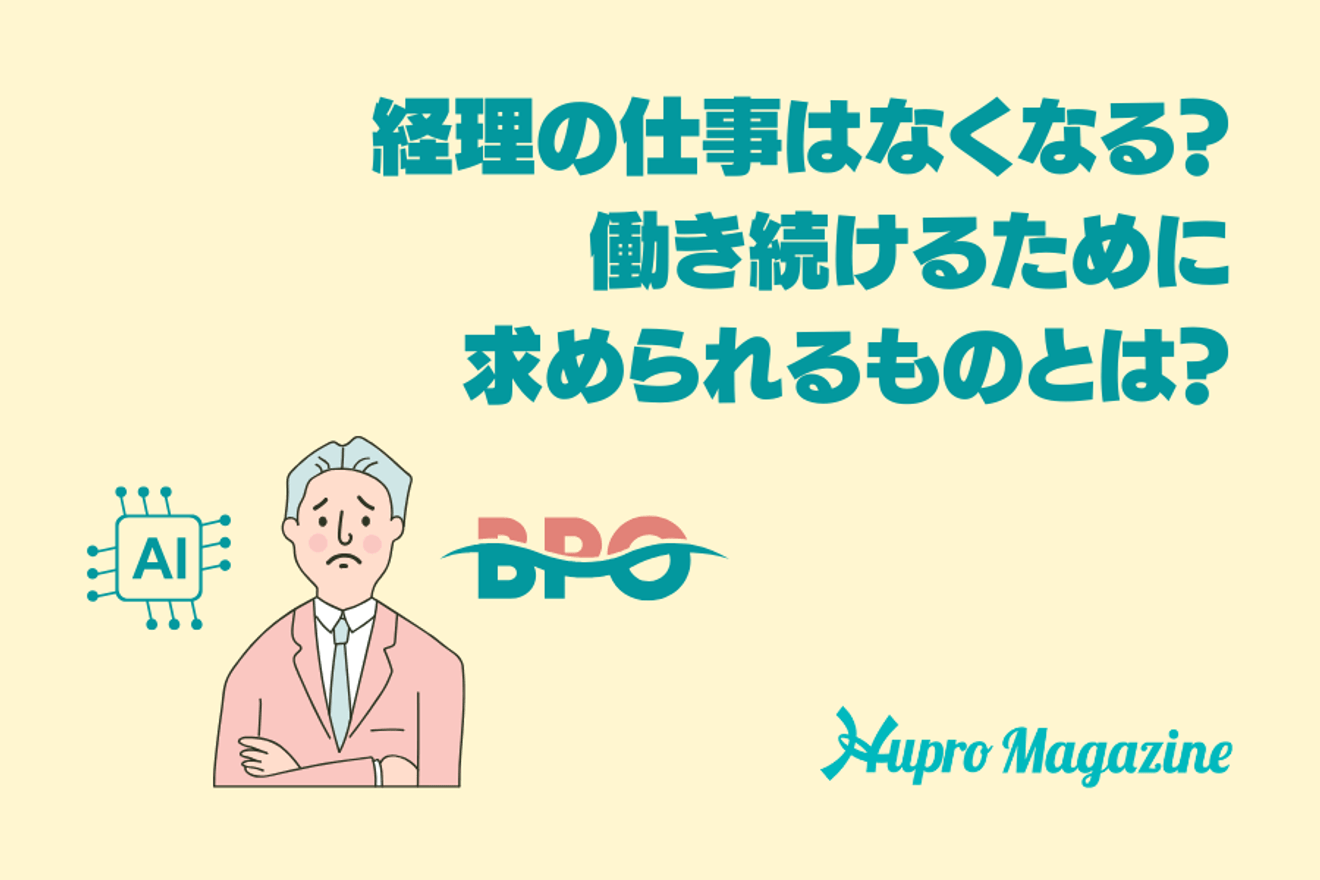
AIの台頭やRPAの進化や外部委託の増加により、あらゆるものが自動化されています。便利な世の中になる反面、将来人間の仕事がなくなると言われています。特に、この記事では、経理の仕事が本当になくなってしまうのか、また経理として働き続けるために何が必要なのか、解説していきます。
まずは経理がどんな仕事なのかについて解説します。
経理の仕事を一言で表すと、会社のお金全般の管理をすることです。大きく分けると日次業務・月次業務・年次業務の3つに分類でき、それぞれが以下のような業務を行っています。
| 日次業務 | 会社の毎日のお金の取引を記録・集計する |
| 月次業務 | 1か月間で発生したお金の流れを記録・管理する |
| 年次業務 | 1年間のお金の流れを資料としてまとめる |
会社における経理の重要性は高く、会社の意思決定をするための土台となるのはもちろん、会社の所有者である株主に対して企業活動の成果や状況を報告する役割や、一般市場における投資家の投資判断の基礎となる情報を提供する役割もあります。
同じく企業や組織のお金を扱う仕事として、経理以外に財務や会計があります。混在しがちですが、役割は明確に分かれています。
| 項目 | 財務 | 会計 | 経理 |
|---|---|---|---|
| 役割 | 資金の調達・運用 | 数値の記録・分析 | 日々のお金の処理 |
| 目的 | 会社の資金計画・管理 | 財務状況の見える化 | 正確な会計処理 |
| 主な業務 | 資金調達、投資、予算管理 | 財務諸表の作成、業績分析 | 仕訳入力、請求書処理、決算 |
| 時間軸 | 未来志向(資金計画) | 過去・現在の記録と分析 | 現在の取引処理 |
| 関係する資料 | 資金繰り表、投資計画書 | 財務諸表、損益計算書 | 伝票、請求書、領収書 |
| 関係者 | 経営者、投資家、金融機関 | 経営者、株主、税務当局 | 社員、取引先、税理士 |
経理の仕事内容について、詳しくは以下の記事をご参照ください。
上述のように企業で大きな役割を持っているにも関わらず、経理の仕事が「なくなる」と言われているのは、なぜでしょうか?その理由について解説します。
最も大きい要素として、AIやRPAの普及があります。
AIは「人工知能」とも呼ばれ、業務の流れを自動的に学んで仕事をこなしていくものです。決まった業務をこなすことはできますが、トラブルが起きた際に臨機応変に対応をするものや、ある基準を満たしているかどうかといったような業務は苦手とされています。
一方、RPAとは「ロボティック・プロセス・オートメーション」と呼ばれ、AIのように学んでいくというよりも、同じ業務を効率化して行うロボットです。プログラムを入力すれば、ミスなくその通りに動き、365日24時間作動し続けます。経理の業務でいえば、請求書を発行することや事務処理の作業はRPAに任せることができるのです。
このようなAIによる業務効率化やRPAによる業務自動化は、企業の経費節減に大きく貢献します。ある程度の導入費用は掛かるかもしれませんが、中長期的な視点では減らせる人件費の方が多くなっていくからです。
そのため、AIやRPAに経理職の人が取って代わられる可能性を指摘する声が挙がってきているのです。
日本社会全体でDX化の流れが進んでいるのも要因の一つです。DX化とは、データやデジタル技術の活用を進めていくことを指します。
DX化によって、経理においては、紙で管理していた企業の資産の流れ(領収書や請求書、発注書など)をデータで管理するペーパーレス化が進みます。
ペーパーレス化することで、人による業務量の低減だけでなく、ミスや紛失のリスクをなくすことにも繋がります。その一方で、手を動かして計算したり紙の保管や管理をする経理担当者は必要なくなります。
そのため、DX化によるペーパーレス化が経理の仕事がなくなる要因の一つとされているのです。
AIやRPA・ペーパーレス化とは方向性が異なりますが、BPOの活用増加も正社員雇用の経理職にとっては痛手となるでしょう。
BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)とは、企業が自社の業務プロセスの一部を外部の専門業者に委託することを指します。BPOは、コスト削減や業務の効率化を目的として、特定の業務(例えば経理、カスタマーサポート、人事、ITサポートなど)を外部に委託する手法です。
BPOの主な目的には以下のようなものがあります。
BPOは、特に経理や人事、カスタマーサポートなどの業務で広く活用されています。そのため、単純作業や外部に依頼しても問題ない業務は、AIなど関係なく、安く済ませられるようになってきています。
このようなAIやRPA・ペーパーレス化の話をすると、経理の仕事が本当に無くなってしまうように思われるかも知れません。
しかし、経理の仕事の将来性は決して暗いものではありません。なぜなら、経理の全ての仕事が人以外に取って代わられるとは考えにくいからです。
ただし当然ではありますが、一部の業務は自動化されてしまうことでしょう。そこで次の章では、経理業務のうち、将来なくなると考えられる業務と、そうでない業務について解説します。
将来的になくなると考えられる業務の共通点として、一定のルールに基づいた単調な作業であることが挙げられます。具体的には、以下のような業務が挙げられます。
仕訳業務は経理の中でも最も基礎的な業務ですが、その業務量はかなり多いため、AIに処理してもらうことで大幅な業務効率向上が見込めます。そのため、かなり早い段階で仕訳を人が行わなければならない企業は少なくなってくると予測されます。
一方、税務申告や決算業務については経理の中でも高度な仕事であるものの、ルールさえ認識させることができればAIやRPAによる実施が可能になると考えられています。
このように単調であることに加え、何かしらのデータを作成したり処理する業務が無くなる可能性が高いです。
従来、仕訳業務は手動で行うことが多かったですが、現在では会計ソフトウェアやAI(人工知能)を活用することで、自動で仕訳を行うことができるようになっています。例えば、取引データを入力すると、AIが自動的に仕訳の勘定科目を選定し、仕訳伝票を作成するシステムがあります。この結果、経理担当者は仕訳を一から手動で行う必要がなくなり、効率化されます。
経費精算のプロセスもデジタル化が進んでおり、経費精算ソフトやクラウドシステムを使用して、経費申請から承認、支払いまでをオンラインで完結させることができます。スマートフォンで領収書を撮影し、システムに自動的に反映させることができ、経理担当者の確認作業も簡略化されます。これにより、紙の伝票や領収書を使わず、ペーパーレスで管理ができるようになり、従来の手作業が大幅に減少します。
税務申告も自動化が進んでおり、会計ソフトやクラウド型税務ソフトが税務計算を自動で行うようになっています。税制の変更に対応した自動更新が行われるため、税理士や経理担当者が手作業で申告書を作成する必要が少なくなり、申告作業はソフトウェアに任せることができるようになります。また、e-Tax(電子申告システム)を利用すれば、申告自体もオンラインで完結するため、紙の申告書を使う必要がなくなります。
決算書作成も会計ソフトやERPシステムによって効率化されています。これらのシステムは、仕訳データや取引データを元に、必要な決算書(損益計算書や貸借対照表など)を自動で作成する機能を提供しています。決算書を作成するために手作業で集計したり、計算を行ったりする必要がなくなり、データを入力するだけで、必要な書類が自動で作成されるようになります。
一方で将来的になくならない業務には、データや資料から思考し、何かを判断するような業務が該当します。
特に、データを分析しながら経営者とコミュニケーションをとって管理会計を処理する場合や、会社にとって有利となるように会計処理を議論するといったような業務は、人にしかできない仕事だといえます。
また、財務状況を踏まえた上でどのような資金繰りをするべきかなどといった、様々な要素を複雑に組み合わせて判断する業務については、今後も人が行うべきものでしょう。
財務分析は、企業の経営戦略に直結する重要な業務です。データをもとにして企業の経営状態や将来の予測を行うためには、単なる数字の処理だけでなく、経済環境や業界の動向を考慮する必要があります。AIや自動化ツールは数値の整理や一部の分析作業を支援することができますが、人間の判断力や業界に対する知識が重要です。財務分析の結果を経営陣にわかりやすく伝え、戦略的な意思決定をサポートするためには、人間の知識や経験が欠かせません。
監査対応は、外部監査法人や税務署とのやり取りを含む重要な業務です。監査人が確認するのは単なる帳簿データだけでなく、企業の内部統制や取引の背後にある意図、経営陣の判断なども含まれます。監査対応には透明性と正確性が求められ、また監査人からの質問やリクエストに対するコミュニケーションも重要です。監査対応は単なるデータ提供では済まず、説明や交渉が必要であり、これらは高度な判断力と人的な対応能力が求められるため、完全に自動化することは難しいです。
業務課題の解決は、企業の状況に応じた柔軟な対応が必要です。経理部門が直面する課題は、システム的な問題から、人員やプロセスに関する問題まで多岐にわたります。自動化ツールや外部サービスがいくら効率化を進めても、特定の課題に対する 創造的な解決策 や 問題の根本原因の分析 は人間の知識や判断に依存します。経営陣や他部門との連携を通じて解決策を導く必要があり、そのためには 柔軟な思考 と 対応能力 が求められます。
経理部門は他部門との連携が欠かせません。例えば、営業部門や人事部門との連絡を通じて、予算や支出、業績に関する情報を共有し、改善策を講じることが求められます。人的なやり取りや調整作業、そして時には 交渉 が必要です。これらの業務は、単なるデータの処理だけではなく、人間の感情や状況の変化に対応する柔軟性が重要であり、自動化ツールでは補えない部分です。
経理の仕事に今後も携わるつもりであれば、AIやRPAができない分野のスキルアップをすることが求められます。
まず、M&Aや管理会計といった実務による経験や専門的な知識がさらに高く求められるようになるでしょう。このような専門的な業務は経験できる企業が限られている分、身に付けておくと活躍しやすくなるでしょう。
さらに、意思決定を求められる時に正しく先を見越して判断する能力、また財務諸表と経営者の意志に基づいて適切なアドバイスを提案する能力についても、財務担当として活躍するためには必要になってくるでしょう。
また、近年では日本企業のグローバル化や外資系企業の日本進出が活発になっています。そのような企業の経理職には、高い英語力が求められるため、英語力を武器に働き続けるというのも有効な選択肢といえます。
最後に、DX化やAI・RPAの導入はもちろん、その運用にあたってもITスキルは欠かせません。そのため、ITスキルを有した経理担当者は現時点でもニーズが高く、今後はさらに高まっていくでしょう。
今回は、経理の仕事が将来的に無なくなってしまうのかについて解説しました。
経理業務の一部は自動化や外部委託が進む中で、なくなるものあるでしょう。ただ、経理として働き続けるために重要なのは、それでも残り続ける仕事のスキルを今のうちからつけておくこと、そしてAIやRPAと共存してうまく仕事を進められるようにしておくことです。
「仕事を奪われる」というイメージによって、AIやRPAを毛嫌いする方もいらっしゃるかもしれませんが、社会や会社には大きなメリットを与えるツールです。それらが導入されたら、むしろ活用することで自身の業務の最適化を進めるのがよいでしょう。
スキルが高くITを活用できる経理担当者になればニーズも高く、年収や働き方などの労働条件を向上させることにも繋がりやすいので、決して損することはないのです。
経理職として生き残るための戦略としては、ただの数字の処理に留まらず、会社や代表の意向を把握した上での戦略的な思考や、データ分析力などを強化して、ビジネス全体に貢献できるポジショニングをとっておくことがポイントです。