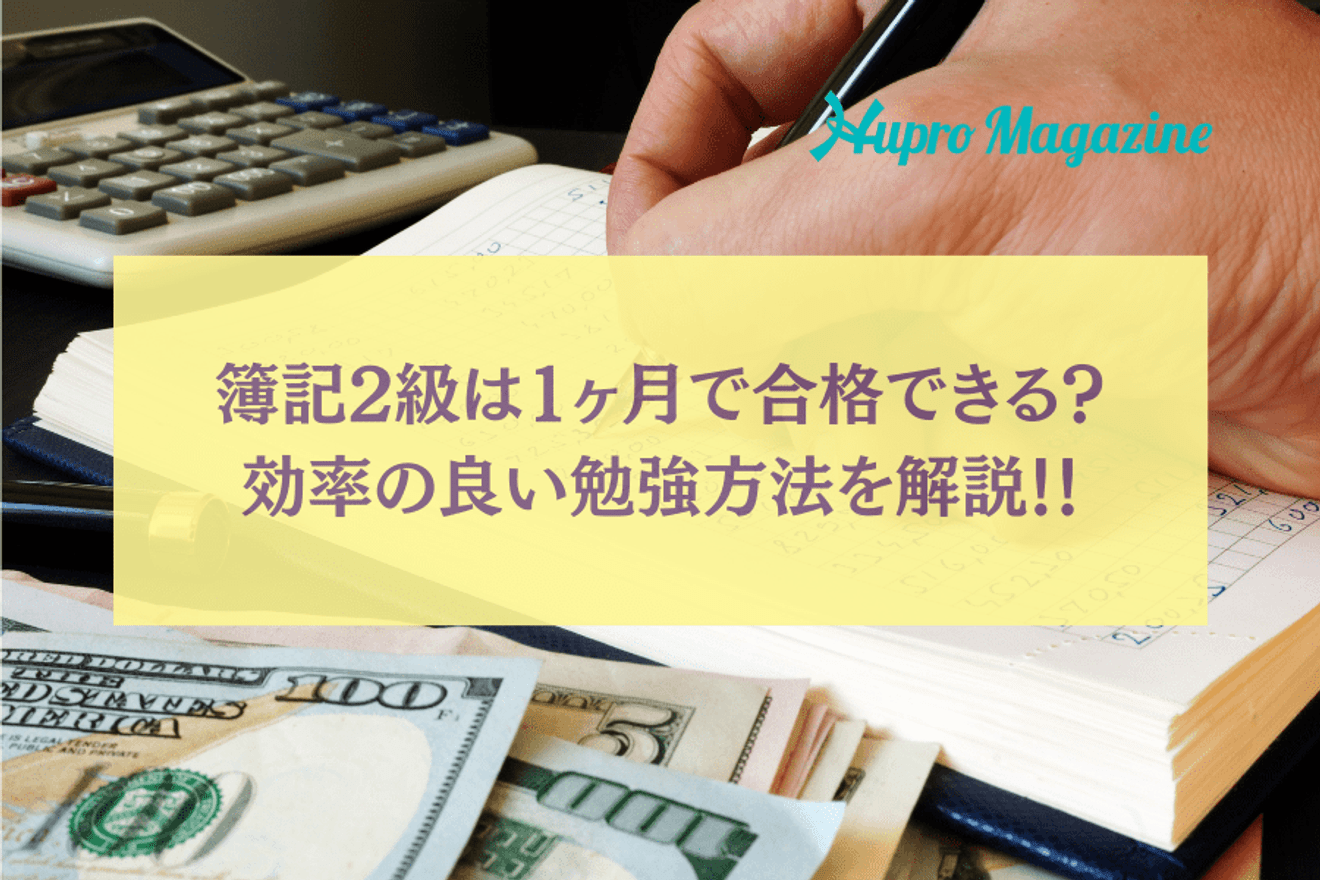
簿記2級試験は、1ヶ月で合格することも可能です。ただし、試験対策講座や専門学校の利用は難しく、独学で計画的に勉強する必要があります。
この記事では、簿記2級に1ヶ月で合格するための勉強時間の目安と、合格するためのポイントについて解説していきます。
結論からお伝えすると、スケジュール管理をしっかりと行って学習を進めることができれば1ヶ月で簿記2級に合格することは可能です。
ただし、1ヶ月で合格することができるといっても、トータルの勉強時間が短くて済むわけではありません。あくまでも、1ヶ月という短期間に集中して勉強すれば合格できるということです。一般的には数ヶ月かけて取り組むような資格であることは予め理解しておきましょう。
また、後述でも触れますが、試験対策講座や専門学校では「1ヶ月の短期合格コース」などは設けられていないため、1ヶ月での合格を目指す場合は基本的に独学での挑戦になることも頭に入れておいてください。
その場合、参考書や問題集も自身で探す必要があるので、この後の部分で教材の選び方や勉強の進め方についてもお伝えします。
一般的に、簿記2級に合格するための勉強時間は、独学で350~500時間、資格スクールなどを利用して250~350時間程度と言われています。つまり、毎日8~12時間勉強すれば、1ヶ月で簿記2級の知識を習得することが可能だということになります。前述でもお伝えした通り、基本的には取得までに数ヶ月かかる資格ですので、1ヶ月で取得しようと思うと、1日あたりの勉強時間を十分に確保できる環境にある必要があります。
もしかすると、「これよりも圧倒的に短い勉強時間で合格した」という話を周囲の噂や合格者の体験談などで耳にすることがあるかもしれません。しかし、それはあくまでもその人の場合の話であって、合格の確実性やその後の知識の定着度合いを鑑みると、やはり250~350時間は勉強時間を確保すべきではあるので、より確実に合格したい方は参考にしてみてください。
1ヶ月の短期決戦になるため、隙間時間も無駄なく利用して、毎日欠かさずコツコツとやることが重要です。頑張って勉強したのに間に合わなかった、ということにならないように、計画を立てて勉強しましょう。
簿記2級の合格に必要な勉強時間の目安は以下の通りです。
商業簿記と工業簿記の順番はどちらから始めても問題ないですが、記憶が定着しやすいように同時進行で進めていくのが良いでしょう。
・商業簿記の基礎 :70~100時間
・工業簿記の基礎 :50~70時間
・商業簿記・工業簿記の応用 :70~100時間
・過去問 :60~80時間
前述の通り、大前提として少なくとも3~4ヶ月で計画的に勉強を進めての受験がオススメではありますが、「どうしても1ヶ月で合格したい」という方は、最後の1週間は全て演習に時間を充てられるように、少なくとも最初の3週間で全範囲の学習を終えられるようにスケジュールを立てましょう。
基本的には1週間で1科目終わらせるようなスケジュールで進めると、最終週は演習に時間を割くことができるでしょう。
また、既に簿記3級を持っている方でも合格してから時間が経っている場合は、簿記2級の勉強を始める前に、一度3級の内容をおさらいしておきましょう。
資格専門学校の通学講座では、資格専門学校が監修した参考書や問題集が与えられます。しかし、簿記2級を1ヶ月で合格するためには、最適な参考書や問題集を自身で選定する必要があります。
参考書には様々なものがありますが、カラーや表でわかりやすく解説されている参考書が覚えやすい、漫画のようなデザインや挿絵が入ったものが好きである、持ち歩き用に軽量なものが良い、全ての情報が一冊で網羅出来るような情報量の多いものが良いなど、自身のこれまでの学習方法や性格を振り返り、合ったものを購入するようにしましょう。
問題集も同様に、見直しがしやすいようにチェックを付す欄があるものにしたり、理解して覚えるための解説が豊富なもの等、自分の学習方法や性格に合ったものが良いでしょう。
自身に合ったものが分からない人は、参考書であれば本の厚みが薄いもの、問題集は出題頻度が高いものを優先的に学習できるもの、勉強方法はとにかく問題集をこなすことを意識してみてください。
理由としては、簿記2級の試験は算数的な要素が強いため、出題内容に関する理解が乏しくとも、問題と問題に対する回答方法のパターンさえ掴めれば、合格できる可能性があるからです。
先ほどの内容にも少し重複しますが、1ヶ月での簿記2級合格に向けた勉強法をご紹介します。
簿記3級を持っていない状態から2級の合格を目指す場合、上記の内容に簿記3級の勉強が加わります。ただでさえ時間が限られているため、できるだけここで時間を使いたくないというのが本音です。とはいえ、基礎がない状態で応用へ進んでも、理解が追い付かず逆に効率が悪くなってしまう恐れがあります。
そのため、薄いもので問題ないのでテキストを1冊用意し、1~2周する中で不明点をなくすようにしましょう。簿記2級で応用になるため、ここでは応用の問題演習は一旦行わず、とにかく基礎を固めるようにしましょう。
商業簿記は有価証券や財務諸表、連結会計のように各項目に分かれているため、工業簿記よりも勉強時間が必要になります。どの項目から勉強するかの優先順位は特にありませんが、基本的にはテキストを前から順番に進めていくのが良いでしょう。
最終週に演習の時間を取る前提とは言え、時間的な余裕がないためインプットをしてからアウトプットではなく、実際に問題を解きながら理解を深めていく方法がおすすめです。これにより問題の傾向や回答の仕方などの実践的な知識も同時に着けることができます。
こちらも商業簿記と同じくではありますが、特に工業簿記は点数を取りに行きたい範囲のため、問題演習を中心に勉強を進めてください。コツを掴めば点数が取りやすい範囲ですので、極力満点を目指しましょう。
結局は問題にどれだけ慣れているかがものを言うので、必ず十分に時間を使って問題演習に取り組んでください。ここで注意していただきたいのが、解きっぱなしにしないことです。
受験勉強をした経験がある方は納得していただきやすいかと思いますが、時間が限られているからとにかくたくさんの問題に触れようとして復習をおろそかにしてしまいがち
簿記2級知識の習得にかかる勉強時間は「1日の勉強時間を十分に確保できるかどうか」、「既に簿記3級を持っているかどうか」など前提条件によって異なります。以下でそれぞれの違いを見てみましょう。
簿記3級の合格に必要な勉強時間は50~100時間程 と言われています。そのため、簿記3級を既に持っている状態からの受験であれば、50時間程度は勉強時間を短縮することができます。簿記3級は最初の基礎になる部分のため、簿記3級を持っていない状態から簿記2級の取得をいきなり目指す場合でも、結局は簿記3級の範囲を一通りは学習することになります。
社会人のように1日あたりの試験勉強にかけられる時間が限られている場合、1ヶ月での合格は非常にハードルの高い挑戦になります。大抵の方が、勉強時間を確保できるとしても就業前後と休日に限られるため、1日あたりの勉強時間は平日で2~3時間、休日で10~15時間程度となるでしょう。そうなると、1ヶ月で最低限の知識を身に着けた状態でイチかバチかの受験をするか、3~4ヶ月かけて十分に勉強した上での受験となります。
簿記2級の難易度を解説するにあたり、難易度を表す数値として最も分かりやすいのが合格率です。簿記2級の合格率は、主催をする商工会議所により公表をされています。近年の試験の合格率は、平均すると約20%となっています。
ただ、簿記2級の合格率は安定しておらず、低い回では8.6%、高い回では47.5%といったように、合格率に大きな差があります。
合格率が低い回に当たってしまった場合、勉強時間が1ヶ月だと、合格することが難しいかもしれません。
・第166回試験(2024年2月25日実施)
受験者数10,814人/実受験者8,728人/合格者数1,356名/合格率8.6%
・第165回試験(2023年11月19日実施)
受験者数数11,572名/実受験者数9,511人/合格者数1,133人/合格率11.9%
・第164回試験(2023年6月11日実施)
受験者数10,618人/実受験者数8,454人/合格者数1,788人/合格率21.1%
・第163回試験(2023年2月26日実施)
受験者数15,103人/実受験者数12,033人/合格者数2,983人/合格率24.8%
・第162回試験(2022年11月20日実施)
受験者数19,141人/実受験者数15,570人/合格者数3,257人/合格率20.9%
簿記2級の試験を受けるつもりで受験申し込みをしたものの、思うように勉強時間がとれないまま気付けば試験日まで残り1ヶ月程度しか無い、という状況はよくあることだと思います。
この場合、残り1ヶ月程度の時点で、大手の資格専門学校の通学講座では既に直前対策講座等の期間に入っているため、通学講座への合流は難しいといえるでしょう。
簿記2級の受験対策として、様々な資格専門学校が講座を開いています。その一例として、大手の資格専門学校の通学講座では、簿記3級合格者向けの2級試験対策講座が、3〜8カ月で知識を習得できるように学習計画がなされています。
ただ専門学校や通信講座を利用することで、トータルの勉強時間を短縮することは可能です。特に通信講座では講座を好きな時間に視聴できるので、1ヶ月に集中して講義視聴を進めることができます。問題集などでの演習を挟みながら理解を深めていきましょう。
【関連リンク】
簿記2級の合格を目指すなら、スタディングの簿記講座がオススメです。ぜひご検討ください!
簿記講座の詳細はこちら
試験日までの残日数が1ヶ月程度しかないので、1ヶ月で簿記2級を目指す人もいるでしょう。簿記2級は年に3回しか実施されていないので、試験日と学習ペースが合わないこともあります。
ネット試験なら、試験日程の調整がしやすいです。無理に1ヶ月で合格を目指す必要はありません。ほぼいつでも試験が開催されているので、自分のペースで勉強ができ、都合の良いタイミングで受験できます。
《関連記事》

簿記2級は、有名な資格ではありますが民間資格です。したがって専門家としての独占業務や開業はできないものの、民間企業での支持は高い傾向にあります。また活かせる仕事は「経理」や「会計事務所」などが代表的にあげられます。他にも銀行、証券会社、保険会社の営業やコンサルティング会社など、幅広く活躍できます。ここでは経理職と会計事務所の仕事内容に、触れていきます。
経理職とは、一言でいうと企業や組織においてお金の取引や流れを記録する仕事です。
商品の仕入れに発生するお金や、通勤にかかる費用などその企業に関わる全ての金銭のやり取りを記録し、月次決算や年次決算などのタイミングでそれらをまとめ、収支を明確化します。
経営陣は経理がまとめたこれらの資料やデータを参照しながら方針や指針を決めることになりますので、正確性が非常に重要です。
日々のお金の流れを集計するための仕訳や記帳など、経理における基礎的なスキルは簿記2級の習得によって身に着けることができるので、未経験から働いたとしてもある程度スムーズに業務にあたることができます。
また経理職で豊富な経験を積んだ方の中には、企業のCFOクラスとしてIPO達成に導くための対応を任されることもあるように、ハイキャリアも目指しやすい職種といえます。
業務内容という面では、会計事務所も経理職と同じこともやっていますが、経理職が所属企業のお金を管理するのに対して、会計事務所はクライアントである法人や個人の業務を代行しているという部分に大きな違いがあります。
ただし簿記2級の知識を活用できるという面では、相違ありません。
また、会計事務所で働いていると、税理士資格に必要な知識が実務を通じて学べますので、会計・税務の知識を極めて税理士資格を取るというプランも見出すことができます。
簿記2級を活かせるオススメの職場として、Hana税理士法人/株式会社H Smartをご紹介します!
Hana税理士法人は東京オフィス・静岡オフィスを展開しており、「関わる人すべてを笑顔に」をミッションとしている税理士法人です。
会計税務顧問、バックオフィスサポート、IPO・資金調達支援はもちろん、クラウド会計ツールをはじめとしたITツールを駆使して、会計士事務所の枠にとらわれないサポートをクライアント様に提供しています。
Hana税理士法人は、社内のプロジェクトに携わることで、ベンチャー事業会社での事業成長や組織作りを、代表と共に経営者目線で行うことができます。そのため、「ベンチャー・スタートアップ企業の会計・税務業務を、様々なクラウドツールを通じて支援したい!」という方や、創業期の税理士法人で立ち上げメンバーとして活躍したい方が働くのに、特にオススメの職場です。
また、繁忙期を除き残業時間はほとんどないことや、フレックス制度やリモートワーク制度など様々な働き方を積極的に取り入れていることなどから、働きやすい環境であるといえます。
Hana税理士法人/株式会社H Smartについて、詳しい情報を確認されたい方は、以下より事務所様のサイトをご覧ください。
簿記2級は会計や経理の基礎を熟知していることがどの企業からも認められる資格です。したがって経理や会計系などの管理職への転職がおすすめです。銀行や証券、保険会社系は営業やコンサルティングの自信のある方へおすすめできます。
また会計事務所や経理職で転職するなら業界知識が豊富なエージェントから詳しく情報提供してもらえるヒュープロがおすすめ!
ヒュープロは士業・管理職のエージェントの中で求人数が一番多いので幅広い選択肢から自分にあった求人が選べます。また面接の日程調整、書類の添削、条件交渉など全て無料で行ってくれます。
今回は1ヶ月での簿記2級合格は可能なのかという点に焦点を当ててご説明しました。
結論としては、簿記2級を1ヶ月で合格することは不可能ではないです。しかし、簿記2級に1ヶ月の勉強時間で試験に臨むということは、受験生の中では非常に短い勉強期間となるため、かなりの努力と集中力が必要となります。時間に余裕がある方はしっかりと時間をかけて十分な準備をした上で臨んでほしいところではありますが、短期決戦で決めたいという方は後悔の無いように、今回ご紹介したポイントを意識して臨んでみてください!
《関連記事》