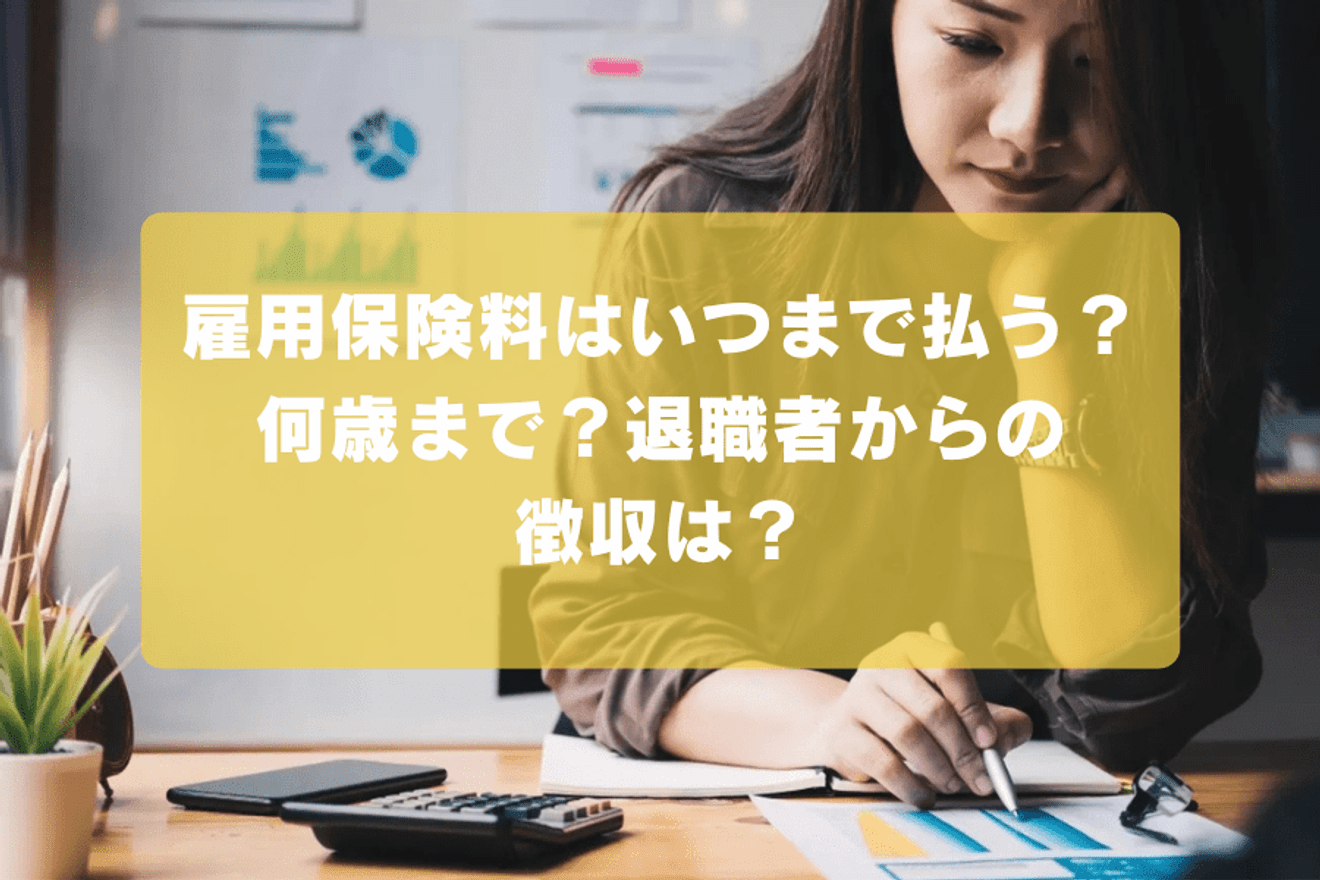
雇用保険は、失業したときや教育訓練を受けるとき等に給付金を受け取れる重要な制度。
しかし雇用保険料を支払う必要があるため、「雇用保険料をいつまで払うのか」と疑問に感じるかもしれません。
今回は雇用保険料をいつまで払うのかについて、雇用保険の概要や法改正の内容を踏まえて解説していきます。

雇用保険料の支払いは、雇用保険に加入していて賃金が発生している限り必要があります。
この理由について2つの視点で確認しましょう。
「いつまで」を「何歳まで」と言い換える場合には、年齢制限がないため、何歳であっても雇用保険の資格を喪失するまで払う必要があります。
年齢制限がないという点については「65歳まででは?」と疑問に感じる方がいるかもしれませんが、法改正がおこなわれていますので詳細を後述します。
「いつまで」を「どの月まで」と言い換える場合、健康保険料や厚生年金保険料のように翌月徴収(納付)するという仕組みはないため、労働の対価として賃金(賞与含む)を受け取る場合にはその都度払うことになります。
たとえば労務担当者が、退職する方の雇用保険料を徴収する際には「最終給与支払日まで」(あるいは最終賞与支払日)と考えておけばよいでしょう。
給与締切日によっては退職日より後に最終給与が発生する場合もありますが、「もう退職したのだから雇用保険料は徴収しなくてよい」とはなりませんので注意が必要です。
雇用保険は「1週間の所定労働時間が20時間以上」かつ「31日以上引き続き雇用されると見込まれる」労働者に対して加入が義務づけられているものです。
本人の希望や会社の意向は関係ありませんし、労働者を1人でも雇用する事業所はすべて適用事業となるため、2つの条件を満たせば必ず加入しなくてはなりません。
雇用形態も関係ないため、正社員はもちろん、パートタイムやアルバイト、派遣社員等であっても条件を満たせば加入します。
ただし学生については原則として被保険者となりません。例外的に、卒業前に就職して卒業後も同じ事業所に勤務する予定の者など、一定の条件を満たすと学生でも加入できます。
出典:雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!厚生労働省
労働契約の変更等で、雇用保険の加入条件を満たさなくなる場合があります。このときは原則として被保険者としての資格を喪失することになり、それ以降の雇用保険料は払う必要がありません。
ただし所定労働時間の変更が一時的なものである場合には、資格喪失の手続は必要ないとされています。
雇用保険料は、毎月の賃金総額に保険料率をかけて算出します。ここでいう賃金総額とは社会保険料や税金等を控除する前の、会社が労働者に支払うすべてのものを指します。
ただし災害見舞金や傷病手当金等、一部のものは雇用保険料の算出における賃金に含まれません。
保険料率は「一般の事業」「農林水産・清酒製造の事業」「建設の事業」ごとに定められており、年度によって変わる可能性があります。
労働者と事業主がそれぞれ保険料を負担しますが、社会保険料のように労使折半ではなく、事業主の負担割合が多いのが雇用保険料の特徴です。
出典:雇用保険料率について/厚生労働省
65歳以上の方の雇用保険については近年法改正がおこなわれていますので、概要と流れを説明します。
平成28年12月31日までは、65歳以上の方は雇用保険の適用除外でした。例外的に、65歳に達した日の前日から引き続き65歳に達した日以降も雇用される場合は「高年齢継続被保険者」として雇用保険に加入し、雇用保険料は免除されていました。
しかし法改正により、平成29年1月1日から65歳以上の方も雇用保険の適用対象となりました。「高年齢継続被保険者」は廃止され、65歳以上で雇用保険の加入要件を満たす方はすべて「高年齢被保険者」に統合されています。
高年齢被保険者が失業した場合には、退職前の1年間に通算6ヶ月以上の被保険者期間があり、ハローワークで失業認定されると、失業給付を受け取ることができます。「高年齢求職者給付金」という一時金で、年金との併給も可能です。
関連記事:【雇用保険の年齢制限撤廃】加入条件が変わり65歳以上も対象
高年齢被保険者の雇用保険料については、平成29年1月1日から令和2年3月31日までは、被保険者と事業主負担分がともに免除されていました。前述した法改正にともなう経過措置です。
令和2年4月1日からは高年齢被保険者の保険料は免除されません。したがって、すべての雇用保険の被保険者は、令和2年4月1日以降に賃金を受け取る場合には雇用保険料を払う必要があります。
労務担当者としても、高年齢被保険者の保険料を徴収し忘れないように注意が必要です。また労働者のほうから「今までは保険料が引かれていなかったのに突然引かれるようになった」と相談を受ける可能性もあります。
そのため法改正と経過措置の概要を分かりやすく説明できるようにしておきましょう。
※出典:雇用保険被保険者を雇用する事業主雇用保険被保険者の皆様へ/厚生労働省
雇用保険は会社に雇用され、要件を満たす限りは加入しているものです。賃金が発生する都度、雇用保険料を払うことになりますので、労働者、労務担当者ともに留意しましょう。
とくに65歳以上の方の雇用保険料については法改正がおこなわれています。令和2年4月1日からは保険料の免除も終了となりますので確実に覚えておきましょう。