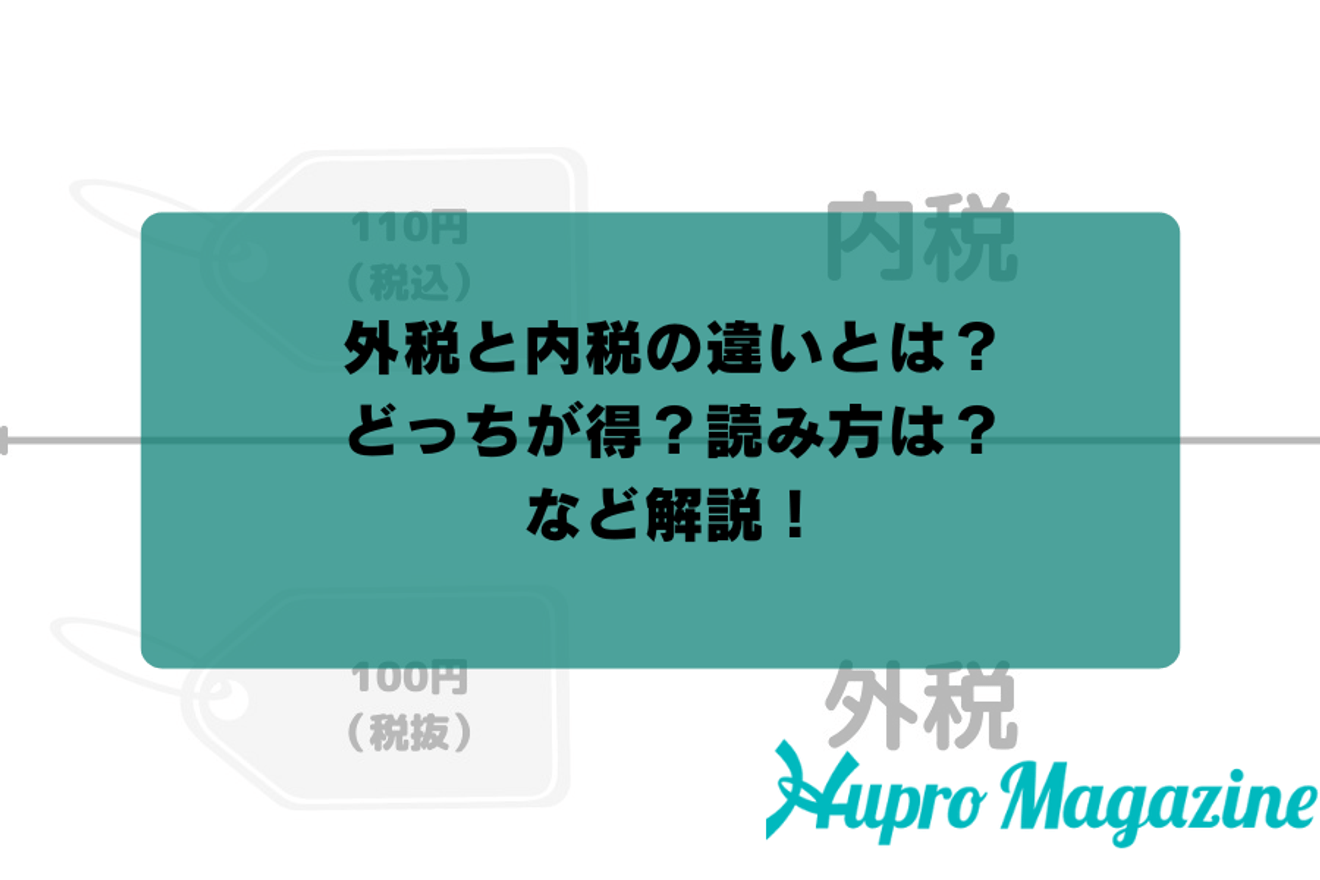
1989年から消費税が課税されるようになりました。当初は3%でしたが、現在は10%です。
課税率、課税対象に変動が起きやすい消費税ですが、表示に関しても内税と外税という種類があります。
なじみが深い、「内税」「外税」といったワードですが、今回は、実際のところの本当の意味や違いなどをご説明していきます。

この項目では、内税と外税の違いについて、説明していきます。まずは、内税からご説明しましょう。
内税とは、商品本体の価格に消費税分の金額をあらかじめ含めておく価格表示の方式です。読み方は”うちぜい”です。
要するに、消費税を含んだ価格ということになります。日本では、商品やサービスに消費税が課税されます。1989年からこの制度が導入されています。
「税込み」となると聞きなれている方も多いのではないでしょうか。この内税は、総額表示とも呼ばれています。平成16年4月からは、この総額表示が義務付けられています。商品価格には、必ず税込み価格を提示することとなっています。
外税とは消費税分を商品の価格表示に含めず、売買の際に消費税分の金額を上乗せする方式です。読み方は”そとぜい”です。」989年から消費税が課税されるようになりました。当初は3%でしたが、現在は10%です。課税率、課税対象に変動が起きやすい消費税ですが、表示に関しても内税と外税という種類があります。なじみが深い、「内税」「外税」といったワードですが、今回は、実際のところの本当の意味や違いなどをご説明していきます。
この項目では、内税と外税の違いについて、説明していきます。まずは、内税からご説明しましょう。
内税とは、商品本体の価格に消費税分の金額をあらかじめ含めておく価格表示の方式です。読み方は”うちぜい”です。
要するに、消費税を含んだ価格ということになります。日本では、商品やサービスに消費税が課税されます。1989年からこの制度が導入されています。
「税込み」となると聞きなれている方も多いのではないでしょうか。この内税は、総額表示とも呼ばれています。平成16年4月からは、この総額表示が義務付けられています。商品価格には、必ず税込み価格を提示することとなっています。
外税とは消費税分を商品の価格表示に含めず、売買の際に消費税分の金額を上乗せする方式です。読み方は”そとぜい”です。
税抜き価格、税別と言われることもあります。表示価格は、税込みの金額ではなく、税抜きとなっていて、購入する時に税を上乗せして支払うということです。

先ほど、内税のところでご説明していますが、平成16年度から総額表示が義務付けさていて、法律上税込みで表示しなければいけないのですが、消費税というのは変動があります。
課税率が変わりますよね。そうなってくると販売する側に、値札の付け替え、広告表示の変更など様々な負担がかかってきます。そのことで消費者の購買活動に影響がないように、特別に外税表示を認められているケースもあります。
※価格表示方法で、内税と外税の違いをおさらい
内税と外税では、支払い時に金額が変わってきます。
内税は、提示価格通り、外税は、支払い時に提示価格に10%課税された額を支払うことになります。内税で表示してもらうほうが、レジであたふたせずに済みそうですね。
まず、外税が認められるケースからご説明していきます。
総額表示は法律により義務付けされているとお話しています。しかし、実際に店頭やネット通販などでも、外税表示は多く見かけます。
これは、総額表示しなくてもいいケースがありますともお話しました。どういった場合に、総額表示をしなくてもいいのでしょうか。
これも先述しているのですが、消費税の課税率は変動がありますので、販売者側の負担を得減らすという意味でも、表示価格に税抜きであることを明記しておく、そして、お店などのわかりやすいところに、「当店の表示価格はすべて税抜きです」などのコピーを掲示しておくと総額表示をしなくてもよくなります。
など、よく見かける表示法です。
商品ひとつひとつにこの値札をつけておいて、店頭のわかりやすいとことに外税価格であることを掲示しておく必要があります。
この表示方法は、2021年3月31日までの期限付きですが、消費者が混乱しないように表示できるならば、税別でも提示できることが可能です。
たまに見かけますが、レジのところに小さく「当店は税抜きです」というお店もありますが、これは認められていません。消費者がわかりやすく提示する必要があります。
総額表示しなくてもいいものでまず挙げられるものが、
などです。
対象が多数の個人消費者ではなく、事業者間などでは、総額表示でなくてもよいということです。
しかし、契約書にはきっちりと消費税額を明記しておく必要はあります。経理処理などで消費税の納付額を計上しなくてはいけません。契約者間できちんと契約金額を把握したうえということが前提となります。
そして店内のわかりやすい場所に「当店は外税で表示しています」の一文が必要であり、レジ横に小さく表示などはだめです。
・多数の消費者が対象でなく事業者間の契約書、請求書、見積書においては、総額表示は義務付けられていない。(経理処理の面では、契約書に消費税を明記する必要はある)