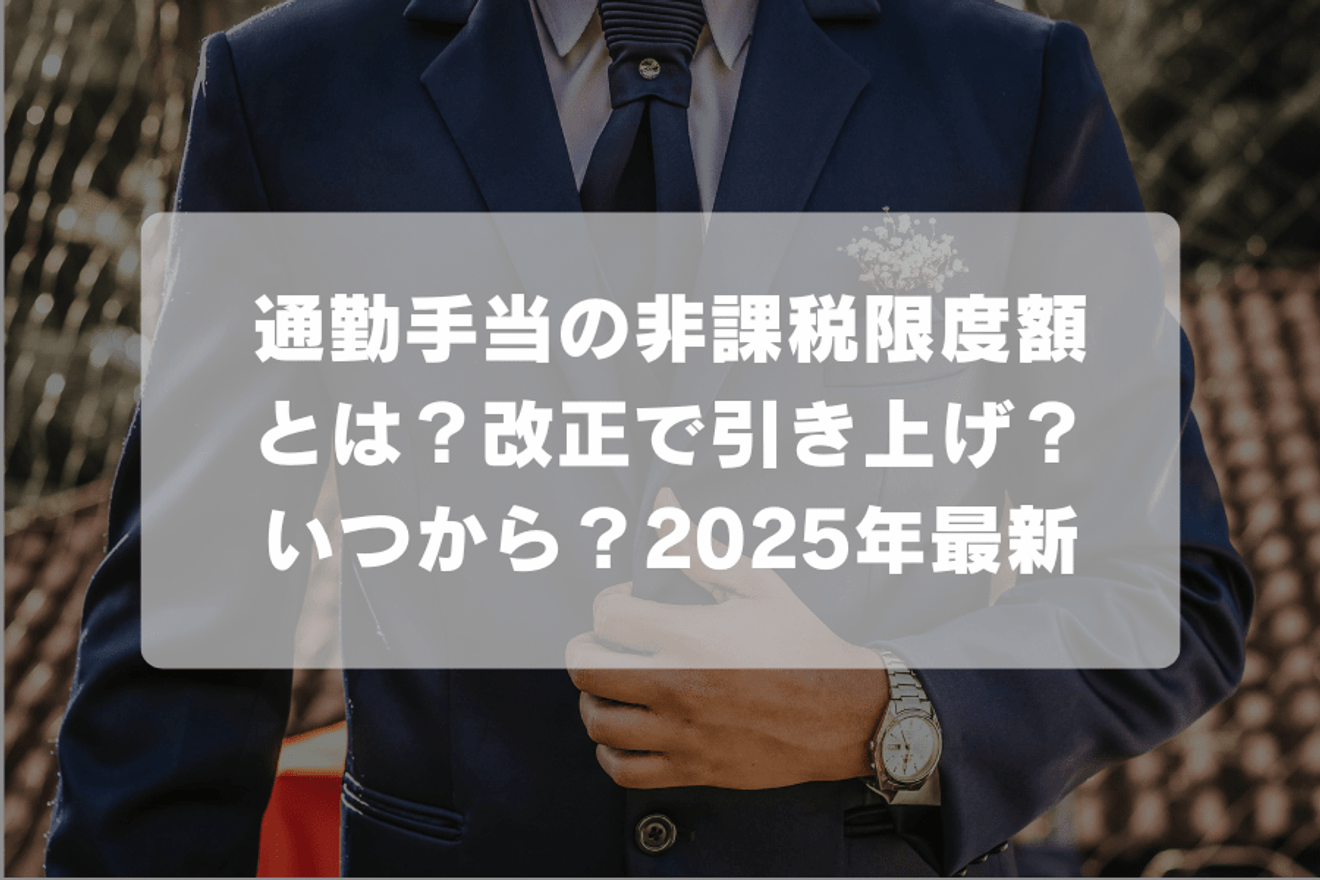
「通勤手当の非課税限度額はいくら?」「最近引き上げられたの?」と気になっていませんか?
この記事では、非課税限度額の仕組みや交通手段別の計算方法まで、最新情報を分かりやすく解説します。
通勤手当の非課税限度額とは、従業員が会社から受け取る通勤手当(交通費)のうち、「所得税がかからない上限金額」のことです。
本来、会社から受け取る金銭は「給与所得」として課税対象になりますが、通勤手当は「業務を行うために必要不可欠な実費」という性質が強いため、国が定めた一定額までは税金をかけない(非課税にする)というルールが設けられています。
国税庁
によると、令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のために自動車などの交通用具を使用する給与所得者に支給される通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
施行日は令和7年11月20日です。この改正は、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(ただし、同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給されるものを除く)について適用されます。
この改正により、令和7年分の年末調整で対応が必要となる場合があります。
1 改正後の非課税限度額
改正後の1か月当たりの非課税限度額は、次のとおりです。
| 区 分 | 課 税 さ れ な い 金 額 | ||
| 改 正 後 (令和7年4月1日以後適用) |
改 正 前 | ||
| ① 交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当 | 1か月当たりの合理的な運賃等の額 (最高限度 150,000 円) |
同 左 | |
| ② 自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当 | 通勤距離が片道 55km 以上 である場合 |
38,700 円 | 31,600 円 |
| 通勤距離が片道 45km 以上 55km 未満である場合 |
32,300 円 | 28,000 円 | |
| 通勤距離が片道 35km 以上 45km 未満である場合 |
25,900 円 | 24,400 円 | |
| 通勤距離が片道 25km 以上 35km 未満である場合 |
19,700 円 | 18,700 円 | |
| 通勤距離が片道 15km 以上 25km 未満である場合 |
13,500 円 | 12,900 円 | |
| 通勤距離が片道 10km 以上 15km 未満である場合 |
7,300 円 | 7,100 円 | |
| 通勤距離が片道 2km 以上 10km 未満である場合 |
4,200 円 | 同 左 | |
| 通勤距離が片道 2km 未満 である場合 |
(全額課税) | 同 左 | |
| ③ 交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券 | 1か月当たりの合理的な運賃等の額 (最高限度 150,000 円) |
同 左 | |
| ④ 交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 | 1か月当たりの合理的な運賃等の額 と②の金額との合計額 (最高限度 150,000 円) |
同 左 | |
改正前に既に支払われた通勤手当について、改正前の非課税限度額を適用して源泉徴収が行われている場合、改正後の非課税限度額を適用することで過納となる税額がある場合には、本年の年末調整の際に精算を行うことになります。
既に支払われた通勤手当が改正前の非課税限度額以下である人については、精算の手続きは不要です。
年の中途に退職した人など、年末調整の機会がない人については、確定申告により精算します。
年末調整での課税済み通勤手当の精算手続きの流れは以下の5つのステップに大別されます。
※出典:国税庁 通勤手当の非課税限度額の引上げについて
以下でそれぞれ詳しく見ていきます。
改正前に既に支払われた通勤手当については、改正前の非課税限度額を適用したところで所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われていますが、改正後の非課税限度額を適用した場合に過納となる税額がある場合には、本年の年末調整の際に精算することになります。
(注)
1 既に支払われた通勤手当が改正前の非課税限度額以下である人については、この精算の手続は不要です。
2 年の中途に退職した人など本年の年末調整の際に精算する機会のない人については、確定申告により精算することになります。
既に改正前の非課税限度額を適用したところで所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をした
(課税された)通勤手当のうち、改正後の非課税限度額によって新たに非課税となった部分の金額を計算します。
「令和7年分給与所得に対する源泉徴収簿」(以下「源泉徴収簿」といいます。)の余白に「非課税となる通勤手当」と表示して、イの計算根拠及び今回の改正により新たに非課税となった部分の金額を記入します。
源泉徴収簿の「年末調整」欄の「給料・手当等①」欄には、「給料・手当等」欄の「総支
給金額」の「計①」欄の金額からロの新たに非課税となった部分の金額を差し引いた後の金額を記入します。
以上により、改正後の非課税限度額によって新たに非課税となった部分の金額が、本年の給与総額から一括して差し引かれることになるため、その差引後の給与の総額を基にして年末調整を行います。
通勤手当の非課税枠の管理など、人事・労務の業務は法改正への対応や細かい規定の運用が求められる、非常に専門性の高い仕事です。
もしあなたが、「もっと自分の専門性を評価してくれる会社で働きたい」「給与計算や労務管理のスキルを活かして年収を上げたい」とお考えなら、士業・管理部門に特化した転職エージェント「ヒュープロ」を活用してみませんか?
ヒュープロは、人事・総務・労務・経理といった「管理部門」の求人に特化しています。 一般的な総合転職サイトには載っていない、優良企業の管理部門求人や、専門知識を高く評価してくれる企業の非公開求人を多数保有しています。
日々の実務で培ったその知識と経験は、あなたが思っている以上に市場価値が高いかもしれません。 まずは無料の会員登録で、どのような求人があるのかチェックすることから始めてみませんか?ヒュープロが、あなたのキャリアアップを全力でサポートします。