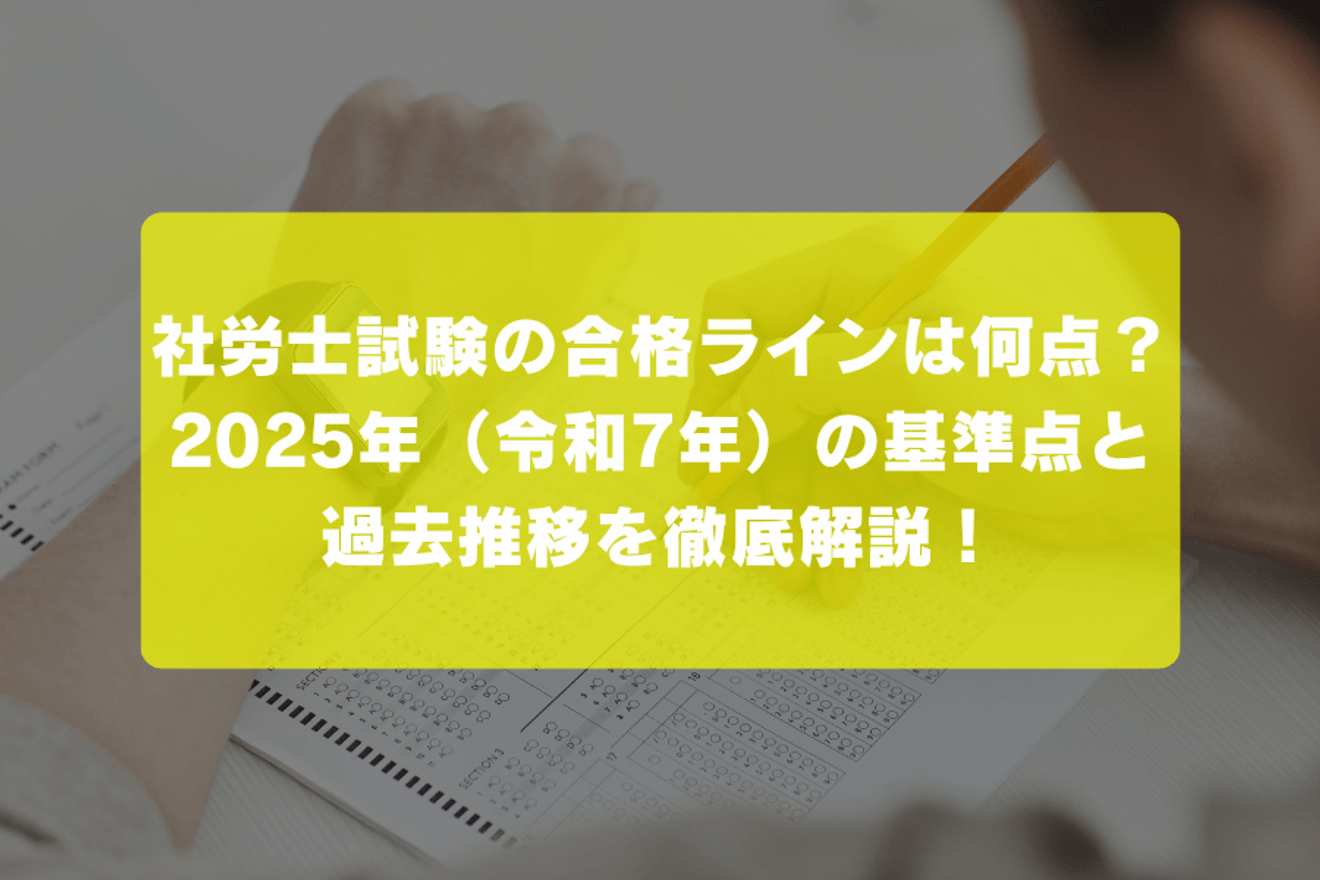
社労士試験の合格ラインは、受験生にとって最も気になる情報のひとつです。この記事では、2025年(令和7年)の最新データをもとに、過去の推移や補正の仕組みも含めて、2026年(令和8年)試験に向けた学習戦略に役立つ情報を徹底解説します。
まず、2025年の社労士試験結果をもとに、以下の点を詳しく解説していきます。
2025年(令和7年)の合格基準点は以下の通りです。
・選択式:総得点22点以上、各科目3点以上
※労働者災害補償保険法、労働に関する一般常識(労一)、社会保険に関する一般常識(社一)は、2点以上
・択一式:総得点42点以上、各科目4点以上
※雇用保険法のみ3点以上
この年の救済措置は、選択式「労働者災害補償保険法」「労働に関する一般常識(労一)」「社会保険に関する一般常識(社一)」で入り、2点で足切り回避となりました。
また、択一式では「雇用保険法」で入り、3点で足切り回避となりました。
試験の難易度が高かったことが背景にあります。
2025年(令和7年)の合格者数と合格率は下記のとおりでした。
受験者数は昨年の43,174名から、258名増えて43,421名でした。
一方で、合格者数は昨年2,974名から598名減って2,376名でした。
受験者数は約4万3000人のなか、合格者数はたったの2,300人弱と、例年通りの狭き門です。
「あと1点足りなかった…」という悔しさを味わった方も多いかもしれません。
社労士試験では、一定の条件を満たした受験者に対して「科目免除制度」が設けられています。これは、過去の試験合格や実務経験などにより、特定科目の受験を免除できる制度です。
2025年では、免除者に対して以下のような固定点数の加算が行われました。
・選択式:免除された科目につき、1科目あたり 2.3点 を加算
・択一式:免除された科目につき、1科目あたり 6.0点 を加算
この加点方式は、免除者が不利にならないように設計されており、満点に対する割合(選択式40点満点、択一式70点満点)を基準に算出されています。つまり、免除された科目が「平均的な得点だった」と仮定して合否判定が行われる仕組みです。
合格ラインは毎年変動します。ここでは、過去5年間のデータをもとに社労士試験の合格ラインの推移と難易度を詳しく見ていきます。
以下は過去5年の基準点の推移です。
| 年度 | 選択式 | 択一式 | 救済措置 |
|---|---|---|---|
| 2024年(令和6年) | 25点 | 44点 | 労一:2点 |
| 2023年(令和5年) | 26点 | 45点 | なし |
| 2022年(令和4年) | 27点 | 44点 | なし |
| 2021年(令和3年) | 24点 | 45点 | 労一:1点、国年:2点 |
| 2020年(令和2年) | 25点 | 44点 | 労一・社一・健保:2点 |
平均点や難易度によって基準点が上下するため、毎年の傾向を把握することが重要です。
以下は、過去5年間分の合格率の推移です。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 43,174人 | 2,974人 | 6.9% |
| 2023年 | 40,633人 | 2,609人 | 6.4% |
| 2022年 | 47,850人 | 2,134人 | 4.5% |
| 2021年 | 49,581人 | 2,937人 | 5.9% |
| 2020年 | 49,250人 | 2,237人 | 4.5% |
社労士試験の合格率は例年5〜6%前後で推移しており、試験の難易度や救済措置の有無によって上下します。受験者数は年々減少傾向にあるものの、合格者数は大きく変動せず、一定数に保たれている傾向があります。
例年5〜6%前後の合格率ということは、受験者の多くは一度は不合格を経験していることになります。今回が残念な結果だった場合でも、継続的な努力が合格につながることには間違いありません。
社労士試験が難しいと言われる理由は、単に合格率が低いことだけではありません。
試験の構造や出題傾向など複数のハードルが存在するため、総合的な対策が求められます。
社労士試験は、選択式・択一式ともに10科目にわたって出題されます。そのうえ、総得点だけでなく科目ごとの最低得点(足切り)が設定されており、1科目でも基準未満だと不合格になります。
このため、「得意科目で高得点を取っても、苦手科目で足切りになる」というケースが少なくありません。特に選択式では、1問の失点が命取りになることもあり、全科目をまんべんなく対策する力が求められます。
社労士試験では、労働法・社会保険法などの法令改正や最新の行政動向が出題されることが多く、過去問だけでは対応しきれない場合もあります。
特に「労働一般常識(労一)」「社会保険一般常識(社一)」では、厚生労働白書や統計資料、時事的な制度改正が問われることがあり、予測が難しい分野です。
受験生の多くが「何を勉強すればいいのか分からない」と悩むポイントでもあります。
社労士試験の合格ラインは、単なる得点だけでなく、試験全体の難易度や受験者の得点分布を踏まえて調整される仕組みになっています。
ここでは、以下の点を詳しく解説していきます。
社労士試験の合格基準点は、満点の約6〜7割を目安に設定されます。選択式は40点満点中25〜28点、択一式は70点満点中44〜46点が目安です。
ただし、これはあくまで目安であり、実際の基準点は毎年の試験の難易度や受験受験者の平均点に応じて補正されます。
たとえば、試験問題が難しく平均点が低かった場合は、合格基準点が下がることがあります。逆に、問題が易しく平均点が高かった場合は、基準点が上がる傾向にあります。
このように、社労士試験は「絶対評価」ではなく「相対評価」の性質が強く、年度ごとに合格ラインが変動するのが特徴です。受験生にとっては、毎年の傾向を把握し、安定して得点できる力をつけることが重要です。
社労士試験では、総得点だけでなく各科目ごとに最低ライン(足切りライン)が設定されています。これをクリアしないと、総得点が合格基準に満たしていても不合格となります。
原則として、足切り条件は以下の通りです。
・選択式:原則3点以上
・択一式:各科目4点以上
この足切り制度があるため、苦手科目の対策は非常に重要です。特に選択式では、1問1点のため、わずか1問の失点が足切りにつながることもあります。
実際、「総得点は合格ラインを超えていたのに、1科目だけ足切りで不合格だった」というケースは毎年多く見られます。こうした悔しさを味わった受験生も少なくないかと思います。その1点を超える力をつけることが、合格への確かな一歩になります。
救済措置とは、特定科目の平均点が著しく低い場合に、足切り基準を一時的に緩和する制度です。これは、問題の難易度が想定以上に高かったとされる場合などに、受験者の不利益を避けるために実施されます。
例えば、2024年(令和6年)は「労働一般常識(労一)」において、平均点が2.0点と低かったため、足切り基準が3点から2点に引き下げられました。これにより、2点得点した受験者は足切りを回避できたことになります。
過去の救済措置の例は下記のとおりです。
| 2021年(令和3年度) | 労一(1点)、国年(2点) |
| 2020年(令和2年度) | 労一・社一・健保(各2点) |
| 2019年(令和元年度) | 社一(2点) |
特に「一般常識科目(労一・社一)」は、出題範囲が広く、時事性の高い内容が含まれるため、毎年救済措置が入りやすい傾向があります。
2026年(令和8年)についても、試験後の平均点や受験者の得点分布によっては、救済措置が実施される可能性があります。試験直後は自己採点を行い、該当科目の平均点速報や予備校の分析をチェックすることが重要です。
社労士試験の合格ラインは、年度ごとの難易度や平均点に応じて変動します。
2025年では、選択式22点・択一式42点が基準となり、「労働者災害補償保険法」「労働に関する一般常識」「社会保険に関する一般常識」「雇用保険法」では救済措置が入りました。
過去の推移を見ても、一般常識科目を中心に足切りや補正が行われる傾向が強く、苦手科目の対策が合否を左右します。過去データを参考に、2026年では「基準点+α」を目指す戦略的な学習が重要です。
合格率は例年5〜6%台で推移しており、狭き門であることに変わりはありません。しかし、合格者の多くは一度は不合格を経験しており、継続的な努力が合格につながります。
社労士資格は、転職やキャリアアップに活かせる強力な武器です。資格取得後のキャリアを見据えている方は、士業・管理部門に特化した転職エージェント「ヒュープロ」にぜひご相談ください。あなたのキャリア形成を、専門的な知見でしっかりサポートいたします。