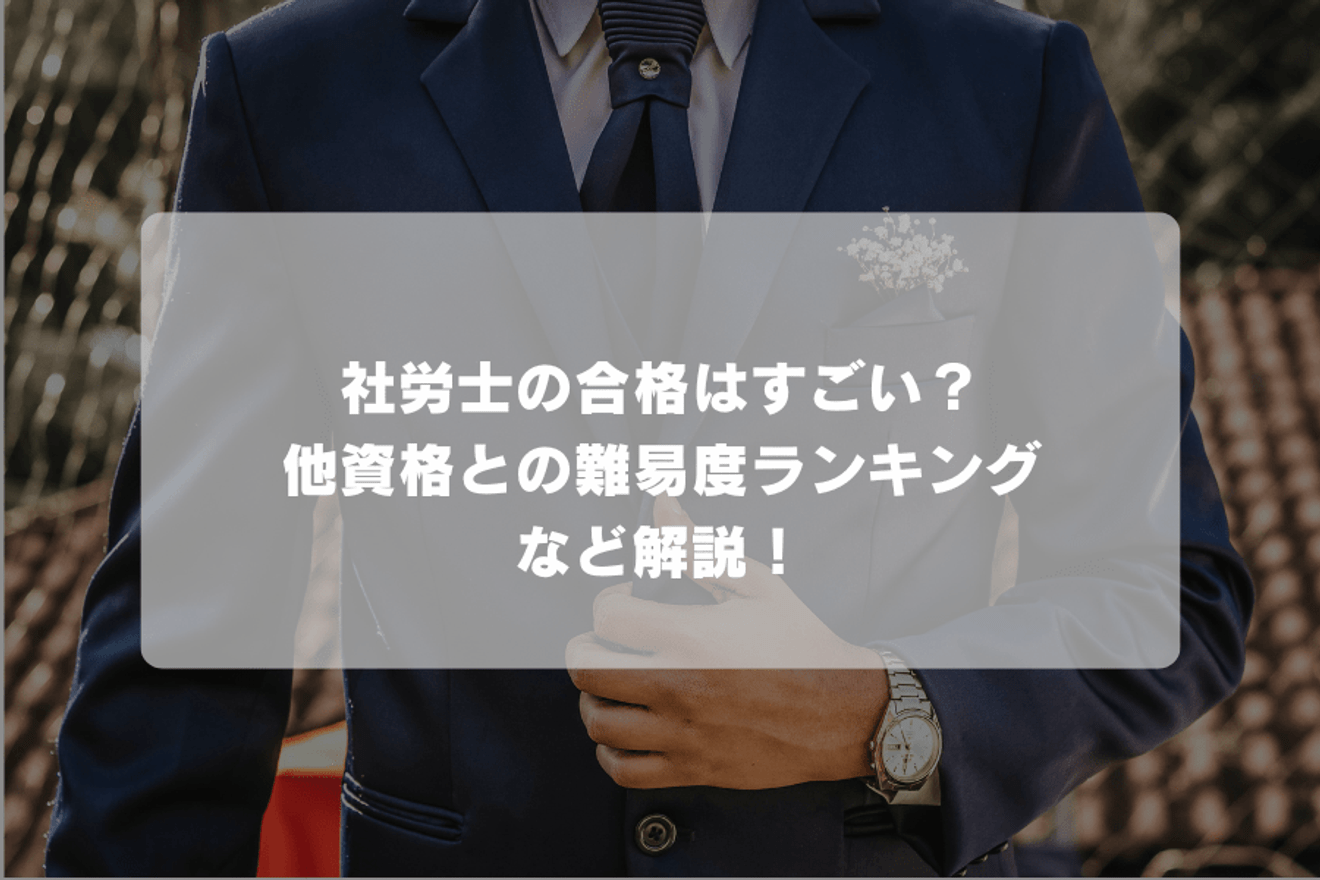
「社労士試験に合格したら本当に“すごい”の?」受験を考えている方や、すでに勉強を始めている方なら一度は気になる疑問ではないでしょうか。
社労士は人事労務・社会保険の専門家として企業や社会で必要とされる国家資格であり、その合格は決して簡単なものではありません。
この記事では、
について解説していきます。これから受験を考える方にとって、合格がどれほど価値あるものかを理解し、学習のモチベーションにつなげていただければ幸いです。

社会保険労務士(以下、社労士)試験の合格は「すごい」と考えられます。ここでは、社労士資格の「すごさ」を示す以下の2点について解説します。
社労士試験は国家資格の中でも難関に位置づけられています。合格率は例年5〜8%前後と低く、受験資格に一定の学歴が必要な点も難しさの一因です。
つまり「誰でも簡単に受けられる資格試験」ではなく、挑戦のハードル自体が高いため、合格できること自体が社会的に評価されるのです。
社労士に合格した人は「知識と努力を証明した人材」として評価されます。特に、管理部門(人事・総務・労務)や社会保険労務士事務所ではキャリアの幅が広がり、年収アップにつながるケースも多く見られます。
「周囲に“すごい”と驚かれた」「社内での立場が向上した」といった声も少なくありません。資格があることで転職市場での優位性が増すのは間違いないでしょう。
ここでは「難易度」という観点から、以下の切り口で社労士試験のすごさを明らかにします。
| ランキング | 資格名 | 合格率* |
| 1位 | 司法書士試験 | 5%程度 |
| 2位 | 社労士試験 | 5~8% |
| 3位 | 行政書士試験 | 10~14% |
| 4位 | 宅建試験 | 15~19% |
| 5位 | 司法試験 | 39~46% |
*過去5回の値参照
社労士試験の合格率は例年5〜8%と低水準です。これは宅建(15〜19%)、行政書士(10〜14%)と比較しても難易度が高い水準であるといえます。
「合格率が低い=合格がすごい」と言えるのは、この数字を見れば納得できるでしょう。
| 順位 | 資格 | 勉強時間 |
| 1位 | 司法試験 | 6000時間 |
| 2位 | 司法書士試験 | 3000時間 |
| 4位 | 社労士試験 | 800~1000時間 |
| 5位 | 行政書士試験 | 600時間 |
| 6位 | 宅建試験 | 300~400時間 |
社労士試験に必要な勉強時間はおよそ1,000時間以上とされています。行政書士(600〜800時間)、宅建(300時間程度)と比較すると、圧倒的に必要な勉強時間が多いのが社労士試験の特徴です。
「フルタイムで働きながら合格できるのか」と悩む方も多いでしょう。確かに楽な道ではありませんが、学習時間をしっかり確保して合格できた場合、「ここまで努力した自分」を誇れること間違いなしです。
社労士になると、以下のような専門性の高い業務ができるようになります。
以下でそれぞれ詳しく見ていきます。
社労士になるとできるすごいこととして、1号・2号業務があります。
社労士の1号・2号とは一般的に社会保険労務士法第2条1項1号・2号のことを指します。これらの業務は社労士の独占業務です。
社労士の第1号業務とは、社会保険労務士法第2条1項1号に定められている、労働保険の書類の作成・提出代行や、健康保険・雇用保険などへの加入・脱退手続き、給付手続きや助成金の申請などを指します。また、これらの書類作成にあたっての相談に応じることも含まれます。
これら1号業務は社労士及び弁護士の独占業務であり、法律上弁護士・社労士のみが実施可能とされています。
社労士の第2号業務とは、社会保険労務士法第2条1項2号に定められている、労働社会保険諸法令に従う帳簿書類の作成、労働者名簿や賃金台帳の作成請負、就業規則や各種労使協定の作成などを指します。また企業が常時10名以上の従業員を使用する場合は、就業規則の作成が義務付けられています。
これらの業務も社労士の独占業務です。
社労士になるとできるすごいこととして、3号業務(コンサルティング業務)があります。
3号業務とは、事業における労務管理、その他の労働に関する事項及び、労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、または指導することを指します。
これらは1号・2号業務と異なり社労士の独占業務ではありません。そのため、これらに習熟した実務経験者や中小企業診断士などが担うこともあります。
しかし、その一方で社労士が担うことも多く、まさに社労士になるとできる業務の一つであるといえます。
社労士になるとできるすごいこととして、社会保険や年金の相談に応じることがあります。
これらは社労士の独占業務ではないため、FP資格保持者や銀行員なども行うことがあります。
しかしその一方、社会保険や年金制度に関して広く学んでいる社労士にも活躍の余地があるといえます。
社労士になるとできるすごいこととして、資格試験予備校の講師として社労士講座を担当することがあります。
一般的に資格試験の予備校講師は、その資格の合格者が担当します。その資格に合格していない人から教わるというのは受講者からすると不安になりますよね。
そして社労士試験は合格率が例年10%以下であるなど非常に難易度の高い試験であることが知られています。
多くの資格試験の中でも、難易度が高く合格者数が限られる社労士試験は講師としての需要も豊富であると言えるでしょう。
社労士になるとできるすごいこととして、社労士関連の記事執筆が挙げられます。特に昨今はインターネット上の記事が多く存在します。
これらの記事のうち、社労士の試験や制度に関する内容に関しては、一般的に社労士有資格者による執筆が好まれます。
例えば社労士試験合格のための勉強方法について知りたいときに、試験に受かっていない人による勉強方法解説を見ても不安ですよね。
社労士に合格したいなら実際に合格した人の勉強方法を知りたいと思うのが通常です。そこで、社労士合格者による執筆の需要があるのです。
昨今ではクラウドソーシングサイトなどで、ネット完結で副業としてライティング業務に携わることも可能です。
社労士試験に合格するのは間違いなく「すごいこと」であると言えるでしょう。合格率の低さ、必要な勉強時間の多さ、そして合格後に得られるキャリアの広がりを考えれば、その価値は非常に大きいです。
ただし、資格を取得しただけでは活かしきれないのも事実です。実務経験を積み、知識を現場で使うことでこそ、社労士資格の価値は最大限に発揮されます。
そのためには、管理部門(人事・労務・総務)や社労士事務所への転職がもっとも現実的で効果的な選択肢となります。
特に、社労士試験合格者のキャリア支援に強みを持つ 管理部門・士業特化型エージェントヒュープロを活用すれば、自分の資格を武器にできる環境を効率的に見つけることができます。
まずは無料の相談からでもいかがでしょうか!
