
「まっとうさ」と「成長スピード」を両立するエス・エム・エス。高齢化という社会課題に向き合いながら、社員の挑戦と自律を支援する財務企画部。その魅力と求める人物像について、部長の中澤牧子氏に伺いました。
ーまず初めに、中澤様の株式会社エス・エム・エスにご入社されるまでのご経歴をお伺いできますでしょうか?
2008年、有限責任監査法人トーマツに入社し、最初の3年間は、IPO準備を含む売上500億円規模の企業の監査業務を担当していました。
その後、IFRSコンサル部署に異動し、エネルギーセクターを中心とした多様なプロジェクトに携わります。最終的にはカナダに駐在し、海外拠点での業務も経験しました。
2017年6月、自然電力株式会社に経理責任者として入社しました。監査法人時代に上場企業への知見はあったため、次は非上場で、かつユニークなエネルギー企業に挑戦してみたいという思いが芽生えたのがきっかけです。
ー2019年に株式会社エス・エム・エスにご入社されました。エス・エム・エスを選ばれた理由についてもお聞かせいただけますでしょうか?
前職の非上場企業で働くことで、投資家やステークホルダーに情報開示することの重要性について改めて興味がわき、上場会社でマネジメントをやってみたいと意識が変化したことがきっかけとなります。
その上で、日本が世界に先駆けて直面する高齢社会という課題に事業を通じてアプローチできる点に、強く魅力を感じました。そして、最終的な決め手は役員との面接です。
純粋に話していて、「どこまで深く思考がめくられていくんだろう」という感覚が面白かった点、その後のオファー面談で3時間かけてマーケットの環境と事業拡大の方向性等をご説明いただき、ここまで言語化して説明しきる聡明さに心惹かれました。

ーもともとは経理財務グループ長としてご入社されて、現在は財務企画部長としてお仕事をされているそうですが、現在の業務内容についても詳しくお伺いできますでしょうか?
財務企画部は、「経営と事業の不可欠なパートナー」として、意思決定と実行の双方を支える役割を担っています。コーポレート機能の一翼として、単なる数値管理にとどまらず、全社最適の実現をミッションとしています。
具体的には、事業フロント以降の数値を取りまとめ、IR対応や予算策定を通じて、全社の方向性をマネジメントと共に検討しています。数値管理だけでなく、ノンコア業務の巻き取りやオペレーション改善、コスト削減交渉など、利益への直接貢献も重要な業務です。
また、事業と経理・IRをつなぐ“前後工程の理解”を大切にし、社内のオペレーション全体を標準化・自動化することで、ルーティン業務を減らし、より事業に深く入り込む体制を整えています。
「領域を決めず、会社のために必要なことは何でもやる」。これが財務企画部のスタンスであり、他部署との自律的な連携を通じて、最適なリソース配分とスピーディな意思決定を可能にしています。
ー「財務企画部の仕事はこれ!」と決めつけないのがエス・エム・エス流。幅広い業務を担う中で、事業部からの依頼も多いと思いますが、どのように優先順位を決めているのですか?
まずは各事業部に「このタスクの重要度と緊急度は?」とヒアリングします。すると、事業部同士で自然と優先順位が調整されていきます。この自律的な連携こそ、エス・エム・エスの強みです。どの事業部も自分の部署のことをなるべく早くやってほしいと考えますが、事業部同士で横でディスカッションし、リソースを勘案し、現実的な打ち手とスケジュールに収れんされていきます。このディスカッションを積極的に行うという社風は、当社の良い点だと思います。
ー財務企画部の組織構成についてもお伺いできればと思います。
財務企画部の組織構成は、経理財務・販管経理第一・第二・事業支援および海外子会社管理グループを2025年4月以降に新設し、合計5つのグループで構成される予定です。
販売プロセスを除いた全社経理業務(給与、支払、精算、連結、税務、監査対応など)と、それらの業務改善を担います。
全事業の販売プロセスを担当。40以上あるサービスの商材やステージに応じ、新商材・新規ビジネスの立ち上げに向けて事業側とともにオペレーション設計・運用を行います。
ミドル・ノンコア業務の巻き取りや業務改善など、フロント支援が主な業務です。
海外子会社の経理担当者と連携し、業務改善を推進します。
2024年3月までは、購買グループも財務企画部に所属していたのですが、当初のミッションである「システム導入」と「経理との連携」という役割を十分果たしたので、次のミッションへ向けて別の部署にグループごと移管予定です。このように必要とされる形に柔軟に組織を変化できることも財務企画部の強みです。
ーお話しいただいたように変革を続けている御社の財務企画部ですが、どのような方が向いているとお考えでしょうか?
「自分で成果定義をし、最適なアプローチを自分で思考し行動すること」を求めています。
同時に、会社で働く他メンバーも同様に自分で成果定義をし、思考して行動しています。自分の成果だけでなく他者の成果にも貢献するために臆せず指摘し、全社最適を考えながら他者と協力していくことも必要となります。
言い換えると、自律して、成長意欲があり、失敗や指摘を受け入れられる素直な心がある方。そして、他者に自分の思考を理解して頂けるだけの言語化スキルがあり、他者と協力して、1人ではできないことを実現していくことに興味がある方が活躍できると思います。
あとは今までの経験とご本人のキャリアの希望とその時に必要なポジションによって決まりますが、グループごとに要件の差異はないです。強いていえば、経理財務グループのマネジメントには、英語力の読み書きと連結開示のスキルが必要ですが、他は特にこだわりはないです。
ー具体的なスキルセットよりもマインドセットを重視しているということなのですね。
そうですね、常に学んでいただく必要がありますし、新しい環境や方法を受け入れられる方を求めています。学んで、体系化して、形にしていくという柔軟性がある方であれば、スキルは重視していないです。
ー上司からミッションやKPIを渡される企業が多い中で、御社は自分で成果定義をするとのことでした。
会社やグループ内の方向性を示したうえで、その中で自分のやりたいことを選んでもらう形を採っています。会社のやりたいことに全て「Yes」と答えてしまうと、その方が上司になられた際に困ることになります。メンバーであっても、自分で考えるということを重視しています。
ー場合によってはマネージャーレベルの方がやるようなことにも感じられるのですが、新しく入られた方は初めからすんなりとできるものなのでしょうか?
特に最初のステップである「問いを立てる」ことに、多くの方が戸惑います。問いを立てた後、何をすればよいかわからなくなったり、一度うまくいかないと手が止まってしまったりすることもあります。
ですが、問いを立て、提案し、周囲の意見を受け入れて改善し、再実行する——この一連の流れこそが、成長に直結するプロセスです。どんなに小さな問いでも構いません。まずは、そのサイクルを回してみることを大切にしています。
ー他にもマインド面で向いている方の特徴はありますか?
先ほどもお話ししましたが、当社の財務企画部は「領域にこだわることなく何でもやる」という特徴があります。この「領域」というのは必ずしもコーポレートの仕事だけではなく、事業側と協力しながら様々な業務に取り組む必要があります。そのため、自分の仕事だけにコミットするというよりは、会社が最善の動きができるよう、主体的に取り組む方が当社で活躍できると考えています。
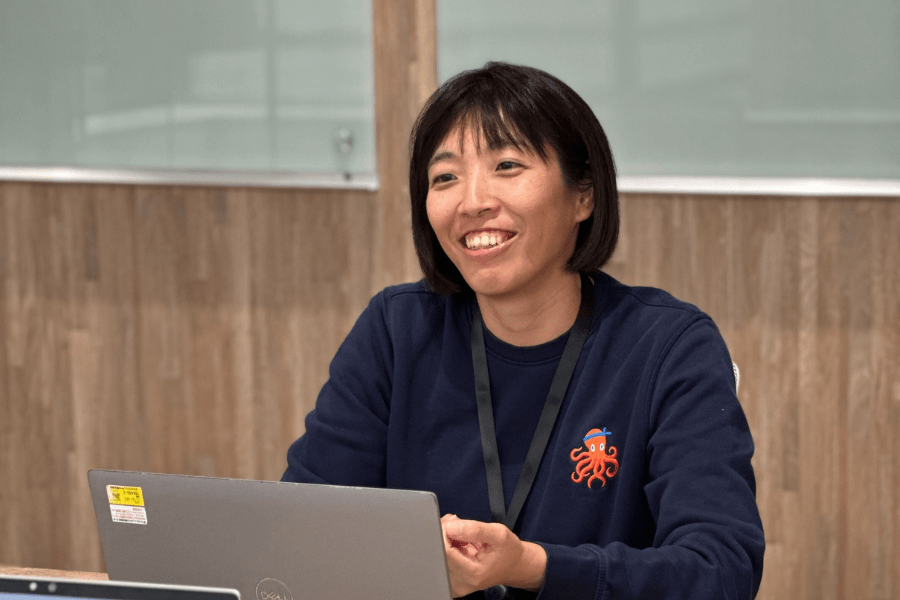
ーありがとうございます。そんな株式会社エス・エム・エスで働く魅力はどんなところにあるとお考えでしょうか?
一言でいうと、「まっとう×成長スピード」です。
監査法人在籍時、色々な会社にお邪魔させていただき、世の中にまっとうな会社は多々あります。成長著しい会社も多々あります。ただ、「まっとう」と「成長スピード」を両立している会社は意外と少ないと感じていました。
特に財務企画部は、内部監査室とともにコンプライアンスの砦なので、「まっとう」であるということは、心理的安全性の観点からも非常に大事なことだと考えています。面接でも、財務企画領域に応募される方から、コンプライアンスについてよく質問をうけます。専門領域だからこそ、気にする方が多いのでしょう。
「まっとうさ」は、単なるコンプライアンス遵守にとどまりません。エス・エム・エスならではの特長が、いくつも存在しています。
一つ目は「リレーション」です。
「お互いにフィードバックをするのが当然」というカルチャーが、会社のまっとうさを担保していると考えています。「新設グループを作るのであれば、中澤さんのリソースを考えると、既存のグループの中で中澤さんがやらないことをもっと増やすべき」という面白いフィードバックを、最近部下からいただきました。同様のフィードバックを、私からマネジメントや同僚の部長へも行いますし、事業部にも行います。
経理として、「だめなものはだめです」とマネジメントにも事業にもご説明することはあります。お互いの常識や優先順位が異なるため、経理の常識からすると悪意なく想定外の質問を受けることもよくあります。その上で経理の常識を説明し、ご理解いただけなかったことは一度もありません。両者の関係性は非常に対等だと感じます。
ー事業部・コーポレートの関係構築に苦戦したり、対等な連携が取りにくいという企業さんも見受けられ、試行錯誤されている印象です。そんな中で御社が両者の対等性を維持している秘訣はありますか?
まず第一に全社の戦略が各部の中に浸透し、全社戦略をもとに各部の戦略が縦につながっています。自部門戦略の達成のみ優先したとしても、全社戦略が達成できなければ会社としての達成ではないことを、各事業責任者は理解しています。
エス・エム・エスには事業ステージの異なる40以上のサービスがありますが、コーポレートも含めてそれぞれの事業ステージと役割にリスペクトがあります。極めて普通のことですが、安定してキャッシュを稼げる事業があるからこそ、新規事業に投資ができる。新規事業があるからこそ将来にわたって成長し続けるということを事業責任者もコーポレートも理解しているため、相互のリスペクトがあります。
また、「戦略を実行するためのリソース」を重視しているという点も特徴かもしれません。成長を掲げる会社は多いですが、成長に必要なリソースまで考えるように促してもらえる会社は少ないです。当社は、「戦略・人材・オペレーション」という「経営プロセス」をもとに、自分で決めた成果定義(戦略)には、実現に向けて必要なリソースとオペレーション策定までお願いしています。
「まっとうさ」は自然にあるものではなく、日々努力して維持しています。ルーティンをそのまま継続すれば維持できるものではなく、やはり最初にリレーションがあって、社会課題の解決がしたいという感情があって、加えてリソースを無理なく回すという働き方も含めて、「まっとうさ」を担保できるようにしています。
ーここまで何度か「社会課題」という言葉を使っていただいたと思うのですが、「社会課題の解決がしたい」というのも御社で大事にしている部分なのでしょうか?
そうですね。多くの企業が利益最大化を目指して事業を展開していると思います。もちろん当社も増収増益を掲げており、利益の最大化を重視しています。同時に収益性だけを追い求めるのではなく、社会的課題の解決ができるかどうかという視点で事業に取り組んでいます。そのようなスタイルに魅力を感じていただけると嬉しいです。
ーありがとうございます。魅力のもう一つとして挙げていただいた、「成長スピード」を支える要素についてもお伺いできればと思います。
増収増益の目標を掲げていることも要因としてありますが、3つのカルチャーが成長を支えていると感じます。
まず一つ目が、「失敗してよい、とりあえずやってみる」というカルチャーです。
「経営プロセス」を自分で回す中で、最初からすべてがうまくいくことはないので、ある程度失敗しても問題ありません。失敗を恐れて何もやらないよりは、何度もトライしていつか成功させることの方が圧倒的に評価されます。もちろん無謀な挑戦とならないように小さく試行錯誤を繰り返しながら改善していくことが大切です。
二つ目が、「ダイバーシティーが担保されている」ことです。
中途比率が高く、バックグラウンド・年齢・性別・社歴にかかわらず活躍できる環境があります。私自身も入社2年で部長を経験させて頂けるとは思っていませんでした。会社にとってよいと思ったものはどんどん受け入れる、という社風が成長を支えています。
三つ目は、「やってみてうまくいかなかったことは、やめることができる」という点です。
よいと思ってはじめてみたが、「実は良くなかったが言い出せない」ということはよくあると思います。当社では、「進める」だけでなく「止める」ということも同じぐらい大事なこととして評価されます。
「止める」という判断は勇気がいるものですが、当社ではそれを正当に評価する文化があります。無理に仕事を維持し続けるのではなく、新たなチャレンジのための余白を生む手段として「止める」ことを捉えています。だからこそ、常に増収増益を目指し、次の挑戦にリソースを投資できる環境が整っています。
ーこれまで御社での業務に向いている方やカルチャーについてお伺いしてきましたが、そういった環境でキャリアを歩んでいく方々の評価は、どのようにされているのでしょうか?
お話した通り、ご自身で成果定義を行うという特徴があります。財務企画部においては、上長である私と「何をもって成果が達成できたといえるのか」という評価軸まで合意し、目標設定を行っていただきます。
その後、1on1を毎週実施する中で進捗を確認し、途中で成果定義がかわっていくこともあります。毎期末には、結果としてこの1年で達成した成果はなんだったのか、ご自身としてどういう点が成長したのかということを言語化していただきます。
これらを踏まえて、コーポレートの部長陣で、互いの部署へフィードバックもしつつ最終評価を決めていきます。他部署の部長からの評価もとても重要で、単年度の実績だけでなく、ご本人の能力がどれだけ成長したのか、そして成長したことを多くの部署の方に共感していただけるか、という点によく気づかされます。
評価はメリハリがありますので、ステイが続く方もいれば、毎年飛躍的にアップしていく方もいます。
ーこの評価制度を取り入れて良かったと感じる事例などはありますか?
キャリアラダーの良い事例でいうと、購買グループのグループ長の採用に苦慮し、同僚の部長に相談したところ、「現オフィスグループ長が購買グループ長を兼務すると、ご本人のキャリアとして、購買グループとして、より大きな視座で会社としてもよいのではないか」という提案を頂きました。オフィスグループ長からも即座に快諾いただき、相談後3か月ほどで就任いただきました。
上記のように既存の領域にとらわれず、全社最適の視点で自らの役割を拡張し、組織を設計し、会社に貢献していくことができる会社は珍しいのではないかなと思います。
ー最後に、どのような方に応募してほしいとお考えか、また応募を希望されている方へのメッセージをお願いいたします。
「自分で戦略を立て、リソースを確保し、オペレーションを設計し、関係者を巻き込みながら解決していく」——このプロセスそのものに価値を感じてくれる方に、ぜひご応募いただきたいです。
決算を締めて、分析結果を出力するだけの業務は、将来的には生成AIでも代替可能になるかもしれません。
だからこそ、「問いを立てる」「全体戦略の中で意味づける」「人を巻き込みながら意思決定と実行を進める」といった、人間にしかできない価値創出が、ますます重要になると感じています。
「コーポレートが、全社に本質的な貢献をもたらせる奥深く、面白い仕事である」と実感できる会社だと思います。会計士や税理士として専門領域を極める会社ではないですが、会社とはこのように運営されて成長していくのか、そして自分の仕事が会社への貢献にどのように繋がっていくのかということを、マネジメントや事業の方と協業を通して、実体験をもって感じられます。
メンバーであっても、年齢や経験、スキルにかかわらず、自分で決めて自分で裁量を持って実現できることが、魅力の一つでもあります。
是非、ご応募お待ちしております!
お話を伺った株式会社エス・エム・エスのHPはこちら
株式会社エス・エム・エスの採用ページはこちら
