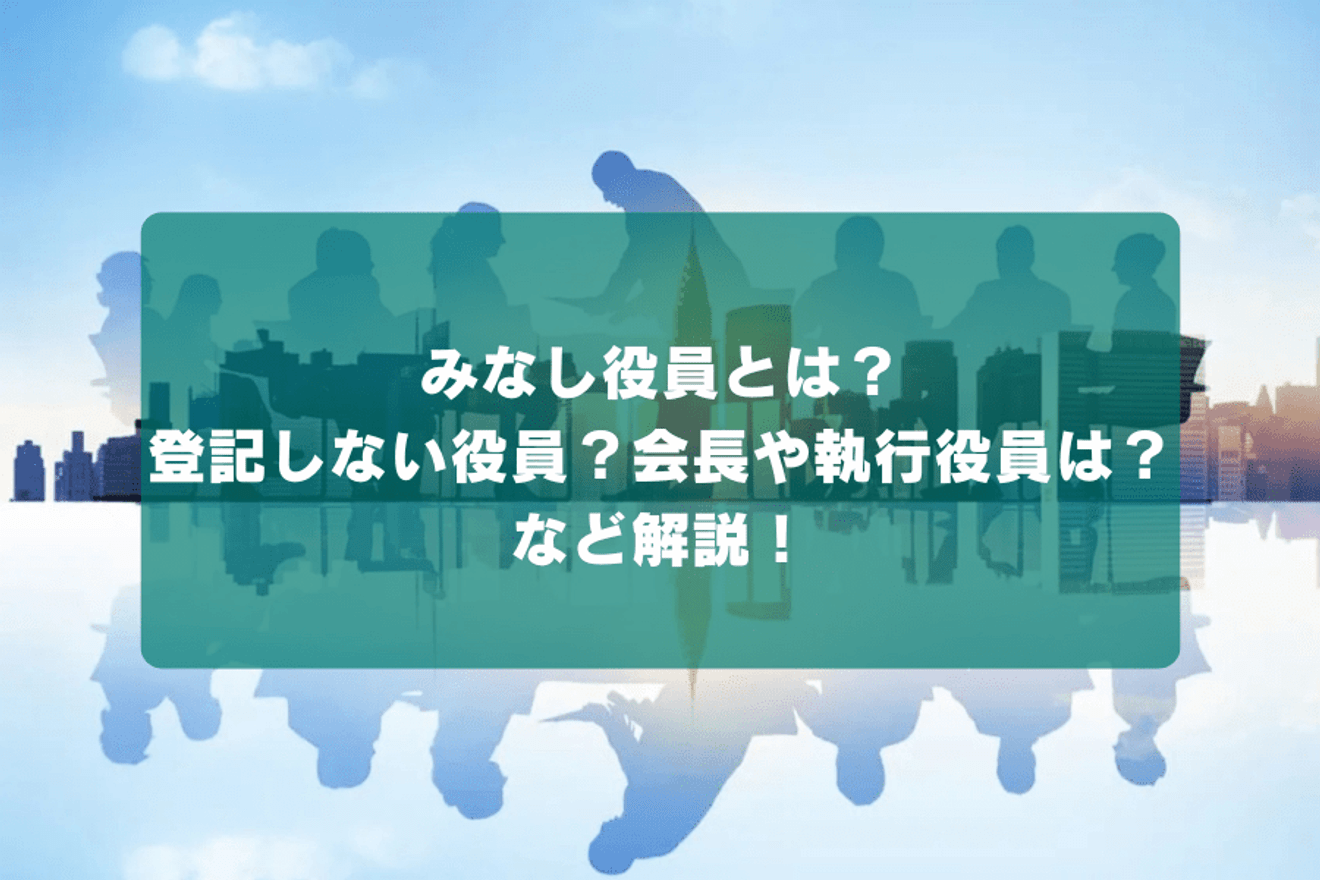
税務調査で会社の登記上は役員として登記していなくても、法人税法上では役員としてみなされる場合があります。
こうした人たちは「みなし役員」と呼ばれ、その報酬に制約がかかることになるのですが、なぜそのようなことをするのでしょうか。
本記事では「みなし役員」について解説します。

会社法で役員という場合は、株主総会で選任された取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人を指します。
しかし、法人税法上においては、役員報酬の取扱についてより実効性を高めるため、登記上だけではなく、役員報酬や経営への参画、株式の取得状況などの実態に応じて役員と解釈します。これを「みなし役員」といいます。
つまり、役員登記していないにも関わらず、法人税法上はその給与や賞与は役員報酬として扱うことになるのです。
なお「みなし役員」はあくまで法人税法上の概念なので、「会社法」や「労働基準法」においてはあくまで「従業員」・「雇用されている側」になります。
そのため、登記上の役員とは異なり、雇用保険や労災保険の被保険者になることが可能です。
◆みなし役員とは
・法人税法上→役員と同じ扱い
・会社法・労働基準法上→「従業員」・「雇用されている側」として雇用契約を締結。雇用保険や労働保険の対象となる。
どのような実態がある場合「みなし役員」としてみなされるのでしょうか?以下についてそれぞれ詳しく見ていきます。
役員でも使用人でもないのにその経営に従事している人とみなされるのは、具体的には以下のケースです。
出典:国税庁HP|タックスアンサーNo.5200 役員の範囲
これはいわゆるファミリー企業の使用人でありながら、株式の所有割合が高く、会社の経営に携わっている人が該当します。
出典:国税庁HP|タックスアンサーNo.5200 役員の範囲
中小企業では、一般的に家族はこの持株割合の条件を満たしているケースがほとんどです。
どちらも、会社の「役員」としては登記されていませんが、その役職や株式保有率に加え、会社の重要な意思決定に関わっていることが「みなし役員」とされる条件となっています。
この「会社の意思決定に関わる」については、どの程度の参画なのかによって「みなし役員」とするかそうでないかの判断が別れます。詳しくは税理士など専門家に確認しましょう。
執行役員というポジションは、会社法上必ずしも役員として登記されているわけではなく、雇用契約または委任契約の関係で設置されていることがあります。
税務上、一般的には「取締役会の議決権を持たない」「経営方針の決定ではなく日常業務・執行が中心」といった執行役員は、使用人扱い(=役員ではない)という考え方が有力です。
ただし、実際には「執行役員が経営の重要な意思決定に関与している」「会社の経営に実質的に従事している」と認められる場合には、税法上のみなし役員と判断されるケースがあります。
みなし役員というのは、役員ではありませんが、その給与は「役員報酬」とみなされます。従業員の給与と役員報酬には以下のような違いがあります。
従業員の給与・賞与は「給与手当」として全額損金です。また、従業員の給与・賞与については、本人の成績や会社の業績、さらには時間外勤務の手当などで毎月変動があるなどします。
これは給与規程に定めた範囲内で、会社が自由に決めることができます。
役員報酬は、従業員に対する給与手当とは異なり、「定期同額給与」の条件を満たしていない場合は経費になりません。
その額の増減には株主総会の決議が必要で、自由に変えることはできないのです。
仮に、役員報酬を期中で増額しても、増額分は経費とは認められませんし、逆に減額すると減額前に多く払っていた金額が経費として認められないということになります。
みなし役員もこれと同じで、使用人でありながらその報酬は簡単に変えられないという制約を受けることになります。
みなし役員についてが、使用人でありながら役員報酬とみなされるのは、企業側による利益操作と過度の節税を防ぐ目的があります。
ほとんどの中小企業は、オーナー経営者とその一族が株式を持っているため、役員報酬を自由に決めることが可能です。
家族であることが多いみなし役員の報酬を使用人と同様に給与手当として取り扱うと、法人税の支払いを逃れる手段を与えることになってしまいます。
例えば急に自社商品がヒットして予期せぬ利益が出たというような場合に、家族である使用人が従業員扱いであったら、利益分を賞与を与えてこれを損金とし、利益はなかったものとして法人税の支払いを行わないというような脱税行為を行うことができてしまうのです。
これは極端な例ですが、家族を社員として給与・賞与を支払っていると「みなし役員」として税務調査で指摘され、追徴課税を課されるケースも多々あります。
「みなし役員」については、定義よりもその実態で該当するかどうかを判別するため、詳しくは税理士など専門家に確認することをおすすめします。