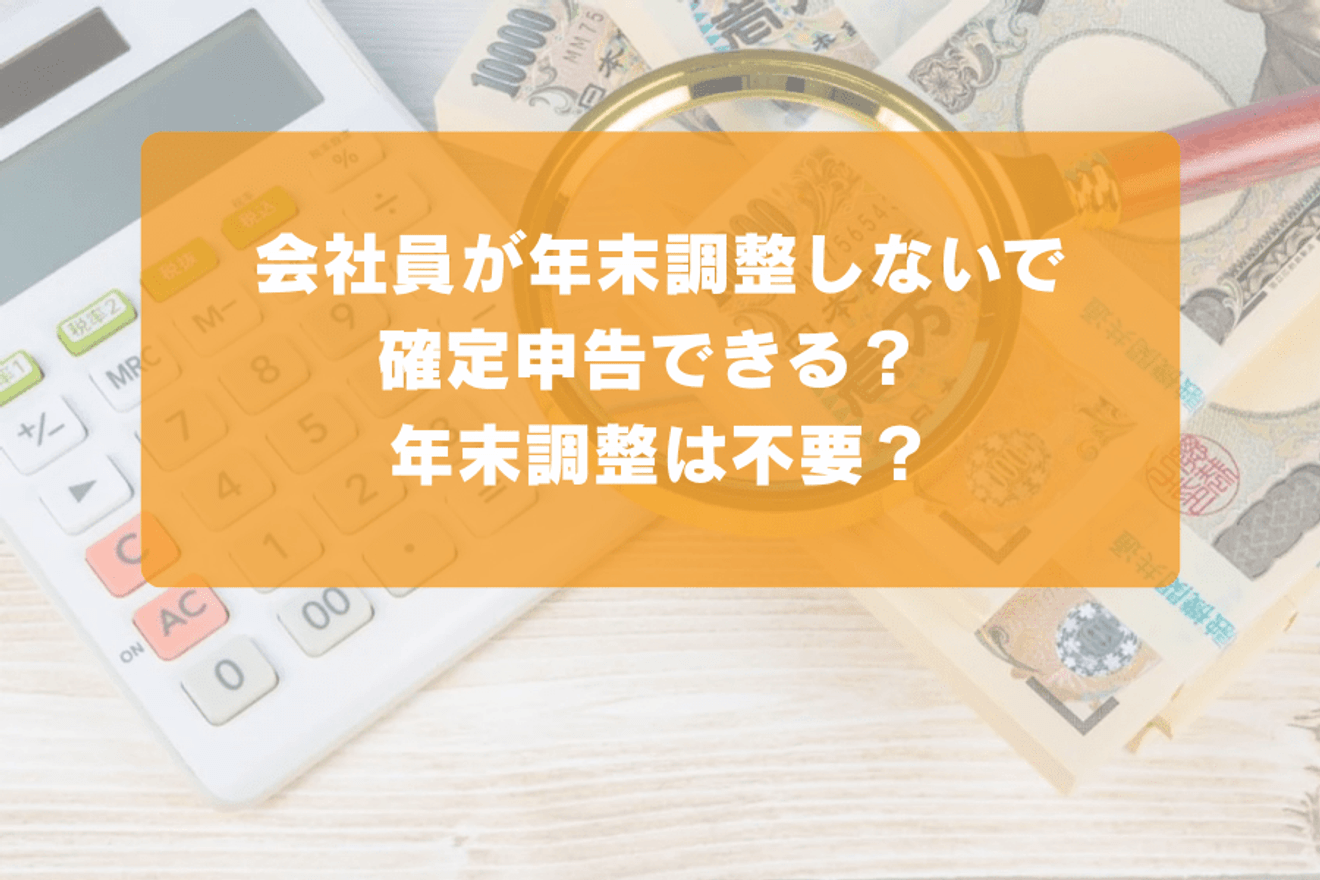
毎年12月は年末調整の季節です。年末調整では、源泉徴収していた所得税を、実際の年収に応じて差分を調整します。
しかし、住宅ローン控除や医療費控除を受けようという方は、いずれにしても確定申告をすることが決まっている方は、二度手間なので年末調整をしなくても良いのではないかと思うかもしれません。
このような場合、年末調整をせず確定申告だけで済ませることができるのでしょうか?この記事では会社員が年末調整しないで確定申告できるかなどについて解説します。
会社員が年末調整しないで確定することはできません。年末調整は必須です。
年末調整は、個人が受ける受けないを選択できるものではありません。会社などに一年を通じて勤務している人や、その年の中途で就職し、年末まで勤務している人(青色専業事業専従者も含みます)も対象になります。
会社や事業所に年末まで勤務しているにもかかわらず、年末調整を受けない方は、以下のいずれか二つに当てはまる人のみです。
年末ではなく年の途中で年末調整を行う場合もあります。その対象になるのは以下の人たちです。
したがって、年の中途で退職した人で(1)~(5)以外の人は年末調整の対象となりません。
出典:国税庁WEBサイト タックスアンサー No.2665 年末調整の対象となる人
なお年末調整については、所得税法第190条にその詳細が定められています。
法律で定められた制度として対象外の方以外は全て年末調整を受ける義務があるといえるでしょう
参考:国税庁WEBサイト 第190条《年末調整》関係
まず、前項で揚げた以下の2つのいずれかの条件に当てはまる人は、会社や事業所に年末まで勤務しているにもかかわらず、年末調整の対象外なので、確定申告を行う必要があります。
また、以下の条件に当てはまる人も、源泉徴収されている所得税があったとしても年末調整は行われません。
個人事業主など給与所得者ではなく開業している場合は、確定申告は必須ですが、年の途中で退職した人でその後再就職していない人(かつ退職金が退職所得控除内に収まっている人)は確定申告の対象ではありません。
しかし、申告を行うことで払いすぎた税金を取り戻すことができる場合があります。

年末調整は会社がすべきことなのですが、小規模な会社やワンマン企業などでは会社が年末調整をしてくれない(もしくは年末調整業務自体が忘れられている)ということが時にはあるようです。
こうした場合にまず確認したいのは、給与から源泉徴収されているかどうかです。
もし給与額が支給分の満額支払われている場合ですと、源泉徴収されていない、つまり税金を支払っていないということになる無申告状態ですので、一刻も早い申告が必要になります。気が付いた時点で、税務署に確認しましょう。
次に、源泉所得税は引かれていても、年末調整がない場合については、やはり会社の方で作業が漏れていることが考えられます。
扶養家族がいたり、生命保険などに加入していたりする場合は、確定申告を行うことにより控除されている税金が戻ってくることも考えられます。
何についても、会社が年末調整をしてくれないという場合は、自分で確定申告をする必要があります。源泉徴収票など必要な書類をそろえて確定申告を行うようにしましょう・
なお源泉徴収と年末調整については会社の義務ですので、従業員が自身で確定申告を行っているからといって年末調整をしないということにはできません 。
従業員や依頼先に源泉徴収を行った上で所得税を納付しないと、不納付加算税といって会社にペナルティが課せられます。
こうした場合は、国税庁や税務署に情報提供として訴えることも可能です。
・参考:国税庁WEBサイト 課税・徴収漏れに関する情報の提供
会社員の毎月の給与からは、所得税が天引きつまり源泉徴収され、年末に所得が確定してから徴収済みの税額との差額を調整する年末調整が行われます。
それらにかかる業務負担は軽くはありません。なぜこのような作業をしているのでしょうか。
年末調整の元となる源泉徴収制度は、国が確定申告に先立って税収を平準化して得るための手段です。
日本では申告納税制度が採用されています。本来であれば、納税者は自分自身で申告書を作成し、その申告内容に応じて税金を納める必要があります。
しかし本当に国民全員が確定申告をするとなると、その納税業務をさばききれるほどのリソースが行政側にはありません。そこで、 効率的に税金を徴収するために導入されたのが源泉徴収制度です。
毎月の源泉徴収によって給与から税金が天引きされ、所得が確定する一年の最後に、控除が核を確認して年末調整を終えることで、給与所得者のほとんどは自分で計算することなく納税が可能となります。
*国全体と、国民の納税にかかる作業を削減するというメリット*がありますが、会社や事業者の事務負担と、個人の納税意識の希薄化も生んでいるというデメリットもあります。
納税にかかる事務負担の軽減のために、2016年からマイナンバー制度が始まり、企業や事業者では、従業員に対しマイナンバーの提出を義務付けた上で、源泉徴収とマイナンバーが紐付けられるようになりました。
このことから、2019年より確定申告を行う際の源泉徴収票添付が不要になるほか、今後様々な税に関する手続きの簡素化が望まれています。
源泉徴収や年末調整にかかる企業などの事務負担を減らし、給与所得者が納税意識の高めるために、源泉徴収や年末調整を廃止することも検討されてはいましたが、そのためには税金の申告がもっと簡単になる必要があります。
電子申告やスマホでの確定申告など新しいシステムなどが開始されていますが、将来的には原則に則って、所得税の確定申告も不要になる時代が来るのかもしれません。